事業戦略の立て方や改善方法が分からず、企業成長が頭打ちになっていると感じている経営者や担当者は少なくありません。特に「事業戦略 コンサルティング」というキーワードで情報を探す方は、次のような悩みを抱えていることが多いでしょう。
-
自社の方向性が明確になっておらず、戦略が場当たり的になっている
-
新規事業や既存事業の成長戦略をどのように描けばいいのか分からない
-
社内リソースや市場環境を踏まえた最適な事業戦略が組めない
-
コンサルティングを依頼しても成果につながるのか不安
本記事では、事業戦略コンサルティングを導入することで企業がどのように変革し、持続的な成長を実現できるのかを、成功事例と実践プロセスを交えて詳しく解説します。Google検索上位で多く扱われている「事業戦略の立案方法」「市場分析」「KPI設定」「組織改革」といったテーマを網羅し、初心者でも理解できるよう専門用語も丁寧に説明します。
さらに、合同会社えいおうが提供する事業戦略コンサルティングの特徴や、成果を最大化するための取り組み方も具体的に紹介。読了後には、自社にとって必要な戦略やコンサルティングの活用方法が明確になり、すぐに改善の第一歩を踏み出せる状態になるでしょう。
目次
- 1 事業戦略コンサルティングとは?
- 2 戦略コンサルティングを活用するメリットと導入理由
- 3 戦略コンサルタントに求められるスキルと資質
- 4 戦略コンサルティングが扱う主なテーマ
- 4.1 全社戦略・中期経営計画(成長戦略と資源配分の設計)
- 4.2 事業ポートフォリオ最適化(撤退・集中・育成の意思決定)
- 4.3 新規事業開発(PMF達成までのロードマップ)
- 4.4 Go-To-Marketとマーケティング戦略(顧客起点の拡販設計)
- 4.5 価格戦略・収益モデル(利益性の最大化と再現性)
- 4.6 M&A・アライアンス戦略とPMI(統合マネジメント)
- 4.7 DX(デジタル変革)戦略とデータ活用(オペレーティングモデル刷新)
- 4.8 サプライチェーン戦略とコスト構造改革(バリューチェーン最適化)
- 4.9 海外進出・グローバル戦略(現地適合と本社ガバナンス)
- 4.10 ESG・サステナビリティ経営(リスクと機会の統合)
- 4.11 事業再生・ターンアラウンド(短期改善と中期再成長の両立)
- 4.12 組織・人材戦略と変革マネジメント(7Sで要素整合)
- 4.13 実行支援・PMOとKPIマネジメント(戦略の運用化)
- 4.14 主なテーマと成果物・指標の対応表(要約)
- 5 戦略策定に役立つ定番フレームワーク
- 6 成果を高めるための支援プロセスとポイント
- 7 価格戦略・利益性視点を含めた戦略設計
- 8 陥りがちな失敗事例とその防止策|事業戦略コンサルティングの実務
- 8.1 失敗パターンの全体像(要約表)
- 8.2 目標・KPIの不整合で走り出す
- 8.3 データの信頼性が低い・ダッシュボードが乱立
- 8.4 分析過多で実行が遅れる(Analysis Paralysis)
- 8.5 ステークホルダーの巻き込み不足・合意形成の欠落
- 8.6 PMO不在で横串管理ができない
- 8.7 価格戦略が場当たり(値引き常態化・価格崩れ)
- 8.8 変革マネジメントを軽視し、現場が反発
- 8.9 7S(戦略・組織・仕組み・人・価値観・スキル・スタイル)の不整合
- 8.10 DXが“手段の目的化”で迷走
- 8.11 M&A/PMIでシナジー未達
- 8.12 事業ポートフォリオの先送り
- 8.13 リスク管理が形骸化
- 8.14 ドキュメント不備・属人化
- 8.15 モニタリング頻度が低い
- 8.16 そのまま使えるチェックリスト(実務用)
- 9 合同会社えいおうの事業戦略コンサルティングの特徴
- 10 合同会社えいおうが支援できるクライアント像|事業戦略コンサルティングの対象と適合条件
- 10.1 創業初期・アーリー期の企業|PMF達成と成長戦略の骨格づくり
- 10.2 売上停滞・競争激化に直面する中小企業|既存事業の立て直し
- 10.3 新規市場開拓・事業拡大を目指す企業|GTMとスケール設計
- 10.4 オムニチャネル化を進めたい小売・EC|価格・在庫・体験の整合
- 10.5 サービス・サブスク事業|解約率コントロールとLTV最大化
- 10.6 製造業・B2B企業|販路再編と価値販売への移行
- 10.7 M&A/PMI直後の企業|シナジー創出と統合加速
- 10.8 事業再生・ターンアラウンド|キャッシュ創出と再成長軌道
- 10.9 地域密着ビジネス・観光関連|北陸の文脈を活かした戦略
- 10.10 クライアント像別の要点サマリー
- 11 あなたの事業を未来へ導く第一歩|事業戦略コンサルティングを成果に変える始め方
事業戦略コンサルティングとは?

企業が「どこで戦い、どう勝つか」を明確にし、それを実行に移すための専門的支援
――それが事業戦略コンサルティングです。
経営戦略や中期経営計画の策定にとどまらず、市場分析・競合分析・ビジネスモデル設計・KPI(重要業績評価指標)設計・実行計画までを一貫してサポートします。近年では、戦略を立案するだけでなく、実行・運用まで伴走する形態が主流になっています。グローバル大手も「戦略を現実にする」という実践重視の姿勢を打ち出しています。
この記事では、事業戦略コンサルティングの基本的な意味から導入メリット、支援領域、典型的なプロセスまでを体系的に解説し、合同会社えいおうのサービスの位置づけも明確にします。
本セクションの要点をひと目で
|
項目 |
要点 |
|---|---|
|
定義 |
企業の成長・競争優位実現に向け、環境分析〜戦略立案〜実行計画〜伴走支援までを行う専門サービス |
|
主な支援範囲 |
全社戦略、事業ポートフォリオ、マーケティング戦略、新規事業、価格戦略、DX、M&A・アライアンス、事業再生など |
|
成果物 |
戦略ストーリー、収益モデル、KPI設計、実行ロードマップ、組織・人材要件、モニタリング設計 |
|
関連フレームワーク |
3C、SWOT、PEST、7S、バリューチェーン、ペルソナ、カスタマージャーニー |
|
近年の潮流 |
戦略立案に加え、実行支援・運用支援まで伴走し、成果に直結するコンサルティングが主流 |
事業戦略コンサルティングの定義と目的
事業戦略コンサルティングとは、企業の経営層が行う意思決定を支援し、持続的成長を実現するために「構想から実装まで」を扱うコンサルティング領域です。市場機会の特定、競争優位性の明確化、顧客価値の設計、収益構造の最適化、KPI設計と実行計画までを包括的に行います。
目的は以下の3点に集約されます。
-
成長戦略の具体化
-
ヒト・モノ・カネ・時間など経営資源の最適配分
-
実行力の強化
初心者向け用語解説
-
経営戦略/事業戦略:経営戦略は会社全体の方向性、事業戦略は個別事業の勝ち方を示す。
-
KPI(重要業績評価指標):戦略の進捗や成果を定量的に測る指標。
-
実行ロードマップ:戦略を誰が・いつ・どのように実施するかを時系列で示す計画。
なぜ今、企業に事業戦略コンサルティングが必要なのか
市場や技術の変化が早まり、仮説検証を高速に回す「実行力」が競争優位を左右します。人口動態の変化、技術革新、地政学リスク、規制強化など、複雑な外部要因が経営環境を不安定にしています。こうした背景から、戦略構築から実行までを一貫して支援できる外部パートナーの必要性が高まっています。
外部の戦略コンサルティングは、以下の価値を提供します。
-
第三者視点による冷静な機会評価
-
データ分析に基づくリスクとリターンの設計
-
組織を巻き込む現実的な実行計画づくり
事業戦略コンサルティングが扱う主な支援領域
全社戦略と事業ポートフォリオ最適化
複数事業の収益性・成長性・シナジーを分析し、資源配分を最適化します。撤退や集中、提携の判断も含め、資本効率を最大化します。
新規事業開発・マーケティング戦略
顧客インサイトの発見、ペルソナ設定、カスタマージャーニー設計、価格戦略や販路戦略までを連動させます。MVP(Minimum Viable Product)やPoC(概念実証)による検証も行います。
M&A・アライアンス戦略
買収や提携の是非を産業構造や競争環境から評価します。PMI(Post Merger Integration=統合プロセス)やガバナンス設計までサポートします。
DX(デジタル変革)と収益モデル再設計
データ活用や業務刷新によって顧客体験とコスト最適化を両立します。投資優先度と成果指標を明確化します。
事業再生・ターンアラウンド
損益やキャッシュフローを可視化し、コスト構造や販売戦略を短期改善。中期的な再成長の道筋を描きます。
事業戦略コンサルティングの典型プロセス
-
現状・外部環境の可視化:3C、PEST、SWOT、定量分析、顧客・競合ヒアリング
-
戦略仮説の設計:市場選定、価値提案、価格戦略、収益モデル設計
-
実行ロードマップ化:KPI設定、リソース計画、組織・人材要件、リスク管理
-
実行支援:プロジェクト推進、施策実装、営業・マーケティング体制の構築
-
運用・改善:レビューと改善の仕組み化、再投資の判断
戦略コンサルティングを活用するメリットと導入理由

戦略コンサルティングは、事業戦略や中期経営計画を「机上の計画」で終わらせず、実装まで到達させるための外部リソースです。第三者視点での客観分析、KPI(重要業績評価指標)と戦略の整合、PMO(プロジェクトマネジメント機能)による実行支援までを一気通貫で補い、意思決定の質とスピードを底上げします。国内外のトレンドでも“立案だけでなく実行まで伴走する”コンサルティングが主流化しており、成果創出に直結する支援への期待が高まっています。
戦略コンサルティングのメリット
|
メリット項目 |
ビジネス効果 |
関連キーワード |
|---|---|---|
|
客観性と専門知見 |
課題の可視化、思考のバイアス除去、最適解の選定 |
第三者視点、ベストプラクティス |
|
実行支援(PMO) |
進捗管理・標準化・KPI運用が定着、プロジェクト成功率向上 |
PMO、KPI整合、実行伴走 |
|
意思決定の質向上 |
データ分析×仮説検証で投資判断の精度が上がる |
エビデンス、ROI、検証 |
|
スピード向上と内製補完 |
リソース不足を補い、検討〜実装のリードタイム短縮 |
リソース最適化、運用設計 |
|
コスト最適化 |
ベンダー調整や標準テンプレ導入でムダを削減 |
価格戦略、ベンダー交渉 |
|
長期ビジョン策定支援 |
中長期の勝ち筋を明確化、組織のベクトルがそろう |
長期ビジョン、中期経営計画 |
客観性と専門知見がもたらす意思決定の質の向上
社内だけで検討すると、既存前提や部門利害が判断を曇らせる場合があります。戦略コンサルティングは第三者視点で状況を分解し、ベストプラクティスや他社事例を踏まえて意思決定を支援します。結果として、戦略オプションの比較検討が深まり、投資の選択と集中が進みやすくなります。外部活用の主要メリットとして「知見の獲得」「スピードアップ」「客観評価」を挙げる論考も一般的です。
ベストプラクティス:一定の状況で高い成果が再現されている実務知見。単なる流行ではなく、原理原則に根差した手法を指します。
実行支援とPMO機能でプロジェクト成功確率が上がる
戦略は「実装」されて初めて価値になります。PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)や実行伴走の導入により、KPIと戦略目標の整合、可視化、標準化テンプレートの適用が進み、計画倒れを回避しやすくなります。PMI×PwCの国際調査でも、上位組織はKPIを戦略ゴールと一致させ、ガバナンスとデータ活用を強化していることが示されています。PMOの外部活用は短期間でベストプラクティスを導入し、現場定着までを支援できる点が強みです。
PMO:複数プロジェクトを統括し、進捗・品質・リソースを管理する機能。戦略目標とKPIの紐づけ、課題の早期検知、部門横断の調整を担います。
データ分析とKPI整合で投資判断が精緻化
戦略コンサルティングは、データに基づく仮説検証を仕組み化し、KPI設計を通じて「戦略—実行—評価」のループを回し続けます。KPIが戦略ゴールと一致しているほど、意思決定は再現性を持ちます。国際調査でも統合と整合(KPI×戦略目標)が上位組織の特長として強調されます。
スピードとリソース最適化:内製の限界を補完
デジタル変革や新規事業など、スキルの幅と深さが同時に求められる領域では、内製だけでの推進に時間がかかることがあります。外部コンサルティングを併用することで、検討から実装までのリードタイムを縮め、社内人材は中核業務に集中できるようになります。一般に「専門家の活用は業務スピードを高める」効果が指摘されます。
コスト最適化と価格戦略・ベンダー調整の付加価値
導入の現実的な理由として、価格戦略の再設計や調達・ベンダー交渉の最適化があります。発注仕様の整理、相見積もりの設計、要件定義の明確化を第三者が担うことで、齟齬を減らし、総コストを抑えやすくなります。外部が間に入ることで、プロジェクト推進上の摩擦も低減しやすいのが実情です。
長期ビジョン策定と競争優位の強化
昨今の戦略は「3年の中計」だけでは不十分とされ、10年スパンの長期ビジョンを描き、サステナビリティやメガトレンドを織り込む発想が求められています。戦略の難度が上がる中で、構想力と実装力を兼備した外部パートナーの価値はむしろ増しています。
戦略コンサルティング導入が適しているシグナル
-
事業ポートフォリオの再編や撤退・集中の判断を迫られている
-
DXや新規事業で「構想はあるが実装が進まない」
-
KPIが部署ごとにバラバラで、戦略目標とズレている
-
大型プロジェクトのPMO機能が整っておらず、進捗が見えない
-
中期経営計画の見直しが必要だが、客観性に不安がある
これらは、外部パートナーのレバレッジが効きやすい局面です。PMOやKPI整合の観点から、戦略目標→KPI→実行計画の連鎖を再設計することが効果的です。
合同会社えいおうに依頼する導入の流れ(実務イメージ)
えいおうは伴走型の実行支援を前提に、以下の流れで導入を設計します。
-
現状ヒアリングと課題の可視化(KPI棚卸し、意思決定プロセスの診断)
-
戦略仮説の設計と優先順位づけ(市場/顧客/価格/チャネルの観点)
-
実行ロードマップとPMO設計(標準テンプレ、レビュー運用、ボトルネック解消)
-
施策実装の伴走(マーケ/セールス/オペレーションの型化、定例レビュー)
-
効果検証と再投資判断(KPI—戦略目標の整合確認、改善ループの固定化)
よくある懸念と対策
-
費用対効果が見えにくい:KPIとマイルストーンを事前合意し、四半期ごとにレビュー。成果の定量化を徹底します。
-
社内の巻き込みが難しい:意思決定者・実務責任者・現場の3層でR&R(役割と責任)を設計。PMOが合意形成を支援。
-
「外部任せ」になりがち:内製化ロードマップを最初から設計し、ドキュメントと標準手順を移譲します。
実行に強い戦略が企業価値を動かす
戦略コンサルティングの本質は、客観知+実装力で意思決定の質とスピードを高め、戦略目標とKPIを一致させ続ける運用にあります。PMOとベストプラクティスを梃子に、価格戦略・資源配分・実行ロードマップを統合すれば、計画倒れの確率は下がり、投資効率は上がるはずです。
「描くだけでなく、やり切る」
――この姿勢こそが、外部パートナーを導入する最も実務的な理由と言えるでしょう。
戦略コンサルタントに求められるスキルと資質

事業戦略コンサルティングを成功に導くためには、高度な分析力だけでなく、実行段階まで見据えた総合的な能力が必要です。ここでは、戦略コンサルタントに欠かせないスキルと資質を体系的に解説します。初心者の方でも理解できるよう、専門用語には説明を添えながら、実務での活用例も紹介します。
ロジカルシンキングと課題解決力
ロジカルシンキング(論理的思考力)とは、物事を筋道立てて整理し、矛盾のない結論に導く思考方法です。戦略コンサルタントは、限られた情報や時間の中で「課題の本質は何か」を見極め、仮説を立てて検証します。
課題解決力とは、このロジカルシンキングを軸に、現実的で実行可能な解決策を設計する能力です。
実務での活用例
-
売上低迷の原因を、顧客層・販売チャネル・商品力など複数の要素に分解して分析
-
原因ごとの改善施策を立案し、優先順位をつけて実行計画に落とし込む
データ分析力と情報活用力
戦略立案には、感覚ではなくデータに基づいた判断が不可欠です。データ分析力とは、数値データや調査結果から意味のある洞察(インサイト)を導き出す能力を指します。また、情報活用力とは、統計データ・業界レポート・社内資料など多様な情報源を組み合わせて戦略に反映する力です。
ポイント
-
単なる数値整理ではなく、「なぜそうなったか」を説明できるレベルまで掘り下げる
-
定量データ(数字)と定性データ(顧客の声や市場動向)を組み合わせる
コミュニケーション力と合意形成力
戦略は一人では実行できません。経営陣から現場担当者まで、多様な関係者を巻き込み、同じ方向へ進むためには高いコミュニケーション力が必要です。さらに、利害の異なる関係者間で意見を調整し、合意を形成する力も求められます。
実務での活用例
-
経営層への戦略提案時に、数値根拠と市場背景を明確に示す
-
部門間の優先度の違いを整理し、全体最適の視点で合意を得る
実行力とプロジェクトマネジメント力
優れた戦略も、実行されなければ成果は生まれません。実行力とは、計画を現実の行動に移し、結果を出すために必要な推進力のことです。
プロジェクトマネジメント力は、複数のタスクや関係者を管理し、スケジュール通りに成果を出す能力です。戦略コンサルタントは、計画策定後もPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)として進捗管理やリスク対応を行うことがあります。
フレームワーク活用力
フレームワークとは、戦略立案や分析を効率的かつ漏れなく進めるための枠組みのことです。代表的なものに、3C分析、SWOT分析、PEST分析、バリューチェーン分析などがあります。これらを適切に使い分けることで、複雑な情報を整理しやすくなります。
倫理観と信頼性
戦略コンサルティングは企業の機密情報を扱う業務です。そのため、高い倫理観と守秘義務の遵守は欠かせません。また、クライアントとの信頼関係を築くため、約束を守る姿勢や誠実な対応も重要な資質です。
戦略コンサルタントに求められるスキル・資質の整理表
|
スキル・資質 |
説明 |
実務での活用例 |
|---|---|---|
|
ロジカルシンキング |
論理的に物事を整理し、矛盾のない結論を導く |
課題の構造化、仮説立案 |
|
課題解決力 |
実行可能な解決策を設計する力 |
改善施策の立案と優先順位付け |
|
データ分析力 |
数値や調査から有用な知見を得る |
売上分析、顧客動向の把握 |
|
コミュニケーション力 |
関係者を巻き込み、理解を得る |
戦略提案、部門間調整 |
|
合意形成力 |
利害調整を行い全体最適を実現する |
プロジェクトの方向性統一 |
|
実行力 |
計画を行動に移す推進力 |
戦略施策の実行・モニタリング |
|
プロジェクトマネジメント力 |
タスク管理・進捗管理を行う能力 |
PMO業務、進捗報告 |
|
フレームワーク活用力 |
分析・戦略立案の型を使いこなす |
3C分析、SWOT分析の実施 |
|
倫理観・信頼性 |
機密保持と誠実な姿勢 |
情報管理、長期的関係構築 |
戦略コンサルティングが扱う主なテーマ

戦略コンサルティングの領域は「どこで戦い、どう勝つか」を実装まで落とし込むために、全社戦略から新規事業、M&A、DX、価格戦略、サステナビリティ、事業再生まで幅広く展開します。
全社戦略・中期経営計画(成長戦略と資源配分の設計)
企業全体の方向性を定め、3〜5年の中期経営計画に落とし込む領域。収益性・成長性・リスクのバランスを見ながら、ヒト・モノ・カネの資源配分を最適化します。ポイントは、定量目標(売上・営業利益・ROICなど)と実行KPI(リード指標)を結び、レビューの仕組みをPMOで運用すること。
ROICは投下資本利益率。資本効率の高さを示す指標。
事業ポートフォリオ最適化(撤退・集中・育成の意思決定)
複数事業の位置づけを可視化し、集中投資すべき事業・撤退すべき事業・提携で補う事業を整理します。市場規模・成長率・収益性・シナジーを総合評価し、資源配分を刷新。撤退判断の基準やタイムラインまで設計することで、実行段階の迷いを減らします。
新規事業開発(PMF達成までのロードマップ)
新規事業は“構想”と“検証”の往復運動です。
機会探索
市場課題の発見、顧客セグメントの定義、競合のポジショニングを整理。
仮説検証(MVP/PoC)
最小構成の製品・サービス(MVP)や概念実証(PoC)で価値仮説を検証し、KPIの変化を観察。
収益モデル設計
単価・継続率・顧客獲得単価(CAC)・顧客生涯価値(LTV)のバランスを設計。
PMF(Product-Market Fit)は、提供価値が市場に適合した状態。
Go-To-Marketとマーケティング戦略(顧客起点の拡販設計)
セグメンテーション/ターゲティング/ポジショニング
「誰に」「何を」「どう伝えるか」を明確化。
価格戦略・チャネル戦略
バンドル、段階課金、サブスクリプションなどの価格メニューと、直販・代理店・ECなどチャネルの最適組み合わせを決めます。
カスタマージャーニーとKPI
認知→比較→購入→継続の各段階でKPIを設計し、コンテンツや営業プロセスを連動させます。
価格戦略・収益モデル(利益性の最大化と再現性)
価格は利益に直結するレバー。コストベース、競合ベンチマーク、価値ベースの三視点から価格決定を行い、値引きルールや価格階層を整えます。併せて、解約率や継続率を踏まえた収益モデル(LTV/CAC比)の健全化を図ると、資金繰りと成長投資の両立がしやすくなります。
LTV/CAC比は、1顧客から得られる生涯利益を獲得コストで割った指標。
M&A・アライアンス戦略とPMI(統合マネジメント)
戦略適合性の評価
単なる規模拡大ではなく、競争優位が強まるかを評価。
バリュエーションとデューデリジェンス
価値評価とリスク調査を通じ、買収の前提条件を精緻化。
PMI(Post Merger Integration)
組織・システム・プロセスの統合計画を策定。短期のコストシナジーと中期の収益シナジーをKPIで追い、統合の混乱を最小化します。
PMIはM&A後の統合作業全般。
DX(デジタル変革)戦略とデータ活用(オペレーティングモデル刷新)
データ基盤、業務プロセス、顧客体験(CX)をつなぎ、価値創出とコスト最適化を同時に進めます。
顧客体験の再設計
パーソナライズ、オムニチャネル、セルフサービス導線の整備。
データ基盤・ガバナンス
データ品質、権限管理、プライバシー対応をルール化。
業務プロセスの自動化
RPAやワークフローで標準化し、リードタイム短縮と品質安定を実現。
オペレーティングモデルは、戦略を実行する組織・プロセス・システムの設計図。
サプライチェーン戦略とコスト構造改革(バリューチェーン最適化)
需要予測、在庫方針、調達・製造・物流の各工程を連結して最適化。カーボンフットプリントやBCP(事業継続計画)も考慮し、レジリエンスとコストを両立します。
バリューチェーンは価値を生む一連の活動、BCPは非常時に事業を継続させる計画。
海外進出・グローバル戦略(現地適合と本社ガバナンス)
市場選定、参入スキーム(子会社・JV・代理店)、現地法規対応、為替・物流リスク管理を設計。現地最適と本社統制のバランスが鍵。共通KPIとガバナンスを定義し、ローカルの裁量とスピードを担保します。
ESG・サステナビリティ経営(リスクと機会の統合)
気候変動、労働、人権、サプライチェーン管理といったテーマを、リスク回避だけでなく成長機会として戦略に織り込みます。開示(報告)要件と事業ポートフォリオの整合を取り、資金調達やレピュテーション強化にもつなげます。
ESGは環境・社会・ガバナンスの総称。
事業再生・ターンアラウンド(短期改善と中期再成長の両立)
短期ではキャッシュ確保と固定費圧縮、粗利改善に注力。並行して、商品ミックスや価格戦略を見直し、中期的な再成長の“勝ち筋”を描きます。90日プランで可視化し、週次のKPIレビューで実行を支えます。
組織・人材戦略と変革マネジメント(7Sで要素整合)
戦略を支えるのは人と組織。
7Sアラインメント
戦略(Strategy)・組織(Structure)・仕組み(Systems)・価値観(Shared Values)・スキル(Skills)・人材(Staff)・リーダーシップ(Style)の整合を評価。
権限設計とインセンティブ
意思決定の階層や責任範囲を明確化し、報酬・評価を戦略KPIと連動。
変革マネジメント
現場の抵抗を想定し、コミュニケーション計画とトレーニングで定着を促進。
実行支援・PMOとKPIマネジメント(戦略の運用化)
戦略を“運用”に乗せる最後の要。
-
定例運営:月次/四半期でのKPIレビューと意思決定サイクル
-
課題管理:リスク・課題・依存関係を見える化
-
標準化:テンプレート・チェックリスト・ダッシュボード整備
-
移管:内製化ロードマップとナレッジ移転
主なテーマと成果物・指標の対応表(要約)
|
テーマ |
代表的成果物 |
主なKPI/指標 |
|---|---|---|
|
全社戦略/中計 |
成長シナリオ、資源配分方針 |
売上、営業利益、ROIC |
|
ポートフォリオ |
投資/撤退マップ |
投資回収期間、シェア/成長率 |
|
新規事業 |
検証計画、収益モデル |
PMF指標、LTV/CAC、継続率 |
|
GTM/マーケ |
価格・チャネル戦略 |
CVR、CPA、ARPU |
|
M&A/PMI |
統合計画、シナジー計画 |
コスト/売上シナジー達成率 |
|
DX |
データ基盤・自動化設計 |
リードタイム、顧客満足、運用コスト |
|
サプライチェーン |
在庫/需要計画 |
在庫回転、欠品率、原価率 |
|
海外/グローバル |
参入計画、ガバナンス |
現地売上、為替影響、遵法指標 |
|
ESG |
マテリアリティ、開示設計 |
温室効果ガス排出量、サプライヤ監査 |
|
再生/ターンアラウンド |
90日プラン、CF計画 |
営業CF、粗利率、固定費削減率 |
|
組織・人材 |
オペレーティングモデル |
エンゲージメント、離職率 |
|
実行支援/PMO |
ダッシュボード、標準テンプレ |
KPI達成率、課題解決リードタイム |
活用のヒント
合同会社えいおうでは、上記テーマを“単発の助言”ではなく、KPI設計とPMO運用をセットにした伴走型で支援します。戦略—実行—評価のループを現場に定着させることで、計画倒れを避け、投資効率と組織学習の双方を高めることが狙いです。
戦略策定に役立つ定番フレームワーク

事業戦略コンサルティングの現場では、限られた時間で「現状把握→仮説構築→意思決定→実行計画」まで進める必要があります。そこで力を発揮するのが、再現性の高い戦略フレームワーク。3C分析、SWOT分析、PEST分析、7Sフレームワーク、バリューチェーン分析は、上位サイトでも頻出の定番であり、初心者でも扱いやすい道具です。本節では、各フレームの目的、使いどころ、作り方、アウトプット、落とし穴までを実務視点で解説します。
3C分析(市場・顧客・競合を起点にする事業戦略フレームワーク)
3CはCustomer(市場・顧客)/Competitor(競合)/Company(自社)の三視点で外部・内部の状況を整理し、どこで勝つか(ターゲット/ポジショニング)とどう勝つか(差別化/価格戦略/チャネル)を導きます。最初の地図づくりに最適。
3Cの目的と使いどころ
-
市場機会の大きさと構造を把握し、ターゲット顧客像を明確化
-
競合の強み・弱み、勝ち筋のパターンを把握
-
自社の資源・制約・提供価値を照らし合わせ、勝てる土俵を選ぶ
3Cの作り方(ステップ)
-
Customer:市場規模、成長率、顧客セグメント、購買要因(価格・利便性・品質など)
-
Competitor:主要プレーヤー、シェア、価格帯、チャネル、差別化要素、参入障壁
-
Company:自社の資源(人材・技術・ブランド)、コスト構造、収益性、KPIの現況
-
インサイト抽出:未充足ニーズ、空白ポジション、優位を築ける要素
-
仮説化:誰に/何を/いくらで/どのチャネルで/どの体験で提供するかを文章化
3Cの成功のコツと落とし穴
-
コツ:定量(市場データ)と定性(顧客の声)を併用。STP(セグメンテーション/ターゲティング/ポジショニング)へ直結させる。
-
落とし穴:自社視点に偏りCompanyだけが肥大化しがち。必ずCustomer/Competitorから先に整理。
SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威を戦略に結びつける)
SWOT=Strengths/Weaknesses/Opportunities/Threats。内部要因(S/W)と外部要因(O/T)を一枚に一覧化し、戦略方針を合意形成しやすくする道具です。TOWSマトリクスとして戦略案まで落とし込むと有効。
SWOTからTOWSへ:戦略案の導出
|
戦略の型 |
意味 |
例 |
|---|---|---|
|
SO戦略 |
強みで機会をつかむ |
既存技術×拡大市場で高付加価値モデルを展開 |
|
WO戦略 |
弱みを補って機会に乗る |
データ人材採用で分析力を補完し新市場へ |
|
ST戦略 |
強みで脅威を抑える |
ブランド力で価格競争の波を回避 |
|
WT戦略 |
弱みと脅威を回避 |
不採算領域からの撤退、ポートフォリオ再編 |
SWOT作成のポイント
-
内部要因は根拠つきで書く(実績KPI、顧客評価、原価率など)
-
外部要因はPESTや業界構造分析と連動させ、具体的事象で記載
-
4象限を埋めて終わりにせず、3つの戦略案に要約し意思決定へ
PEST分析(外部環境のマクロ要因を読み解く)
PEST=Political/Economic/Social/Technological。中期経営計画や海外戦略、価格戦略の前提条件づくりに役立ちます。法規制や金利、社会価値観、技術トレンドといったコントロール不能だが重要な前提を揃える作業。
PESTの観点チェック
-
Political:規制/補助金/税制/貿易/データ保護/ガバナンス
-
Economic:金利/為替/物価/賃金/景況感/設備投資動向
-
Social:人口構成/ライフスタイル/健康志向/サステナビリティ
-
Technological:AI/IoT/クラウド/自動化/新素材/サイバーセキュリティ
戦略仮説へのつなげ方
PESTで洗い出した事象を「機会/脅威」に分類し、SWOTのO/Tへ転記。影響度×発生確率で優先順位をつけ、対応方針を一文で定義すると意思決定が速くなります。
7Sフレームワーク(戦略と組織の整合:オペレーティングモデル診断)
7SはStrategy/Structure/Systems/Shared Values/Skills/Staff/Styleの整合を診断する枠組み。戦略の実行段階でボトルネックになりやすい組織・人・仕組みを可視化し、PMOによる定着支援に直結します。
7Sの観点と診断の要点
|
要素 |
ねらい |
代表的な診断観点 |
|---|---|---|
|
Strategy |
方向性の妥当性 |
優位性、価格戦略、KPI連動 |
|
Structure |
組織構造 |
権限設計、意思決定の速さ、ガバナンス |
|
Systems |
仕組み・プロセス |
業務標準化、IT/データ基盤、評価制度 |
|
Shared Values |
価値観 |
顧客起点、品質/安全、サステナビリティ |
|
Skills |
スキル |
データ分析、営業力、プロダクト開発力 |
|
Staff |
人材 |
配置最適化、採用/育成、エンゲージメント |
|
Style |
リーダーシップ |
コミュニケーション、変革推進の姿勢 |
使い方
-
期待状態(To‑Be)を明文化
-
現状(As‑Is)とのギャップを定義
-
重要度×実現難易度で優先度を決め、90日アクションへ落とす
バリューチェーン分析(付加価値の源泉とコスト構造を可視化)
バリューチェーンは、主活動(購買→製造→物流→販売→サービス)と支援活動(全社インフラ、人事、技術開発、調達)に分解し、どこでコスト優位・差別化優位が生まれているかを見抜く道具です。価格戦略や原価低減、顧客体験の強化に直結。
進め方とアウトプット
-
活動単位でコスト/工数/リードタイム/品質を計測
-
顧客価値への寄与度を評価し、強化/削減/外部化の方針を決定
-
価格改定やサービス設計(保守、サポートSLA)に反映
ありがちな落とし穴
-
部門ごとの最適化で全体価値が下がること。全体KPI(粗利、在庫回転、NPSなど)を軸に意思決定する。
使い分けガイド(どの課題にどのフレーム?)
|
課題タイプ |
適したフレームワーク |
ねらい/アウトプット例 |
|---|---|---|
|
新市場へ参入 |
3C→PEST→SWOT |
市場規模/競合地図→外部前提→戦略案(SO/WO) |
|
既存事業の立て直し |
バリューチェーン→SWOT |
原価/価値の可視化→改善施策と撤退基準 |
|
実行が進まない |
7S→KPI再設計 |
組織・仕組みの整合診断→PMO運用とレビュー |
|
価格の見直し |
3C→バリューチェーン |
需要価格感応度/競合価格→利益確保の価格帯 |
初心者がハマりやすいポイントと回避策
-
作って満足:図表化して終わらせず、3つの打ち手に要約して意思決定へ
-
定量欠如:感覚に頼らず、最低限の市場規模・成長率・価格帯・KPIを入れる
-
重複と漏れ:3C→PEST→SWOT→7S/バリューチェーンの流れで使うと整理が効く
-
実行への橋渡し不足:各フレームの結論をKPI/担当/期限に変換し、PMOで進捗管理
ダウンロードに適した簡易テンプレ(記入例付き)
3Cメモ
-
Customer:主要セグメント/購買要因/未充足ニーズ
-
Competitor:主要3社の強み/価格/チャネル
-
Company:自社の強み/制約/KPI現況
SWOT→TOWSメモ
-
S:__/W:__/O:__/T:__
-
SO案:__/WO案:__/ST案:__/WT案:__
7Sギャップ表
-
To‑Be:__/As‑Is:__/ギャップ:__/90日アクション:__
成果を高めるための支援プロセスとポイント

戦略コンサルティングは「立案→実行→定着」を一体で設計してこそ成果につながります。本節では、事業戦略の成果を最大化するための支援プロセスを、実務の視点で体系化。
戦略コンサルティングの一般的な進行ステップ
戦略立案だけでなく、実行計画と運用設計まで包含するのが成功の条件。以下のステップを通して、意思決定の質とスピードを両立させます。
ステップ1|課題の可視化(アセスメント)
現状のKPI、収益構造、顧客セグメント、競合ポジションを棚卸し。3CやSWOT、PESTなどのフレームワークで論点を整理し、“本当のボトルネック”を定義します。
KPIは重要業績評価指標。戦略の達成度を測る数値のこと。
ステップ2|情報収集・分析(データドリブン)
定量(売上・粗利・LTV/CAC・チャネル別CVR)と定性(顧客インタビュー、現場観察)を統合。因果仮説を立て、検証可能な論点に絞り込みます。
LTV/CACは顧客生涯価値と獲得コストの比率。
ステップ3|戦略立案(戦略オプション設計)
ターゲット市場、価値提案、価格戦略、優先施策を文書化。OKR(目標と主要な結果)で方向性を揃え、KPIツリーで測定体系を設計します。
OKRは定性的な目標と、達成を示す定量結果のセット。
ステップ4|実行計画作成(ロードマップ化)
四半期ごとのマイルストーン、役割分担(RACI)、リソース計画、予算、リスク対策(RAID:Risk/Assumption/Issue/Dependency)を定義。PMOの設置を明確化します。
RACIは責任分担表。Responsible/Accountable/Consulted/Informedの略。
ステップ5|モニタリング・改善(運用設計)
ダッシュボードでリード/ラグ指標を追跡。月次レビューとQBR(四半期レビュー)で仮説を更新し、バックログを優先順位づけ。A/Bテストで学習速度を上げます。
リード指標は結果に先行する行動指標、ラグ指標は結果そのもの。
ステップ別アウトプット整理(要約)
|
フェーズ |
主要アクティビティ |
成果物(アウトプット) |
オーナー |
代表KPI/チェックポイント |
|---|---|---|---|---|
|
可視化 |
KPI棚卸し/ヒアリング/3C・SWOT |
論点リスト、現状診断レポート |
事業責任者×コンサル |
主要KPIの基準値合意 |
|
分析 |
データ統合/因果仮説構築 |
インサイトメモ、機会領域マップ |
アナリスト×現場 |
仮説の検証計画 |
|
立案 |
価値提案/価格・チャネル設計 |
戦略ドキュメント、OKR、KPIツリー |
経営×コンサル |
戦略承認と優先度決定 |
|
計画 |
RACI/PMO/予算・リソース |
実行ロードマップ、リスク台帳 |
PMO×各部門 |
マイルストーン合意 |
|
運用 |
レビュー/改善/ABテスト |
ダッシュボード、改善バックログ |
PMO×現場 |
KPI達成率、学習サイクル速度 |
プロジェクト成功のための社内巻き込み方法
実行段階で失速する要因の多くは「合意不足」と「役割不明確」。巻き込みは設計です。
経営アラインメント(トップの意思決定を可視化)
経営会議で戦略意図、非採用案、資源配分方針を明文化。意思決定の“裏取り”が現場の納得感を作ります。KPI変更の基準も事前合意。
ステークホルダーマップとRACIの明確化
関与者(経営陣、事業、営業、マーケ、開発、CS、財務)を棚卸し、RACIで責任と連絡経路を定義。承認フローを短く保つのがコツ。
変革マネジメント(チェンジマネジメント)の設計
現場は“何が、いつ、どう変わるか”がわかれば動けます。コミュニケーション計画、教育(Playbook/ガイドライン)、現場の声を吸い上げるフィードバックループを準備。
Playbookは手順書やベストプラクティス集。
クイックウィン(早期成果)の組み込み
90日で実現可能な打ち手をロードマップの序盤に配置。成功事例を社内に流し、モメンタムを生む。学習サイクルの速度が変わります。
実行支援まで伴走する重要性(PMO・ガバナンス・内製化)
伴走型の実行支援は、計画倒れを防ぐ保険ではなく、成果創出の仕掛けです。
PMOの役割(統合と可視化)
横断プロジェクトの進捗・品質・リソースを統括。依存関係の解消、ボトルネックの早期発見、意思決定のエスカレーションを標準化します。
PMOはプロジェクトマネジメントオフィス。複数案件を束ねる運営機能。
ガバナンス設計(意思決定とリスク管理のルール)
KPIの閾値、資源再配分の基準、例外承認の条件を明確化。RAIDログ(リスク/前提/課題/依存関係)を運用し、会議体(週次/月次/QBR)で透明性を担保。
スプリント運用とバックログ管理(アジャイル的推進)
2〜4週間のスプリントで小さく実装し、検証→改善を高速化。バックログは“効果×実現容易性”で優先順位を更新。リードタイム短縮が実感値を生みます。
ナレッジトランスファーと内製化ロードマップ
ドキュメント、チェックリスト、ダッシュボードを整備し、運用を現場へ移管。スキルトランスファー計画を立て、依存度を段階的に下げます。長期の運用で効くのは、自走できる体制。
成果を最大化する実務ポイント(落とし穴と対策)
-
KPIと戦略目標の不整合:KPIツリーで因果を可視化し、OKRとひも付ける。
-
会議体の機能不全:アジェンダ固定、意思決定ルール明文化、宿題のRACI化。
-
データの信頼性不足:定義書(データディクショナリ)と単一の信頼できる数(SSOT)を設置。
-
リソース過少:優先度を減らし、集中投下。同時進行の“やりすぎ”を避ける。
-
施策の属人化:Playbook化と標準手順。退職・異動リスクへの備え。
チェックリスト(導入前に確認しておく項目)
|
項目 |
確認ポイント |
状態 |
|---|---|---|
|
目的・範囲 |
何を達成するプロジェクトか、何をやらないか |
□OK/□要修正 |
|
KPI/OKR |
成果指標と計測方法、閾値の合意 |
□OK/□要修正 |
|
RACI |
役割・責任・承認者の明確化 |
□OK/□要修正 |
|
PMO/会議体 |
週次・月次・QBR、議事録と決定事項の管理 |
□OK/□要修正 |
|
リスク管理 |
RAIDログ、代替案(Plan B)の準備 |
□OK/□要修正 |
|
内製化 |
ドキュメント整備、教育、移管計画 |
□OK/□要修正 |
価格戦略・利益性視点を含めた戦略設計

価格は利益を直接左右する最重要レバーです。単なる「いくらで売るか」の決め打ちではなく、価値提案・チャネル設計・コスト構造・需要の価格弾力性をまとめて設計し、利益性(マージン)と成長性(LTV)を同時に最大化する視点が要になります。本節では、事業戦略コンサルティングにおける価格戦略の定番手法と、実務で成果につなげる運用の要点を体系化します。
価格戦略の基本設計:利益方程式とユニットエコノミクス
価格決定は「利益方程式」を軸に考えます。
利益=(価格−変動費)×販売数量−固定費。
この単純式を“1顧客あたり”に落としたのがユニットエコノミクスで、ARPU(顧客あたり平均売上)、粗利率、獲得コスト(CAC)、解約率(チャーン)、LTV(顧客生涯価値)が主要指標になります。価格を1%動かしたときの粗利インパクト、数量変化、LTV/CACの改善幅を同時に評価する設計が基本。感覚での値引きや一律の値上げではなく、数式で確かめる姿勢が要です。
価値ベース×競合ベース×コストベースのハイブリッド
価格の決め方は大きく三類型。単独ではなくハイブリッドに設計します。
価値ベース価格(Value-based Pricing)
顧客のWTP(支払意思額)に基づく決め方。差別化価値が強いほど高い価格が許容されます。機能価値だけでなく、ブランド・時間短縮・安心など無形価値も定量化。
競合ベンチマーク(Competition-based)
代替製品の価格や提供条件を踏まえて、レンジを設定。過度な価格追随は消耗戦のリスクあり。差別化要素を併記して価格正当性を訴求。
コストベース(Cost-plus)
原価に一定マークアップをのせる方法。最低限の“価格下限”を定める際に有効。ただし、顧客価値や競合状況を無視しないこと。
価格弾力性とWTPの把握:調査と実運用テスト
価格の最適化には「需要がどれだけ価格に反応するか」を把握する必要があります。代表的な手法を押さえておきましょう。
調査ベース
-
Gabor–Granger法:複数の価格を提示し、購入意向から需要曲線を推定。
-
Van Westendorp法:高すぎる/安すぎる/高いが許容/安いが許容をたずね、受容帯を推定。
-
コンジョイント分析:価格を含む属性組み合わせの選好から効用を推定。差別化要素の金額換算が可能。
実運用テスト
-
A/Bテスト:小規模に価格やプランを出し分け、CVR・粗利・LTVへの効果を実測。
-
因果推定(差の差法など):季節性・チャネル差の影響を分離し、価格効果をより厳密に評価。
価格アーキテクチャ(プラン構成と価格帯の設計)
“いくら”だけでなく“どう見せるか、どう選ばせるか”が成否を左右します。
段階課金(ティア設計)
Good/Better/Bestの三階層で価格アンカーを作り、中央プランに需要を集める設計が定番。機能・サポート・SLAを段階化。
バンドル/アンバンドル
セット販売でWTPを引き上げるバンドル、選択自由度を高めるアンバンドル。商材特性と在庫/提供コストで使い分け。
フリーミアム/サブスクリプション
無料枠で導入障壁を下げ、有料転換率とARPUで採算を管理。価格フェンス(学割、ロケーション、使用量など)で公正かつ戦略的な差別化を行う。
アドオン/オプション課金
コアは競争的に、アドオンで高粗利を確保。保守、延長保証、優先サポートなど、価値が明確な項目に限定。
収益モデルとLTV/CAC:利益性を“時間軸”で設計
LTVを構成するのはARPU×継続月数×粗利率。価格はARPUだけでなく、解約率やアップセル率にも効きます。
-
コホート分析で価格変更前後の継続性を比較。
-
アップセル/クロスセルの導線をプラン表や購入フローに織り込み、価格ウォーターフォール(カタログ価格→割引→値引き→実効価格)を可視化して漏れを塞ぐ。
-
LTV/CAC比の目標(例:3.0以上)を置き、投資判断のガードレールに。
チャネル別価格戦略:直販・EC・卸/小売での最適化
チャネルが変わればコストと価値も変わります。
-
直販/EC:値引きよりも会員特典・同梱・定期便で価値訴求。
-
卸/小売:マージンを前提に上代(小売価格)/下代(卸価格)を設計。
-
MAP(最低広告価格)の設定で価格崩れを抑制。販促費の配分ルールも明文化。
-
オムニチャネルでは、体験価値(即時受取/試用/設置)で価格差の正当性を説明する。
値引き・プロモーション・値上げのルール設計
短期の販売増は魅力ですが、長期の利益性を損ねない運用が肝要です。
値引きの原則
-
目的を在庫圧縮/新規獲得/離反防止などに限定し、恒常化を避ける。
-
割引の上限、期間、対象SKU、在庫数を事前にルール化。
-
値引き後の実効粗利をダッシュボードで可視化。
値上げの進め方
-
コスト要因の透明化、機能追加・品質改善の価値コミュニケーションを同時に実施。
-
代替案(容量・サービスレベル違い)を用意し、価格フェンスで離脱を抑える。
-
重要顧客には個別説明と移行期間を設定。
動的価格・収益マネジメント(在庫制約型の最適化)
宿泊・交通・イベントのように在庫が消滅する業態では、需要予測と残在庫に応じたダイナミックプライシングが有効。小売でも在庫回転や賞味期限で価格を変える手法が普及。
-
価格変動の頻度と幅に上限を設け、顧客の不信感を抑える。
-
法規・プラットフォーム規約への適合も確認。
価格ガバナンスとPMO:承認フローと可視化の仕組み
価格は現場裁量に任せすぎると崩れやすい領域。PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)がガードレールを定義します。
-
承認フロー:定価改定、キャンペーン、例外割引の承認者を明確化。
-
RAIDログでリスク・前提・課題・依存関係を管理。
-
ダッシュボードに価格ウォーターフォール、割引率分布、粗利/在庫/チャーンを統合表示。単一の信頼できる数(SSOT)を運用。
KPIと価格施策の対応表(実務で使える早見表)
|
価格施策 |
主要KPI |
補助KPI |
成功のサイン |
|---|---|---|---|
|
ティア再設計 |
ARPU、粗利率 |
中央プラン選択比率 |
アップセル率上昇、解約横ばい |
|
価格改定(値上げ) |
粗利額 |
解約率、NPS |
粗利増加>解約増加の損益分岐超え |
|
バンドル導入 |
取引単価 |
在庫回転、返品率 |
単価上昇と在庫健全化の両立 |
|
割引最適化 |
実効粗利 |
割引率分布 |
割引の“尾っぽ”が縮小 |
|
MAP運用 |
チャネル粗利 |
価格乖離の件数 |
価格崩れ件数の減少 |
|
サブスク化 |
LTV/CAC |
継続率、初回解約 |
6ヶ月LTVの改善、CAC据え置き |
ありがちな失敗と回避策
-
値引きの常態化:短期目標に引っ張られやすい。目的別KPIと期間を明記し、終了後の回復策をセットで計画。
-
“コストだけ”の値上げ:価値訴求が伴わないと解約リスクが跳ね上がる。機能/品質/体験の改善とセットで。
-
チャネル間の価格不一致:MAPと販促費ルールを明文化し、監視を自動化。
-
検証不足:ABテストの設計が甘いと誤推論に陥る。対象外期間・対照群の確保を徹底。
えいおうの実務スタンス
合同会社えいおうでは、価格設計を価値提案・チャネル・オペレーションと一体で最適化します。調査(WTP推定)と実運用テスト(AB/コホート)を両輪に、ウォーターフォールの可視化とガバナンス運用まで伴走。LTV/CAC、粗利、在庫、NPSをひとつのダッシュボードで管理し、価格決定を“勘と根性”から“再現可能な仕組み”へアップグレードします。
陥りがちな失敗事例とその防止策|事業戦略コンサルティングの実務

戦略は「描く」より「やり切る」段階で崩れます。よくある失敗は、目標とKPIの不整合、データの信頼性不足、合意形成の欠落、PMO不在、価格戦略の場当たり運用など。ここでは、事業戦略コンサルティングの現場で頻発する失敗パターンを体系化し、効果的な防止策を実務レベルで提示します。
失敗パターンの全体像(要約表)
|
失敗パターン |
よくある症状 |
主要指標への影響 |
防止策の要点 |
|---|---|---|---|
|
目標・KPIの不整合 |
部門ごとに指標がバラバラ |
投資のムダ・重複 |
OKR×KPIツリーで因果連鎖を可視化 |
|
データ信頼性の欠如 |
ダッシュボード乱立・数字が合わない |
意思決定の遅延 |
SSOTと定義書で“唯一の数”を運用 |
|
分析過多で実行が遅い |
レポートは厚いが着手が遅延 |
機会損失 |
仮説駆動・クイックウィン・スプリント |
|
巻き込み不足 |
部門対立・現場が動かない |
実行停滞 |
ステークホルダーマップとRACI |
|
PMO不在 |
誰も横串で管理しない |
進捗不透明 |
PMO設置・RAIDログ・会議体設計 |
|
価格運用の場当たり |
割引常態化・値崩れ |
粗利悪化 |
価格ガバナンスとMAP、ウォーターフォール |
|
変革マネジメント軽視 |
抵抗・逆戻り |
定着せず成果縮小 |
目的の翻訳・教育・Playbook |
|
7Sの不整合 |
戦略と組織が噛み合わない |
実行力低下 |
7Sアセスメントとオペレーティングモデル |
|
DXの目的不明 |
技術先行・PoC止まり |
ROI不明確 |
ビジネスKPI連動とスケール設計 |
|
M&A/PMIで未達 |
シナジー出ない・離職 |
統合長期化 |
PMI計画とシナジーKPI、文化統合 |
|
ポートフォリオ先送り |
撤退判断できない |
資源分散 |
評価基準と退出ルールの先出し |
|
リスク管理形骸化 |
事故後対応のみ |
損失拡大 |
リスクヒートマップと事前トリガー |
|
属人化・記録不足 |
人に依存して再現不能 |
継続性低下 |
標準化・ドキュメント・ナレッジ移管 |
|
モニタリング不足 |
レビューが年数回 |
学習停滞 |
月次/QBR、リード/ラグ指標の運用 |
目標・KPIの不整合で走り出す
戦略目標と各部門KPIがつながらず、努力が拡散する状態。目先の数字は動くが全社成果に寄与しない、という典型です。
防止策:OKR×KPIツリーで“因果”を固定
-
会社のOKR(方向性)に対して、KPIツリーでリード指標→ラグ指標の連鎖を明文化。
-
KPIは「誰が・いつ・どのソースで計測するか」まで定義。ダッシュボードに統合。
-
用語補足:OKRは定性的目標と主要な定量結果のセット。
データの信頼性が低い・ダッシュボードが乱立
同じ数値でも部署で値が違う。統計定義が統一されていないのが原因。
防止策:SSOTとデータディクショナリ
-
SSOT(Single Source of Truth)を規約化し、数字はそこからのみ引用。
-
指標定義・算式・集計粒度をまとめたデータディクショナリを維持。
-
ダッシュボードは1枚の経営ビューと、部門の実務ビューに集約。
分析過多で実行が遅れる(Analysis Paralysis)
資料は整うが、施策は動かない。実行前提の仮説設計が欠如しています。
防止策:仮説駆動×クイックウィン×スプリント
-
仮説→検証→学習の2〜4週スプリントで進める。
-
90日内に達成できるクイックウィンをロードマップ冒頭に配置。
-
可視化:スプリントレビューで“やった/学んだ/次にやる”を固定。
ステークホルダーの巻き込み不足・合意形成の欠落
経営と現場、営業と開発で優先度が衝突。
防止策:ステークホルダーマップとRACI
-
影響度×関心で関係者を整理し、RACI(Responsible/Accountable/Consulted/Informed)を合意。
-
意思決定フローを短縮。承認の所要日数もKPI化。
-
定例のコミュニケーション計画(誰に、何を、どの頻度で)を文書化。
PMO不在で横串管理ができない
部門最適の寄せ集めで全体が進まない。
防止策:PMO設置・RAIDログ・会議体
-
PMOが進捗・品質・リソースを統合管理。依存関係の解消を主務とする。
-
リスク/前提/課題/依存関係をRAIDログで運用。
-
週次(実行)・月次(戦術)・QBR(戦略)の三層会議体を固定。
価格戦略が場当たり(値引き常態化・価格崩れ)
短期売上を追い値引きが日常化。粗利率が劣化し、価格の説得力も下がります。
防止策:価格ガバナンスとMAP、ウォーターフォール
-
例外割引の承認フローと上限を明記。
-
チャネル間の価格崩れを防ぐMAP(最低広告価格)を設定。
-
価格ウォーターフォール(定価→割引→実効価格)で漏れを可視化。
-
用語補足:MAPは小売が広告で掲示できる最低価格。
変革マネジメントを軽視し、現場が反発
“正しいが動かない”状態。導入目的が現場に伝わっていません。
防止策:目的の翻訳・教育・Playbook
-
組織別に“自分ごと化”したメッセージを用意。
-
ロール別トレーニング、Playbook(手順書)整備、問い合わせ窓口の設置。
-
早期の成功事例を社内で共有し、モメンタムを強化。
7S(戦略・組織・仕組み・人・価値観・スキル・スタイル)の不整合
戦略は良いが、組織が支えない。
防止策:7Sアセスメントとオペレーティングモデル再設計
-
To‑Be(あるべき姿)とAs‑Is(現状)のギャップを7要素で診断。
-
権限設計、評価制度、データ基盤など、オペレーティングモデルを更新。
-
用語補足:オペレーティングモデルは戦略実行の設計図(組織・プロセス・IT)。
DXが“手段の目的化”で迷走
最新技術の導入自体がゴール化。成果が曖昧になります。
防止策:ビジネスKPI連動とPoC→スケール
-
導入目的を売上・粗利・リードタイムなどのKPIに直結。
-
PoCで効果検証→スケール計画(運用費・人材・SLA)まで準備。
M&A/PMIでシナジー未達
統合計画が甘く、人や文化の統合が進まない。
防止策:PMI計画とシナジーKPI、文化統合
-
統合ロードマップ、組織/システムのマイルストーン、シナジーKPIを事前合意。
-
文化差のリスクを明示し、コミュニケーション計画を運用。
-
用語補足:PMIは買収後の統合プロセス。
事業ポートフォリオの先送り
不採算事業を抱え続け、資源が希薄化。
防止策:評価基準と退出ルール
-
成長率・ROIC・戦略適合性の評価スコアで継続/撤退を判断。
-
退出時のタイムラインと影響緩和策を事前設計。
リスク管理が形骸化
“起きてから会議”。被害が拡大します。
防止策:リスクヒートマップと事前トリガー
-
発生確率×影響度でヒートマップ化し、対応レベルを定義。
-
トリガー(閾値)に達したら自動でエスカレーション。
ドキュメント不備・属人化
人に依存し、再現不能。
防止策:標準化とナレッジ移管
-
手順・テンプレ・チェックリストを標準化。
-
新任者オンボーディングの仕組みを作る。成果は資産化。
モニタリング頻度が低い
レビューが四半期に一度。学習が遅れる典型。
防止策:月次/QBR、リード/ラグ指標の運用
-
月次レビューとQBRを固定し、リード/ラグをセットで確認。
-
ダッシュボードでKPIの“見える化”。意思決定を高速化。
そのまま使えるチェックリスト(実務用)
-
目的と範囲は一文で言えるか。外したことも明記しているか。
-
OKRとKPIツリーは合意済みか。誰がどのデータで計測するか定義済みか。
-
SSOT、データ定義書、経営ビューのダッシュボードは運用中か。
-
RACI、会議体(週次・月次・QBR)、RAIDログは機能しているか。
-
価格の承認フロー、MAP、価格ウォーターフォールは更新されているか。
-
7Sギャップから90日アクションが設定されているか。
-
PoCの成功基準とスケール条件はKPIで定義済みか。
-
PMIのシナジーKPIと文化統合の計画は稼働しているか。
-
退出ルールを含むポートフォリオ基準は定期見直しか。
-
リスクヒートマップのトリガー運用とエスカレーションは機能しているか。
合同会社えいおうの事業戦略コンサルティングの特徴

「戦略を描いて終わり」にしない、実装までやり切る設計が強みです。合同会社えいおうは、事業戦略コンサルティングに“現場で動く仕組み”を組み込み、KPI(重要業績評価指標)管理、PMO(プロジェクトマネジメント)、価格戦略、マーケティング運用までを一気通貫で伴走します。北陸を拠点とした地域密着の知見を活かしつつ、中小企業・個人事業主でも導入しやすいスモールスタートを前提に、成果に直結する支援を提供。机上の理論ではなく、売上・粗利・LTV/CACといった“数字”で成果を可視化することにこだわります。
机上の理論ではなく現場重視の伴走型支援
戦略は現場で実装されて初めて価値になります。えいおうの伴走型支援は、企画書の納品では終わりません。週次の進捗レビュー、月次のKPI確認、四半期(QBR)の戦略見直しまでを標準化し、「意思決定→実行→検証」のループを高速で回します。施策の実装・検証・改善が一体化した運用こそ、成果を押し上げる本丸。
伴走の具体:PMO×90日アクション×ダッシュボード
-
PMO運用:部門横断の依存関係を整理し、リードタイム短縮を主務に設定。
-
90日アクション:最重要KPIに効くクイックウィンを先頭に配置し、勢いをつくる。
-
ダッシュボード:リード指標(例:商談数、CVR)とラグ指標(売上、粗利)を同一画面で可視化。SSOT(唯一の信頼できる数)運用で“数字の食い違い”を排除。
成果測定の考え方
売上や粗利だけでなく、在庫回転、CPA、定期率、解約率などの因果に踏み込みます。戦略目標と指標を一本のKPIツリーで連結し、各施策の寄与を定量で確認。計画倒れを防ぐ設計思想です。
マーケティング思考を軸にした戦略設計
事業戦略は顧客から逆算する。えいおうは、STP(セグメンテーション/ターゲティング/ポジショニング)と価値提案を起点に、Go-To-Market(GTM)、価格戦略、コンテンツ、営業プロセス、アフターサービスまでを連動させます。経営戦略とマーケティング戦略を分断しない設計が特徴。
上流から下流までの“一貫性”
-
上流:市場/顧客のインサイト整理、競合地図、ポジショニングの明確化。
-
中流:価格アーキテクチャ(ティア設計、バンドル、サブスク)、チャネル戦略(直販/EC/卸)を設計。
-
下流:CRM、広告運用、販促、CS(カスタマーサクセス)をKPIで接続。意思決定の根拠が全行程で一貫。
価格戦略・LTV設計の内製化
A/Bテストとコホート分析を仕組み化し、LTV/CACをガードレールに運用。価格フェンス、MAP(最低広告価格)、価格ウォーターフォールの整備まで伴走し、現場が自走できる状態へ移行させます。
北陸を拠点とした地域密着型コンサルティング
地域の産業構造や商習慣を踏まえた設計は、実行確度を高めます。えいおうは北陸エリアの製造業、小売・EC、観光・サービスなどの文脈を理解し、オムニチャネル化、観光・地場資源の活用、BCP/物流リスク配慮といったローカル要件を戦略に織り込みます。全国展開を見据える場合でも、まずは地域で検証→勝ち筋をパッケージ化→横展開という順序で無理なくスケール。
地域×デジタルの掛け合わせ
-
実店舗×EC:在庫・価格・販促の整合をダッシュボードで一元化。来店/通販を往来させる導線を構築。
-
観光・インバウンド:季節性や人流をPESTの“社会・経済”要因として織り込み、需要変動に耐える価格・商品ミックスを設計。
公的支援の活用設計
補助金・助成金の要件を“戦略の副作用”としてではなく、投資計画の一部として整理。要件適合とKPI管理の両立を図り、短期の資金繰りと中期の成長投資を両立します。
中小企業・個人事業主に特化した柔軟な対応
大掛かりな体制を前提にしないのがえいおう流。限られたリソースでも“最小の仕組み”で回るよう、スコープと優先度を設計します。成果が見えた領域から順次拡張する形で、リスクを抑えたスモールスタートを支援。
スコープ設計の例
-
戦略合宿(1〜2日):事業ドメイン、KPIツリー、90日アクションを合意形成。
-
価格改定パッケージ:WTP仮説→A/Bテスト→価格ガバナンス構築までを短期実装。
-
EC/チャネル立ち上げ:商品設計、在庫方針、広告/CRMの最小構成でローンチ。
-
営業プロセス再設計:SFA/CRMの項目設計とダッシュボード整備で“見える営業”へ。
料金・契約の考え方
月次の伴走フィーを基本に、明確なマイルストーンと成果指標を事前合意。必要に応じて成功指標の一部連動、あるいはパッケージ型の固定費でリスクを抑える運用も相談可能。内製化ロードマップを起点に、依存度を段階的に下げていく設計です。
支援範囲と成果物の対応表
|
支援領域 |
主要アクティビティ |
代表成果物 |
関連KPI |
|---|---|---|---|
|
事業戦略設計 |
市場/競合分析、KPIツリー、資源配分 |
戦略ドキュメント、KPIマップ |
売上、粗利、ROIC |
|
価格戦略 |
WTP仮説、A/Bテスト、ガバナンス設計 |
価格アーキテクチャ、MAP、価格WF |
粗利率、ARPU、解約率 |
|
GTM/マーケ |
STP、チャネル/広告、CRM |
施策ロードマップ、運用Playbook |
CVR、CPA、LTV |
|
PMO/運用 |
週次/月次/QBR、RAID管理 |
進捗レポート、ダッシュボード |
期限遵守率、課題解決LT |
|
内製化 |
標準化・教育・移管 |
手順書、KPI定義書、研修資料 |
自走率、属人化解消度 |
※ WF=ウォーターフォール、LT=リードタイム
合同会社えいおうが選ばれる理由
-
一貫性:戦略—価格—チャネル—オペレーションが一本の物語でつながる。
-
可視化:KPI、データ定義、意思決定ルールを明文化し、再現可能にする。
-
実装力:PMOとクイックウィンで、90日以内に“動く成果”を作る。
-
柔軟性:中小企業の現実に合わせ、スコープと優先度をチューニング。
-
地域性:北陸の文脈を理解し、スケールの順序を誤らない。
お問い合わせの前に
課題が漠然としていても構いません。まずは現状KPIの棚卸しと、90日で狙うクイックウィンの仮説づくりから。「どこで勝ち、どう勝つか」を、現場と一緒に具体化していきます。
合同会社えいおうが支援できるクライアント像|事業戦略コンサルティングの対象と適合条件

事業戦略コンサルティングは、業種や会社規模にかかわらず「どこで勝ち、どう勝つか」を実行まで落とす営み。合同会社えいおうは、スモールスタートからでも回る伴走型の設計を強みとし、KPI管理やPMO運用、価格戦略、GTM(Go-To-Market)まで一貫して支援します。ここでは、支援対象となる代表的なクライアント像を具体的に示し、課題と解決アプローチ、成果指標を整理します。
創業初期・アーリー期の企業|PMF達成と成長戦略の骨格づくり
プロダクトの価値仮説が固まり切らず、営業・マーケの再現性が弱い段階。資金繰りと成長投資のバランス設計が難題になりがち。
典型課題
-
ターゲット顧客と提供価値の定義が曖昧
-
単価と獲得コスト(CAC)の釣り合いが崩れやすい
-
価格アーキテクチャ(プラン/オプション)が未整備でアップセル導線が弱い
えいおうの支援
-
顧客インサイトの深掘り、ポジショニング明確化、GTMの最小構成設計
-
価値ベース価格の検討、A/Bテスト設計、フリーミアムやバンドルの是非判断
-
90日アクションとPMO運用で、学習サイクルを高速化
成果指標(例)
-
LTV/CAC改善、初回解約率低下、中央プランへの集約率上昇
売上停滞・競争激化に直面する中小企業|既存事業の立て直し
既存顧客の離反、粗利率の劣化、チャネル依存の偏りが目立つ局面。現場オペレーションと価格の歪みが同時に存在しやすい。
典型課題
-
値引き常態化による実効粗利の低下
-
在庫回転の悪化、SKU過多、販促の重複
-
部門別KPIと全社目標の不整合
えいおうの支援
-
3C/SWOT×バリューチェーンで利益の漏れ箇所を可視化
-
価格フェンスやMAP運用、価格ウォーターフォールの整備
-
ダッシュボードのSSOT化とKPIツリー再設計、クイックウィンの実装
成果指標(例)
-
粗利率改善、在庫回転向上、割引“尾っぽ”の縮小、CVRの再上昇
新規市場開拓・事業拡大を目指す企業|GTMとスケール設計
新市場や新セグメントへの展開を志向。再現性のある拡大型オペレーティングモデルが鍵。
典型課題
-
参入順序、チャネル構成、営業モデルの最適解が不明
-
代理店/パートナー活用時のガバナンス設計不足
-
価格・販促ルールの未整備でブランド毀損リスク
えいおうの支援
-
参入市場の優先度付け、チャネルミックスの試験設計
-
パートナープログラムのルール(コミッション、価格/販促の整合)
-
KPI×レビュー体制(週次/月次/QBR)でスケールの律速点を除去
成果指標(例)
-
新規売上比率、チャネル別粗利、パートナー稼働率、地域展開スピード
オムニチャネル化を進めたい小売・EC|価格・在庫・体験の整合
店舗とECの価格・在庫・販促がバラバラになりがちな領域。顧客体験の分断は離脱要因に直結。
典型課題
-
店舗とECで価格不一致、在庫の見える化不足
-
返品・配送の負荷が粗利を圧迫
-
会員基盤やCRM活用が未成熟
えいおうの支援
-
上代/下代の整理、MAP設定、販促カレンダー統合
-
在庫/需要予測の基本設計とSKU整理、返品ポリシーの見直し
-
CRMとロイヤルティ施策のKPI連動(会員LTVの最大化)
成果指標(例)
-
価格乖離件数の減少、在庫回転/欠品率の改善、会員ARPU上昇
サービス・サブスク事業|解約率コントロールとLTV最大化
継続率とARPUの設計が収益性を左右。価格より“体験”が効くことも多い領域。
典型課題
-
オンボーディング不全による初回解約
-
プラン間の差別化不足でアップセルが弱い
-
サポートSLAやヘルススコア未整備
えいおうの支援
-
オンボーディング設計、ヘルススコア定義、CSのPlaybook化
-
ティア設計と価値差の明確化、アドオン/オプションの利益設計
-
コホート分析で改善点を特定、解約原因の定量化
成果指標(例)
-
初回解約率、継続月数、アップセル率、NPS/LTVの改善
製造業・B2B企業|販路再編と価値販売への移行
見積積み上げの慣行が根強く、価値訴求より価格競争に陥りがちな領域。
典型課題
-
値決めがコストプラス一辺倒、差別化価値の言語化が不足
-
代理店依存度が高く、最終顧客のインサイトが希薄
-
カタログやSLAが価値伝達の阻害要因
えいおうの支援
-
価値ベースの提案書テンプレ、価格フェンス(納期/品質/保証)の設計
-
直販/代理の役割再定義、チャネル別KPIの設定
-
アフターサービスや保守の収益化モデル化
成果指標(例)
-
実効単価上昇、見積リードタイム短縮、直販比率・付帯収益の拡大
M&A/PMI直後の企業|シナジー創出と統合加速
統合後の混乱を抑え、短期のコストシナジーと中期の成長シナジーを確実に刈り取る局面。
典型課題
-
組織/システム/価格の統合ルール未整備
-
重複業務・在庫・商品ラインの冗長化
-
文化摩擦による離職と生産性低下
えいおうの支援
-
PMIロードマップと会議体設計、RAIDログ運用
-
商品・価格・販促の統合方針、SKU最適化
-
コミュニケーション計画とオンボーディング支援
成果指標(例)
-
シナジーKPI達成率、統合マイルストーン遵守、離職率の抑制
事業再生・ターンアラウンド|キャッシュ創出と再成長軌道
短期でキャッシュを確保しつつ、中期の勝ち筋を再設計するフェーズ。意思決定と実行のスピードが生命線。
典型課題
-
粗利と固定費のバランスが崩壊、資金繰り逼迫
-
不採算SKUや取引の温存、撤退判断の先送り
-
現場の疲弊とモチベーション低下
えいおうの支援
-
90日プランの策定、価格/原価/販路のテコ入れ
-
撤退・集中の指標化、在庫圧縮とキャッシュ回収のブースト
-
中期の価値提案再定義とロードマップ再構築
成果指標(例)
-
営業CFの黒字化、粗利率改善、固定費削減率、在庫圧縮額
地域密着ビジネス・観光関連|北陸の文脈を活かした戦略
季節性や人流の波、地場資源の活用がカギ。地域の産業構造・商習慣を踏まえた現実的な設計が実行力を左右。
典型課題
-
オフピークの稼働低下、価格訴求のみの集客
-
仕入・人員の変動対応が難しく、損益が不安定
-
デジタル集客や口コミ運用の仕組み不足
えいおうの支援
-
需要カレンダーとダイナミックプライシングの基本設計
-
地域資源を活かした商品パッケージ、EC連動、在庫/人員計画
-
レビュー・UGC活用の運用整備とリピート導線の構築
成果指標(例)
-
稼働率・ADR(平均単価)改善、再訪率向上、販促ROI改善
クライアント像別の要点サマリー
|
クライアント像 |
主要課題 |
コア支援 |
代表KPI |
|---|---|---|---|
|
創業初期 |
PMF前後の不確実性、価格・GTM未整備 |
価値検証、価格テスト、90日アクション |
LTV/CAC、初回解約、中央プラン比率 |
|
売上停滞 |
値引き常態化、在庫・販促の歪み |
価格ガバナンス、在庫/販促統合、KPI再設計 |
粗利率、在庫回転、CVR |
|
新市場開拓 |
参入順序・チャネル設計、統制不足 |
GTM設計、パートナー制度、会議体運用 |
新規売上比率、チャネル粗利 |
|
小売・EC |
価格不一致、在庫・CRM未整備 |
MAP/カレンダー整備、在庫計画、CRM連動 |
価格乖離件数、欠品率、会員ARPU |
|
サブスク |
解約・アップセル不全 |
オンボーディング、ティア設計、CS強化 |
継続率、アップセル率、NPS/LTV |
|
製造/B2B |
コストプラス依存、代理店偏重 |
価値販売化、チャネル再定義、付帯収益設計 |
実効単価、直販比率、付帯収益 |
|
M&A/PMI |
ルール未整備、重複・文化摩擦 |
PMI計画、SKU/価格統合、コミュニケーション |
シナジー達成率、統合遅延率 |
|
再生 |
キャッシュ逼迫、撤退遅延 |
90日プラン、価格/原価/販路テコ入れ |
営業CF、粗利率、固定費削減 |
|
観光・地域 |
季節変動、集客の脆弱性 |
需要設計、商品パッケージ、UGC運用 |
稼働率、ADR、再訪率 |
お問い合わせの目安
課題が「曖昧なまま」でも問題ありません。合同会社えいおうは、KPIの棚卸しと優先度付けから伴走し、実行できる範囲でスモールスタート。戦略—価格—チャネル—運用を一本化し、最短距離で成果に結びつける設計で支援します。
あなたの事業を未来へ導く第一歩|事業戦略コンサルティングを成果に変える始め方
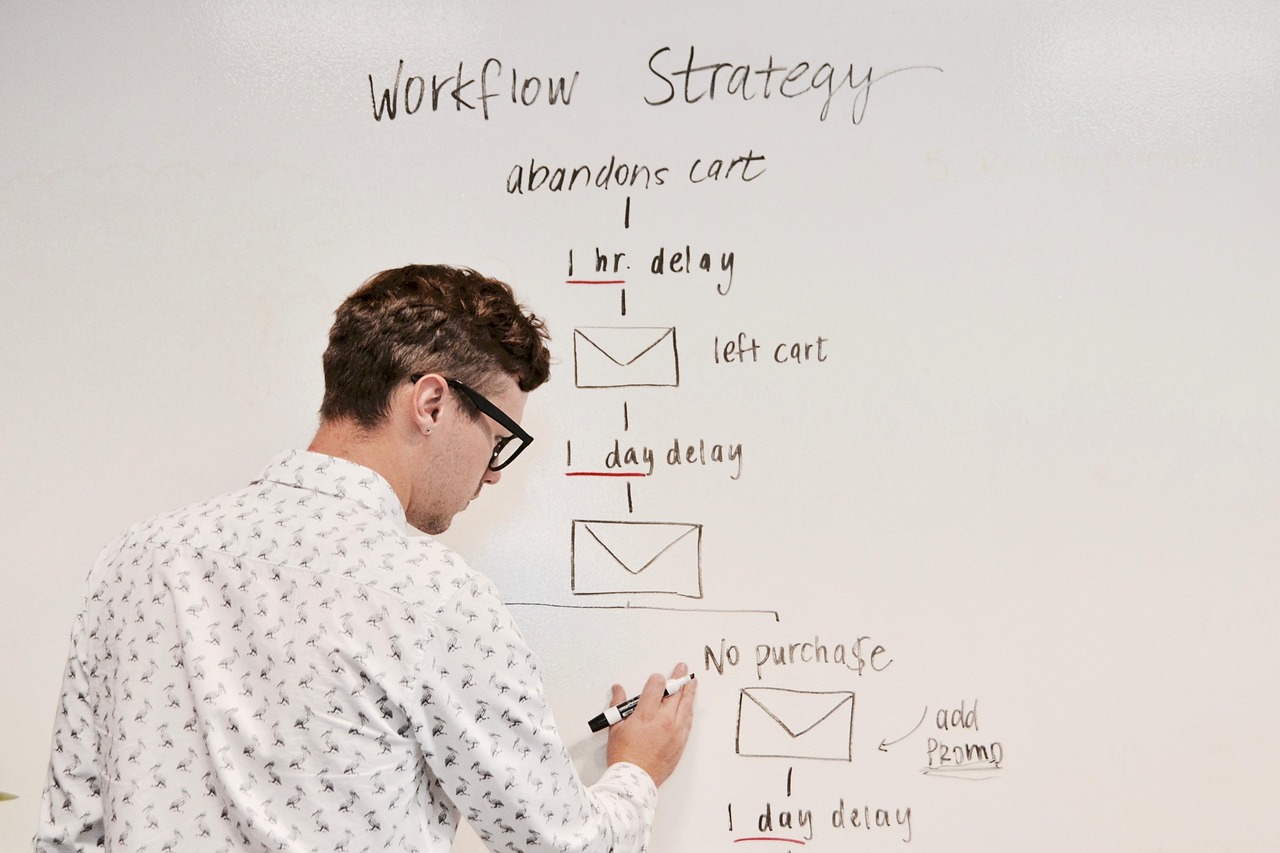
事業戦略コンサルティングの価値は、相談した瞬間から始まります。合同会社えいおうでは、初回ヒアリングで課題の輪郭を素早く掴み、KPI(重要業績評価指標)の棚卸しと仮説づくりへ接続。90日間のクイックウィン設計とPMO(プロジェクトマネジメント)運用をセットに、戦略を“実装できる計画”へ落とし込みます。ここでは、導入の流れ、準備物、投資判断の考え方までを具体的に解説します。
初回コンタクトの進め方:無料相談からスコープ仮説の定義
初回は、経営課題の背景・現状の打ち手・ボトルネックを整理し、スコープ(対象領域)とアウトカム(期待成果)の仮説を置きます。ここで重要なのは、やることだけでなく“やらないこと”も明確化すること。限られたリソースを一点集中させ、早期に手応えを作るための下準備です。
あわせて、KPIの計測単位や現行ダッシュボードの有無も確認します。数字が一箇所に集まっていなくても問題ありません。後続の「KPI棚卸し」で整えます。
現状診断パッケージ:KPI棚卸しと課題の見える化
えいおうの現状診断は、資料の量より意思決定に効く最少セットを重視します。3C/SWOT/PESTといった基本フレームを使いつつ、KPIと業務の実態を照合して“実行で詰まる場所”を特定します。
診断のために確認するデータ項目(例)
-
売上・粗利・在庫回転・受注/失注理由
-
集客〜成約のCVR(転換率)、CPA(獲得単価)、ARPU
-
サブスク/再購買の継続率、解約率、LTV/CAC
-
価格テーブル、割引ルール、チャネル別マージン
診断アウトプット(例)
-
KPIツリー(戦略目標との因果連鎖を可視化)
-
課題バックログ(重要度×緊急度の優先順位)
-
90日で狙うクイックウィン候補と必要リソース
90日アクション設計:クイックウィンで“動く成果”を先に作る
中長期の絵を持ちながらも、最初の90日で成果の芽を出すことが成否を分けます。効果(売上・粗利・リードタイム)と実現容易性で評価し、3〜5本の施策に集中します。
優先順位づけの基準
-
インパクト(利益・成長・リスク低減への寄与)
-
実現容易性(人・期間・コスト・外部依存の少なさ)
-
再現性(仕組みに落ちるか、属人化しないか)
PMO体制と会議体(運用の型)
-
週次:進捗・課題・依存関係を5指標で点検
-
月次:KPIレビューと施策のリプライオリタイゼーション
-
QBR:方向性(OKR)と資源配分の見直し、価格/チャネルの方針更新
実行支援と可視化:ダッシュボードと内製化ロードマップ
えいおうは、SSOT(Single Source of Truth)発想で数字の“唯一の拠り所”をつくります。現状の表計算でも構いません。まずは見える化を先行し、運用の型を整えます。
ダッシュボード要件(最小セット)
-
リード指標×ラグ指標の並列表示(例:商談数↔売上、CVR↔粗利)
-
価格ウォーターフォール(定価→割引→実効価格→粗利)
-
チャネル別KPI(直販/EC/卸)と在庫の健全性
内製化ロードマップ
-
ドキュメント化(KPI定義書、Playbook、会議体ガイド)
-
権限設計とRACI(誰が決め、誰が関与するか)
-
運用移管のマイルストーン設定とトレーニング
投資判断の目安:費用対効果とROIの考え方
意思決定をシンプルにするため、ユニットエコノミクスで考えます。
-
価格改定・ティア設計:ARPU↑と解約率のバランスを検証
-
マーケ施策:CPAの低減だけでなくLTV/CACの改善で評価
-
在庫/オペレーション:在庫回転・欠品率・リードタイムの改善幅を金額換算
簡易の収益式(例)
利益増分≈{(価格改定後ARPU−前ARPU)×継続人数}−追加獲得コスト−運用費
“数字で合意”してから着手することで、後戻りを減らします。
よくある不安とえいおうの対応
|
不安・疑問 |
えいおうの対応 |
指標の目安 |
|---|---|---|
|
現場が忙しく時間が取れない |
90日で3〜5本に絞り、週次30分の定例で推進 |
出席率、期限遵守率 |
|
データがバラバラ |
SSOT化とKPI定義書の整備から着手 |
指標の定義逸脱ゼロ |
|
すぐ成果が出るのか |
クイックウィンと中期施策を併走、先に“見える成果”をつくる |
90日粗利・在庫回転 |
|
費用対効果が心配 |
着手前にKPIと閾値を合意、未達時の打ち手を明確化 |
KPI達成率、ROI |
お問い合わせ前チェックリスト(自己診断)
-
目的と範囲を一文で言える(やらないことも定義している)
-
直近のKPI(売上・粗利・CVR・在庫回転・解約率)が把握できる
-
価格表と割引ルールが存在し、例外の承認者が決まっている
-
週次/月次/QBRの会議体がある、または作る意思がある
-
成果の判定基準(LTV/CACや粗利額など)を合意できる
チェックで空欄が多くても心配ありません。合意形成と設計から伴走します。
合同会社えいおうに相談するメリット
一貫性(戦略—価格—チャネル—運用が一本化)、可視化(KPIと定義の明文化)、実装力(PMOとクイックウィン)、柔軟性(スモールスタート、段階拡張)。この4点で、計画倒れを回避し、投資の確度を高めます。
まずはお気軽にお問い合わせください。現状KPIの棚卸しと90日プランの仮説づくりから、貴社の事業戦略コンサルティングを“成果の出る仕組み”へと組み替えていきます。














