ビジネスデザインという言葉を耳にする機会が増えたものの、「実際には何を指すのか」「どのように活用すればよいのか」と悩む方は少なくありません。経営環境の不確実性が高まる中、従来型の戦略思考だけでは市場の変化に追いつけなくなってきています。そのような時代背景のなかで、「ビジネスデザイン」の重要性が注目されているのです。
この記事をご覧の方は、以下のような悩みを抱えていないでしょうか。
-
「ビジネスデザイン」とは具体的に何を指すのか分からない
-
経営戦略とデザイン思考の関係性が曖昧で活用方法が分からない
-
自社にビジネスデザインをどう導入すればよいかイメージできない
-
他社の成功事例を通じて、実践に活かせるヒントを得たい
本記事では、ビジネスデザインの定義から、その重要性、経営戦略との関係性、実際のプロセス、活用事例、必要なスキル・マインドセット、組織への導入方法、さらには将来性に至るまでを、網羅的かつ初心者にも分かりやすく解説しています。
この記事を読むことで、単なる知識の習得にとどまらず、ビジネスデザインを実務にどう取り入れるかの具体的な手順や視点を得ることができます。そして、最終的には自社の戦略構築や新規事業創出において、より創造的で実効性のあるアプローチを実行できるようになります。
ビジネスデザインを、次なる成長のエンジンとしたいと考えている経営者や戦略担当者、プロジェクトリーダーの方にとって、本記事が確かな道しるべとなることでしょう。
目次
ビジネスデザインとは何か?その定義と重要性

ビジネスデザインは近年、経営やマーケティング、サービス開発など幅広い分野で注目を集めています。特に変化の激しい市場環境の中で、従来の延長線上にはない新たな価値を創造し、持続可能な競争優位を築くための手法として導入が進んでいます。このセクションでは、「ビジネスデザインとは何か?」という基本的な問いに答えながら、その定義と重要性を初心者にもわかりやすく解説します。
ビジネスデザインの定義
ビジネスデザインとは、ビジネスモデルの構築や再設計を目的に、デザイン思考のプロセスを用いて事業やサービスを創り出す手法を指します。
経営学的視点とデザインの創造的アプローチを融合させた考え方であり、以下の要素を含みます。
-
顧客ニーズの深い理解
-
問題解決に向けた仮説検証
-
収益構造や提供価値の設計
-
実行可能性を重視した施策の具現化
たとえば「既存市場での成長が頭打ちになっている」「顧客からの支持が得られにくくなってきた」といった課題に対して、ビジネスデザインは新たな視点を提供します。
ビジネスデザインと経営戦略の関係性
経営戦略は企業の中長期的な方向性や資源配分を定める上位概念です。一方、ビジネスデザインはその戦略を具体的な形に落とし込むための“実行支援”に近い役割を果たします。
たとえば、
-
経営戦略で定めたターゲット市場に対し、どのような提供価値を設計すべきか
-
どのような顧客体験を実現することで競合との差別化が図れるか
-
社内のリソースをどう組み合わせて持続可能な仕組みに昇華させるか
といった問いに対し、ビジネスデザインは具体的な答えを導き出す実務的なアプローチを提供します。
このように、戦略と現場をつなぐ“橋渡し役”としての位置づけで機能する点が、ビジネスデザインの重要な特長です。
サービスデザイン・デザイン思考との違い
ビジネスデザインは、しばしば「サービスデザイン」や「デザイン思考」と混同されがちですが、それぞれに異なる役割があります。
|
概念 |
主な対象 |
アプローチの特徴 |
|---|---|---|
|
デザイン思考 |
問題発見からアイデア創出まで |
共感・発想・試作・テストの反復 |
|
サービスデザイン |
サービス提供プロセスや顧客体験の設計 |
カスタマージャーニーやブループリント |
|
ビジネスデザイン |
ビジネス全体の構造と収益の仕組み |
戦略的視点と実行設計の両立 |
ビジネスデザインはこれらの要素を包含しながら、企業全体の設計という広範な領域に対応します。具体的には、収益モデル、顧客接点、組織構造、パートナーシップ、オペレーションなど、経営全般を視野に入れて構築される点が大きな違いです。
創造と論理の融合が未来を切り拓く
データ分析や戦略フレームワークによる論理的な思考と、デザインによる創造的なアイデア発想。この両輪を活かすビジネスデザインは、既存の常識にとらわれず、新しい価値を社会に届けるための手段として非常に有効です。
変化が激しく、正解のない時代において、直感や想像力だけでなく、構造的かつ実証的な手法で課題を突破する必要があります。ビジネスデザインは、まさにそのための“未来志向の経営デザイン”といえるでしょう。
ビジネスデザインが求められる背景と時代の変化

急激な技術革新と社会構造の変化により、企業は従来の成功パターンでは成長を維持できなくなっています。こうした環境の中で「ビジネスデザイン」が注目される理由には、ビジネスの前提が根本的に変化していることが大きく影響しています。このセクションでは、時代の潮流とともにビジネスデザインの必要性が高まっている背景を解説します。
なぜ今ビジネスデザインが必要なのか?
次のような時代背景が、企業に新しい思考と構造の刷新を迫っています。
-
VUCA時代の到来:Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)が高まり、将来予測が難しくなっている。
-
テクノロジーの急速な進化:AI、IoT、クラウド、ビッグデータなどにより、従来の業界構造が崩壊。異業種からの参入や新興勢力の台頭が加速。
-
サステナビリティ・ESG重視の社会要請:利益追求だけでなく、環境・社会・ガバナンスを意識した経営が求められる。
-
人材の価値観の変化:働く目的や意味を重視する層が増え、企業の存在意義(パーパス)が重要視されている。
このように、単なる利益追求ではなく、「誰のどんな課題を、どのような構造で解決するのか」が、企業の競争力を左右する時代になってきたのです。
ロジャー・マーティンが提唱した“デザイン思考の経営”
ビジネスデザインのルーツとして注目されるのが、カナダの経営学者ロジャー・マーティンが提唱した「デザイン思考を活用した戦略的経営」です。
マーティンは、成功する経営者は「信頼できる直感(reliable intuition)」を活用し、分析的な論理と創造的な発想を統合する“統合的思考(integrative thinking)”ができると述べています。
この考え方は、
-
現状維持ではなく未来の可能性に目を向ける
-
顧客や社会の課題に共感する
-
ビジネスモデルそのものを構造的に設計する
というビジネスデザインの本質に通じるものであり、グローバル企業だけでなく、日本の大企業・中小企業にも広まりつつあります。
日本企業における課題と可能性
日本企業の多くは、長年にわたる「製品中心」「品質重視」の価値観に根ざした経営スタイルが主流でした。しかし、
-
サービス産業の比率拡大
-
少子高齢化による国内需要の縮小
-
グローバル市場における競争激化
といった課題に直面する中で、単なる技術力や品質だけでは持続的な成長が難しくなっています。
そのため、「顧客体験」や「ビジネスモデル全体」を再設計し、新たな価値を創出する能力が問われているのです。ビジネスデザインは、まさにこの課題解決の鍵を握るアプローチといえるでしょう。
図解文化と組織変革の重要性
さらに注目すべきは、ビジネスデザインのプロセスが「視覚化」を重視するという点です。カスタマージャーニーマップ、ビジネスモデルキャンバス、バリュープロポジションキャンバスなど、情報やアイデアを図解することで社内の共通理解が促進されます。
また、ビジネスデザインはプロジェクト単位ではなく、企業文化の変革として導入されるべきものであり、経営層がその推進役となることが成功の鍵となります。
革新が求められる時代、経営と現場が一体となって変革に取り組む必要があります。その中心に「ビジネスデザイン」があるのです。
ビジネスデザインと経営戦略の関係

ビジネスデザインは単なるデザインの枠にとどまらず、経営戦略全体を設計・再構築するための実践的アプローチとして注目されています。本セクションでは、ビジネスデザインが経営戦略に与える影響や、従来の戦略立案との違い、さらに合同会社えいおうがどのようにビジネスデザインを戦略に組み込んでいるのかをご紹介します。
ビジネスデザインは「手段」ではなく「戦略の枠組み」
従来の経営戦略は、競合との差別化や価格競争、コストリーダーシップなど、企業内部のリソースや市場の位置づけをもとに構築されてきました。しかし、現代では環境の不確実性が増し、予測困難な変化に柔軟に対応できるフレームワークが求められています。
ビジネスデザインは、
-
顧客視点(インサイト)から課題を再定義し
-
バリュープロポジション(価値提案)を構築し
-
ビジネスモデル全体を創造・検証し
-
社内の組織や体制もデザインしていく
というアプローチにより、戦略そのものを創造していく役割を果たします。つまり、ビジネスデザインは戦略実行の「手段」ではなく、戦略設計そのものといえるのです。
ビジネスモデルキャンバスとの連動
経営戦略とビジネスデザインの連携において、頻出するのが「ビジネスモデルキャンバス(Business Model Canvas)」です。このツールは、9つの要素からビジネス構造を視覚的に整理するフレームワークで、以下のような構成になっています。
|
要素 |
説明 |
|---|---|
|
顧客セグメント |
誰に価値を提供するのか |
|
バリュープロポジション |
どんな価値を提供するのか |
|
チャネル |
どのように届けるか |
|
顧客関係 |
顧客との関係性はどう構築するか |
|
収益の流れ |
どのように収益を得るか |
|
リソース |
何が強み・資源となるか |
|
活動 |
必要な主要活動は何か |
|
パートナー |
外部連携はどうするか |
|
コスト構造 |
どこにコストがかかるか |
このキャンバスを活用することで、経営者は戦略を具体化し、チーム全体で共通認識を持つことが可能になります。
合同会社えいおうの事業戦略コンサルティングにおけるビジネスデザインの活用
合同会社えいおうでは、中小企業やスタートアップ企業を対象にした事業戦略コンサルティングにおいて、「ビジネスデザインの実装支援」を行っています。
特に重視しているのは次の3点です。
-
現状分析と顧客インサイトの抽出:マーケットデータだけでなく、インタビューや観察による定性的情報を活用
-
仮説立案とプロトタイピング:短期間で戦略案を設計・検証し、必要に応じて柔軟に修正
-
組織の巻き込みと体制構築:トップダウンではなく、現場と対話しながら“共創型”で戦略を推進
このように、単なるアドバイスにとどまらず、組織内部に「戦略を自らデザインする力」を根付かせる支援を行っている点が特徴です。
ビジネスデザインは、戦略を“描く”だけでなく、社内に“根づかせる”ことこそが成功の鍵といえるでしょう。
ビジネスデザインの活用事例から学ぶ成功パターン

ビジネスデザインは、業種や業界を問わずさまざまな企業で活用され、革新的な価値創造を実現しています。このセクションでは、実際にビジネスデザインを取り入れた企業の成功事例を紹介し、どのように活用されたのか、また共通する成功要因は何かを紐解いていきます。
大企業におけるビジネスデザインの導入例
1. 富士フイルム
フィルム需要の急減という危機的状況のなか、富士フイルムはヘルスケア事業など新領域に進出。デザイン思考を活用し、ユーザー起点で事業転換を成功させました。
2. パナソニック(家電事業部)
家電製品のUI/UXにビジネスデザインの視点を取り入れ、“プロダクトアウト”から”マーケットイン”への意識転換を図りました。結果として、顧客満足度とブランド評価の向上を実現。
スタートアップ企業での活用事例
1. AirBnB
もともと収益性に課題があったAirBnBは、利用者体験の改善を中心にデザイン戦略を導入。カスタマージャーニーを徹底的に再設計したことで、グローバルブランドとして成長。
2. note(ピースオブケイク社)
コンテンツプラットフォーム「note」は、サービス立案段階からユーザーの動機や行動背景に着目し、ミニマルでわかりやすいUIを構築。共感設計による支持を得て急成長しました。
成功企業に共通する3つの視点
ビジネスデザインの導入に成功した企業には、以下のような共通点があります。
|
視点 |
内容 |
|---|---|
|
ユーザー起点 |
顧客の課題や価値観に基づいて課題設定を行う |
|
統合思考 |
経営・開発・マーケティングなど、部門を超えた視点で戦略を立案 |
|
実験文化 |
完璧を目指すのではなく、仮説検証を繰り返して学習する文化を醸成 |
これらの視点は、企業規模や業種にかかわらず、ビジネスデザインを成功させるために欠かせない共通項といえます。
合同会社えいおうの支援事例
合同会社えいおうでは、中小企業が抱える事業拡大の課題や、新規サービスの立ち上げに対してビジネスデザインを活用しています。たとえば、ある食品メーカーでは、
-
ターゲット層の再定義
-
ブランド体験の再構築
-
オンラインとオフラインの購買体験の設計
を支援し、新ブランドの立ち上げ後、半年で売上120%増という成果を挙げています。
このように、成功事例から導き出される共通点を理解し、自社に最適な形でビジネスデザインを活用することが、競争力ある経営につながります。
ビジネスデザインのプロセスとフレームワーク

ビジネスデザインを効果的に活用するためには、体系的なプロセスと信頼性のあるフレームワークを理解し、実務に応用することが不可欠です。このセクションでは、代表的なビジネスデザインのプロセスを段階的に解説し、それを支えるフレームワークについても紹介します。
ビジネスデザインの基本プロセス
ビジネスデザインのプロセスは、一般的に以下の5つのステップで構成されます。
|
ステップ |
内容 |
|---|---|
|
1. 問題定義 |
顧客や市場の課題を掘り下げ、本質的な問いを導き出す |
|
2. インサイト収集 |
ユーザー調査やデータ分析により、行動や価値観の深層を理解する |
|
3. アイデア創出 |
課題解決に向けた価値提案やサービス構想を幅広く発想する |
|
4. プロトタイピング |
仮説となるサービスやプロセスを小規模で形にして検証する |
|
5. ビジネスモデル構築 |
実現可能性や収益性を見極めた上で、持続可能な仕組みを設計する |
この一連の流れは、仮説と検証の繰り返し(アジャイル的アプローチ)で進行し、計画よりも学習と柔軟な修正が重視されます。
代表的なフレームワーク
ビジネスデザインでは、以下のようなフレームワークが頻繁に使用されます。目的に応じて適切なものを選び、プロセスに組み込むことがポイントです。
ビジネスモデルキャンバス(Business Model Canvas)
9つの構成要素に分解し、ビジネス全体の価値提供・流れ・収益性を可視化するフレームワーク。戦略立案やピボット判断に有効です。
バリュープロポジションキャンバス(Value Proposition Canvas)
「顧客の課題」と「提供する価値」のフィット感を確認するための設計図。プロダクトマーケットフィットの検証に最適です。
カスタマージャーニーマップ
顧客の体験プロセスを時系列で可視化し、感情の起伏や接点を整理することで、UX向上や改善点の発見に活用されます。
デザイン思考(Design Thinking)
共感・定義・発想・プロトタイプ・テストという5段階からなる思考法。ユーザー中心のアプローチを実現する基本となる考え方です。
合同会社えいおうの導入アプローチ
合同会社えいおうでは、クライアントの課題に応じて柔軟にフレームワークを組み合わせ、短期間で効果検証できるプロセス設計を行います。特に、
-
既存ビジネスの構造整理 → ビジネスモデルキャンバス
-
新規事業の立ち上げ支援 → バリュープロポジション+プロトタイピング
-
顧客接点の再構築 → カスタマージャーニーマップ
といった形で、フェーズに応じたデザインを実施。
また、初期段階から経営層だけでなく現場メンバーを巻き込むことで、プロセスの中で生まれる気づきを組織全体に還元することを大切にしています。
プロセスとフレームワークを理解して活用することは、戦略と実行の溝を埋め、ビジネス成功へと導く橋渡しとなるのです。
ビジネスデザインに必要なスキルとマインドセット

ビジネスデザインを実践するには、単なるデザインスキルだけではなく、戦略的思考や顧客志向のマインドセット、部門を超えた調整力など、複数の能力が求められます。このセクションでは、ビジネスデザインを担う人材に求められる具体的なスキルセットとマインドセットについて詳しく解説します。
ビジネスデザインに求められるスキル
ビジネスデザインを効果的に進めるためには、以下のようなスキルが重要です。
|
スキルカテゴリ |
具体的なスキル内容 |
|---|---|
|
観察・洞察力 |
ユーザーリサーチや市場観察を通じて本質的な課題を見抜く |
|
創造力 |
制約を乗り越えて新たなアイデアやコンセプトを発想する |
|
論理的思考力 |
発想を構造化し、実現性と収益性の観点で評価する力 |
|
ビジネス構築力 |
収益モデルの設計や資源配分、KPI設定などの戦略設計能力 |
|
プロトタイピング力 |
仮説を早く形にしてテストする実行力 |
|
ファシリテーション力 |
部門間の調整やワークショップ運営を円滑に進める能力 |
これらのスキルは、一人の人材がすべて備える必要はなく、プロジェクトチーム全体で補完し合う体制を整えることが現実的です。
ビジネスデザインにおけるマインドセット
ビジネスデザインでは、以下のような姿勢・考え方(マインドセット)が極めて重要とされています。
-
ユーザー中心主義:常に顧客の体験や感情を出発点として思考する
-
仮説思考と柔軟性:完璧を求めず、小さな実験から学びを得る姿勢
-
統合的視点:デザイン・ビジネス・テクノロジーを横断的に見る視野
-
共創志向:一人で完結させず、多様な視点とともに考える態度
-
失敗容認と学習志向:失敗を避けるのではなく、学びの契機と捉える姿勢
このようなマインドセットは、単なる思いつきのアイデアを「実現性あるビジネス」へと昇華させるための土台となります。
合同会社えいおうが重視する人材像
合同会社えいおうでは、クライアント企業のビジネスデザイン支援を行ううえで、以下のような人材像を重視しています。
-
ユーザーインサイトを捉える定性・定量のバランス感覚
-
顧客と伴走しながら「問い」を共創できるファシリテーション力
-
戦略と現場の実行をつなげる橋渡し役としてのマネジメント視点
また、えいおうの支援では、経営者層だけでなく現場の中堅社員・プロジェクトメンバーも巻き込むことを大切にしており、マインドセットの浸透も支援範囲に含まれています。
ビジネスデザインに必要なスキルとマインドを育成することで、単なる施策ではなく、持続可能な事業変革が実現可能となります。
ビジネスデザインにおける顧客理解の重要性

ビジネスデザインを実践する上で最も重要な要素の一つが「顧客理解」です。顧客の行動や価値観、感情の変化を深く理解することが、革新的なビジネスモデルの創出や、既存事業の再構築に直結します。このセクションでは、顧客理解の意義や、具体的な手法、企業が陥りがちな落とし穴について解説します。
なぜ顧客理解がビジネスデザインで重要なのか
顧客のニーズや行動は時代とともに変化します。単に製品やサービスを提供するだけではなく、「顧客がなぜそれを必要とするのか」「どのような体験を求めているのか」を深掘りすることが不可欠です。
ビジネスデザインではこの顧客視点を出発点とし、以下のような効果が期待されます。
-
顧客が本当に求めている価値を明確化できる
-
サービス体験全体を設計するための起点になる
-
新たな市場機会やニッチ市場を発見できる
-
競合との差別化要素を明確にできる
単なる属性データ(年齢、性別など)ではなく、動機・行動・感情といった「インサイト(洞察)」に着目することがビジネスデザインの鍵です。
顧客理解のための主要手法
|
手法 |
概要 |
|---|---|
|
ユーザーインタビュー |
顧客の行動や動機を深堀する1対1の定性調査 |
|
カスタマージャーニーマップ |
顧客の体験プロセスを時系列で可視化し、感情や課題を整理する手法 |
|
ペルソナ設計 |
典型的な顧客像を具体化し、意思決定の基準に活用する |
|
エスノグラフィー調査 |
顧客の日常環境に入り込み、行動観察を行う定性的アプローチ |
|
N1分析 |
1人の顧客の詳細なケースから仮説を立てるミクロ視点の分析 |
これらの手法を組み合わせることで、表面的なニーズだけでなく、潜在的な動機や価値観に迫ることが可能です。
顧客理解で陥りやすい落とし穴
-
思い込みによる決めつけ:自社の視点で顧客像を決めつけてしまうと、本質的な課題を見落とすリスクが高まります。
-
一過性の調査で終わる:リサーチ結果を活用せず、単なる形式になってしまうケース。
-
全体像を捉えられない:断片的な情報にとらわれ、顧客体験の全体設計に結びつけられない。
これらを防ぐためには、調査だけでなくチーム内でのインサイト共有や継続的な仮説検証が不可欠です。
合同会社えいおうが行う顧客理解支援
合同会社えいおうでは、ビジネスデザイン支援において以下のような顧客理解の取り組みを支援しています。
-
経営陣・現場メンバーを交えたユーザーインタビュー設計と実施
-
カスタマージャーニーマップ作成を通じたインサイトの共通認識化
-
ペルソナの再設計を通じてマーケティング施策と連動
このような取り組みによって、企業内の意思決定やプロダクト開発の精度を高め、顧客起点のビジネス変革を実現しています。
ビジネスデザインにおける顧客理解は、戦略・マーケティング・サービス設計のすべての土台であり、企業競争力の源泉となる重要なプロセスです。
ビジネスデザインを成功に導く組織と文化の条件

ビジネスデザインを戦略の中核に据えて実践するには、個人のスキルだけでなく、それを支える「組織体制」や「企業文化」の整備が不可欠です。どれほど優れたアイデアやデザインのフレームワークを用いても、組織全体が変革に対応できる体制でなければ、ビジネスデザインは形骸化してしまいます。
このセクションでは、ビジネスデザインを推進する上で重要となる組織の要件と文化的要素、また企業が陥りやすい課題とその克服方法について詳しく解説します。
ビジネスデザイン推進に必要な組織の特徴
ビジネスデザインを社内で実践するには、次のような特徴を備えた組織体制が重要です。
|
要件 |
説明 |
|---|---|
|
クロスファンクショナルチーム |
マーケティング・開発・営業・経営企画など部門横断で構成され、共創できる体制 |
|
トップダウンとボトムアップの両立 |
経営陣による意思決定と、現場からの気づきや提案の融合 |
|
機動的なプロトタイピング体制 |
仮説検証を迅速に行い、結果を元に柔軟に軌道修正できる体制 |
|
継続的な学習と評価 |
成果に対する評価制度と、チャレンジを奨励する仕組み |
これらの体制が揃うことで、顧客起点の視点を事業に反映させることが可能になります。
デザインドリブンな文化を育てるために
組織体制とともに不可欠なのが、社内に「デザイン思考」を根付かせる文化的な取り組みです。特に次のような文化が浸透していることが理想とされます。
-
仮説検証を前提とした思考:失敗を恐れず試行錯誤を歓迎する風土
-
共創と対話を重視:個人プレーではなく、チーム全体で価値を生み出す
-
可視化・図解文化の浸透:アイデアや課題を言語とビジュアルの両面で共有する習慣
-
ユーザー中心の視点:どの業務も顧客価値に接続して考えるという共通認識
とくに「図解文化」は、複雑な事業戦略や顧客体験を整理・共有する上で有効なコミュニケーション手法であり、合同会社えいおうでも重要視しているポイントです。
組織導入における課題と克服法
ビジネスデザインの導入において企業がよく直面する課題には次のようなものがあります。
-
既存業務との並行が困難:通常業務が優先され、新しい取り組みに時間が割けない
-
評価制度が挑戦を阻害:失敗を避ける文化が根強く、仮説検証が進まない
-
デザインを専門部署任せにしてしまう:全社的な取り組みにならず部分最適に陥る
これらを乗り越えるには、トップマネジメントの強いコミットメントと、現場との対話、制度面の見直しが重要です。具体的には次のような施策が有効です。
-
経営陣自らがユーザーインタビューやプロトタイピングに参加する
-
ビジネスデザイン活動への関与を人事評価に反映させる
-
社内勉強会やデザインスプリントを定期開催し、関心を継続的に醸成する
合同会社えいおうの組織変革支援
合同会社えいおうでは、事業戦略コンサルティングの一環として、ビジネスデザイン導入に向けた組織支援を行っています。たとえば、以下のような施策を通じてクライアントの企業文化醸成を支援しています。
-
デザイン文化導入のためのワークショップ設計とファシリテーション
-
図解を活用した社内プレゼン資料の整備支援
-
現場巻き込み型プロジェクト設計
ビジネスデザインの成否は「スキル」だけではなく、それを受け入れる「文化と仕組み」によって決まります。戦略を絵に描いた餅にしないためにも、組織づくりこそが変革のカギです。
ビジネスデザインの未来と可能性
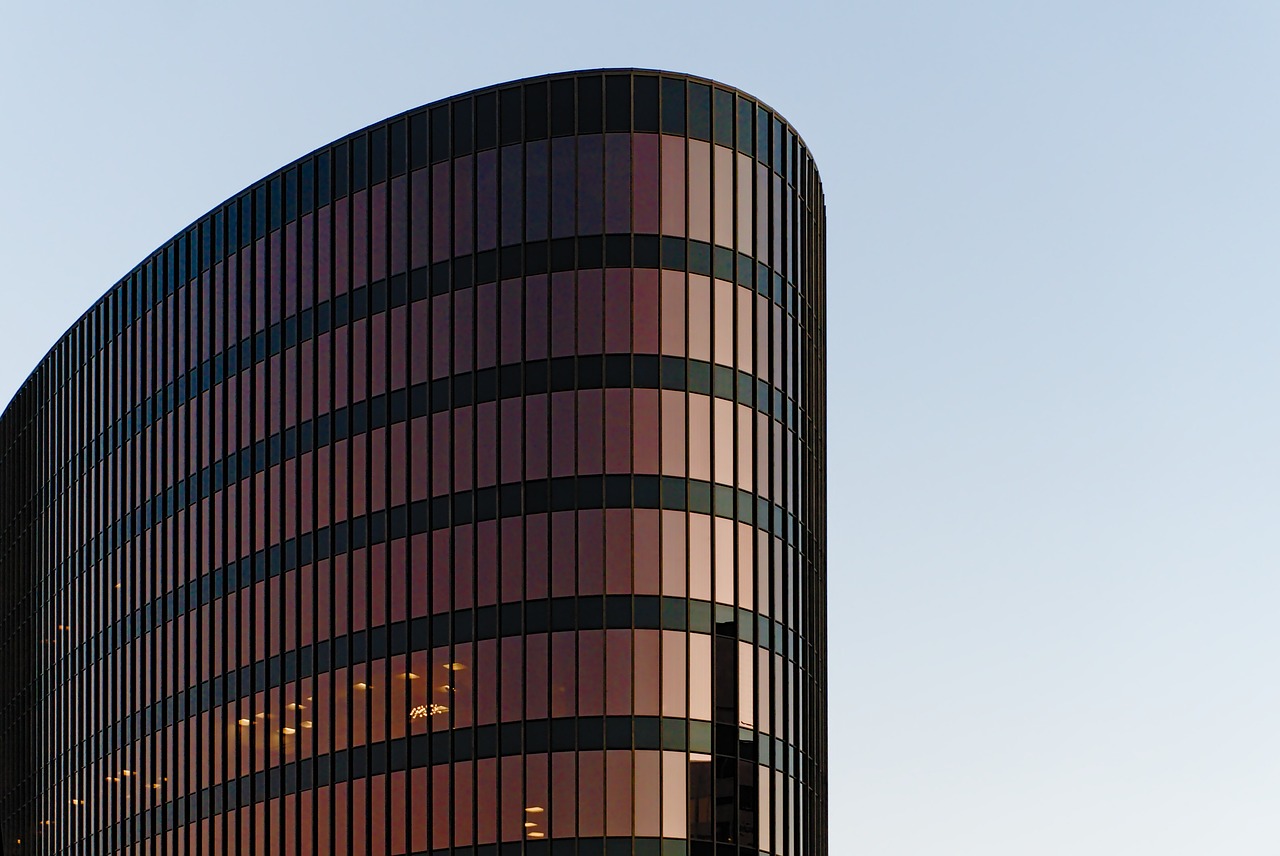
急速に変化する社会や市場環境において、ビジネスデザインは単なる手法ではなく、企業が持続的に成長するための「思考の軸」としての役割を強めています。DX(デジタルトランスフォーメーション)やSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)といったキーワードが注目される今、ビジネスデザインはそれらの土台として機能し、今後ますますその重要性を増していくことが予想されます。
このセクションでは、ビジネスデザインの未来に向けた進化の方向性や、新たな適用分野、企業にもたらす可能性について考察します。
テクノロジーとの融合による進化
AI(人工知能)、IoT、XR(拡張現実)などの先端テクノロジーが加速度的に進化する中で、ビジネスデザインはこれらと融合し、次のステージへ進もうとしています。
-
AIによるユーザーインサイトの自動抽出:インタビューやアンケート結果からのパターン解析が進化
-
XRを活用したプロトタイピング:実際の空間・体験を仮想的に再現し、UXを視覚的に確認可能に
-
ノーコード・ローコードツールとの統合:アイデアをすぐにカタチにしやすくなることでプロセスが高速化
これらの技術との連携により、ビジネスデザインのスピード・精度・表現力は飛躍的に向上します。
社会課題解決との接続
近年は、営利目的にとどまらず、社会課題の解決をビジネスの中核に据える企業が増えています。特にESG(環境・社会・ガバナンス)投資の拡大やSDGsの浸透により、次のような視点がビジネスデザインにも求められています。
-
環境負荷を軽減するサーキュラーエコノミー型のビジネスモデル設計
-
地域社会や多様性に配慮したサービスデザイン
-
従業員やサプライチェーンパートナーを巻き込んだ共創型の取り組み
このように、ビジネスデザインは社会的価値の創出と収益性の両立を支える鍵でもあります。
教育・育成分野への広がり
ビジネスデザインの思考法は、近年ビジネススクールや企業研修でも重要なカリキュラムの一部として取り上げられています。合同会社えいおうでも、次世代の経営人材育成を目的としたワークショップや講座の提供を行っています。
-
事業開発における思考プロセスの標準化
-
問題解決力・構造化力・共創力の育成
-
実践的なプロジェクトを通じた「ビジネス構想力」の養成
こうした取り組みは、社内におけるビジネスデザイン人材の増加や、全社的な価値創造文化の醸成につながります。
ビジネスデザインがもたらす未来像
ビジネスデザインの本質は、「変化を前提とした価値創造の仕組みづくり」です。単に顧客体験を設計するだけではなく、時代の変化や不確実性を受け入れながら、新しい価値を見出し続ける企業体制を構築することにあります。
未来におけるビジネスデザインは、経営の意思決定に直結する中核的なプロセスとなり、次のようなビジョンの実現に貢献するでしょう。
-
組織を超えた共創とネットワーク型経営の確立
-
ユーザー中心から「地球・社会中心」へと拡張する視点
-
「構想→試行→実装→進化」の高速サイクル化
ビジネスデザインは今後、より多くの領域に浸透し、あらゆる組織の未来構想を支える中核的な思考となっていくことが期待されます。
ビジネスデザインを実践に移すための第一歩

この記事をここまで読まれた方は、「ビジネスデザイン」という言葉が単なる流行語ではなく、変化の激しい時代において企業が持続的に成長するための根幹をなす概念であることをご理解いただけたのではないでしょうか。
では、ここからどのようにビジネスデザインを自社で実践していくか。その第一歩は、「現状を見直し、再構想する」ことから始まります。特別なツールや技法よりも、まず大切なのは“問い”を立てる姿勢です。
-
なぜ今の事業を続けているのか?
-
顧客が本当に求めている体験は何か?
-
既存の枠組みに囚われていないか?
-
これからの社会で果たすべき企業の役割とは?
こうした根本的な問いに立ち返ることが、ビジネスデザインの起点となります。
合同会社えいおうでは、事業戦略とデザイン思考を統合したアプローチにより、企業の新規事業創出・サービス再構築・組織変革を支援しています。単なるアドバイスではなく、経営と現場をつなぐ伴走型のコンサルティングを通して、企業が自ら「考え」「つくり」「育てる」力を醸成することを重視しています。
もし、この記事を読んで「自社にもビジネスデザインが必要だ」と感じたのであれば、ぜひ一度お問い合わせください。
-
現状分析・機会探索のワークショップ
-
価値仮説の検証と事業アイデアの具体化
-
ビジネスモデル設計とMVP開発
-
組織浸透に向けた内製化・人材育成
など、貴社のフェーズに合わせた柔軟なサポートが可能です。
ビジネスデザインを机上の知識で終わらせず、「実装可能な戦略」としてカタチにしたい方は、合同会社えいおうの「ビジネスデザイン支援サービス」をご活用ください。未来の競争力は、いま構想し、実行する力から生まれます。














