新規市場開拓の方法を検索されているあなたは、次のような課題を抱えていないでしょうか。
-
新しい市場に挑戦したいが、何から始めればいいか分からない
-
自社のサービスを新しいターゲット層に届けたいが、うまく広げられない
-
営業や販促の手段は持っているものの、成果が出る戦略が見えてこない
-
新規市場を狙った取り組みを始めたものの、社内にノウハウがなく手探り状態
-
KPIの設計や施策の効果測定が曖昧で、改善の方向性がつかめない
この記事は、そんな悩みを持つ中小企業の経営者やマーケティング・営業担当者の方に向けて、「新規市場開拓の方法」を基礎から丁寧に解説する実践ガイドです。
市場調査やターゲット設定といった基本ステップはもちろん、失敗を防ぐための戦略設計、成果につなげるためのアプローチ手法、そして継続的に改善していくためのKPI設計やPDCA運用まで、「新規市場開拓の方法」として必要な要素を網羅的に紹介します。
さらに、実際に新しい市場に進出して成果を上げた国内外の成功事例や、ありがちな失敗パターンとその回避策についても具体的に取り上げているため、理論だけでなく、すぐに現場で役立つ実践ノウハウとして活用いただけます。
この記事を読み終える頃には、自社の強みを活かしながら、ターゲット市場を正確に見極め、効果的な施策を段階的に実行するための考え方と行動指針が身についているはずです。自信を持って次の一手を打てるようになる、実践型のロードマップとしてご活用ください。
目次
なぜ今「新規市場開拓の方法」が注目されているのか

新型コロナウイルスの影響や物価高、人口減少、さらには業界内での競争激化といった経済環境の変化により、既存市場だけに依存した経営は年々リスクを増しています。こうした背景のなかで、企業が継続的に成長するためには、これまで未開拓だった新しい市場への進出が不可欠となっています。特に中小企業やスタートアップ企業では、「新規市場開拓の方法」を体系的に学び、実践することが経営の命運を左右するともいえる状況です。
ここでは、「新規市場開拓の方法」が現代のビジネスシーンで注目されている理由をわかりやすく解説します。併せて、関連キーワードである「市場調査」「ターゲット設定」「競合分析」「販路拡大」「BtoB戦略」などにも触れながら、背景と必要性について詳しく見ていきます。
既存市場に依存することの限界とは?
多くの企業は、自社が長年にわたって築いてきた既存の顧客基盤や販路に大きく依存しています。しかし、次のような理由から、既存市場だけでは将来の持続的な成長は見込めなくなってきています。
-
市場の飽和:ニーズの頭打ちにより売上の成長が鈍化
-
競合の増加:新規参入や価格競争で利益率が低下
-
顧客ニーズの変化:従来のアプローチが通用しなくなる
-
少子高齢化などの社会構造の変化:将来的な市場縮小リスク
これらのリスクを回避し、企業の生存と成長を図るには、新たな顧客層やニーズを取り込む「新規市場開拓」が欠かせません。とりわけ、中小企業においては限られた資源を効率よく活用するためにも、戦略的な市場選定とアプローチ設計が求められています。
「新規市場開拓の方法」が注目される社会的・経済的背景
現代の企業を取り巻く環境は、数年前とは大きく変わりつつあります。次のような要因が、「新規市場開拓の方法」への注目を高める大きなきっかけとなっています。
1. コロナ禍による市場構造の変化
パンデミックにより、対面型営業が困難になったことを契機に、多くの企業が新たなオンライン市場や越境EC(海外販路)への進出を模索するようになりました。既存の販路に代わるチャネルとして、新たな市場ニーズを開拓せざるを得ない状況が生まれたのです。
2. デジタル化の進展と顧客行動の変化
インターネットやSNSの普及により、顧客の情報収集行動が多様化・高速化しました。これにより、従来のBtoB営業では対応しきれない情報提供や顧客体験の設計が必要になり、より顧客に寄り添ったアプローチが求められています。
3. 多様なニーズへの対応力が求められる時代へ
「SDGs」「サステナビリティ」「ウェルビーイング」など、価値観の変化も新市場創出の重要な原動力となっています。単なる商品の販売ではなく、社会的意義や共感を伴った新たな切り口での市場提案が注目されています。
4. 中小企業の生き残り戦略としての必要性
リソースの限られた中小企業こそ、限られた経営資源で効率的に成果を上げる必要があります。新たな市場を見つけ出し、ニッチなポジションを確立することができれば、大手と競合せずに高収益なビジネスモデルを築くことが可能になります。
「販路拡大」と「新市場開拓」はどう違うのか?
混同されがちですが、「販路拡大」と「新規市場開拓」は似て非なるものです。
|
区分 |
販路拡大 |
新市場開拓 |
|---|---|---|
|
対象 |
既存市場内の販売ルート増加 |
未開拓市場の顧客層獲得 |
|
例 |
ECサイトを開設して販売チャネルを増やす |
海外進出/新しいターゲット層の獲得 |
|
主目的 |
流通量の拡大 |
新規売上源の獲得 |
|
難易度 |
比較的低い |
高度な戦略設計が必要 |
新規市場開拓には、単にルートを増やすだけでなく、「誰に」「どのような価値を」提供するのかを根本から見直す姿勢が求められます。そのためには、しっかりとした市場調査やターゲット設定、競合分析といった事前準備が欠かせません。
新規市場開拓が企業にもたらす主なメリット
企業が積極的に新規市場へ参入することで、以下のような成果が期待できます。
-
売上源の多角化による経営安定化
-
競合の少ないブルーオーシャン市場での優位確保
-
自社ブランドの拡張と新たな価値創出
-
既存事業とのシナジーによる相乗効果
-
従業員やパートナー企業の意識変革・モチベーション向上
これらのメリットは、単なる数字的成長にとどまらず、企業の持続可能性(サステナビリティ)やブランド価値の向上にも寄与します。だからこそ、「新規市場開拓の方法」は今、あらゆる業種業態で注目されているのです。
変化の時代に挑戦する企業だけが、新たな未来を切り拓く
変化の激しい今の時代、企業にとって「現状維持」はもはやリスクです。逆に言えば、今こそが「新規市場開拓」というチャレンジを始める最大のチャンスともいえるでしょう。
市場の変化は脅威であると同時に、柔軟に対応できる企業にとっては新たな成長の源泉になります。自社の強みを活かし、顧客の課題を見極め、適切な戦略をもって市場にアプローチすれば、どんな企業にも新しい道が開けます。
新規市場開拓を成功させるための思考整理

新しい市場に参入するには、いきなりアクションを起こすのではなく、まず「思考の整理」が不可欠です。成功している企業ほど、事前に「なぜその市場を狙うのか」「自社にとってその市場がなぜ重要なのか」といった論理的な整理ができています。
ここでは、「新規市場開拓の方法」における出発点として、思考をどう組み立てるべきかをわかりやすく解説します。関連キーワードである「ターゲット設定」「市場選定」「戦略設計」「競合との違い」なども活用しながら、戦略的思考の土台づくりを紹介します。
新規市場開拓における代表的な課題と検索意図
多くのビジネスパーソンが「新規市場開拓」と聞いて最初に感じるのは、「どこから手をつければ良いかわからない」という漠然とした不安です。実際にGoogle検索で見られる検索意図には、次のような傾向があります。
-
「新規市場開拓の進め方がわからない」
-
「具体的な成功事例が知りたい」
-
「BtoB向けとBtoC向けの違いを知りたい」
-
「ターゲットの選び方に悩んでいる」
これらはすべて、「戦略が曖昧なまま進めようとしている」ことが根本原因といえるでしょう。つまり、開拓対象の市場や顧客が不明確であれば、どんな優れた商品や営業力があっても成果は出にくいのです。
そのため、まず最初に必要なのが「市場を見極める力」と「戦略的思考の整理」です。
新規市場開拓を進めるべきタイミングと判断基準
新規市場開拓を始めるべきかどうか、企業にとっては大きな経営判断となります。しかし、次のような兆候が見られる場合は、すでにその必要性が高まっていると考えてよいでしょう。
|
タイミングの兆候 |
内容 |
|---|---|
|
売上が頭打ちになってきた |
既存市場の成長率が鈍化、または停滞している |
|
顧客のニーズが変化してきた |
既存の商品・サービスが受け入れられにくくなっている |
|
競合が増えてきた |
差別化が難しくなり、価格競争が激化している |
|
営業活動の効率が落ちてきた |
従来の営業スタイルでは成果が出にくくなっている |
このような状況下で市場開拓に踏み切る場合、重要なのは「短期的な売上補填」ではなく、「長期的な成長戦略」としての捉え方です。リスクを最小限に抑えるには、まず仮説ベースで小さくテストを行い、フィードバックを得ながら本格展開に進むという流れが理想です。
また、開拓を急ぎすぎると「市場選定のミス」や「ターゲットのズレ」といった問題を引き起こす可能性があるため、冷静な判断と段階的な進め方が求められます。
機動的に動く前に「思考を整える」ことの意味
新規市場開拓は、単に新しい商品を売ることではありません。「誰に」「何を」「なぜ」「どのように届けるのか」という、根本的な問いに答えることがすべての出発点です。これが曖昧なままでは、どんなに優れたプロモーションを打っても結果にはつながりません。
以下の3点は、思考整理の軸として非常に重要です。
-
なぜこの市場を狙うのか(市場性・成長性)
-
なぜ今取り組む必要があるのか(タイミング)
-
なぜ自社がその市場で勝てるのか(差別化・強み)
これらを明確にしておくことで、戦略や実行計画にブレが生じにくくなり、社内外の関係者と方向性を共有しやすくなります。
マーケティングの基本フレームである3C分析(Customer・Competitor・Company)やSWOT分析などを活用して、自社と市場の関係性を俯瞰的に捉えることも大きな効果を発揮します。
思考整理が市場開拓成功のカギを握る
「新規市場開拓の方法」は、実践スキルと同じくらい、「思考の質」によって結果が左右されます。闇雲に行動するのではなく、ターゲット選定、時機の見極め、自社の強みの再確認など、事前の整理を怠らない企業ほど、失敗を回避しやすくなります。
また、思考が整理されていれば、チーム内の合意形成や実行スピードも大きく向上します。新規市場開拓は組織で取り組むテーマであり、思考の「共有」も成果に直結するのです。
新規市場開拓の基本ステップ【初心者向けフレーム】

新規市場開拓の成功には、直感や勢いだけに頼るのではなく、戦略的に構築されたステップを踏んでいくことが重要です。特に中小企業や新規事業担当者にとっては、リソースが限られているからこそ、効率よく的確な判断をするためのフレームワークが求められます。
このセクションでは、「新規市場開拓の方法」を実践するための基本ステップを順を追って解説します。キーワードとして重要な「市場調査」「ターゲット設定」「GTM(Go-to-Market)戦略」「カスタマージャーニー設計」などにも触れながら、初心者でも理解しやすい流れを紹介します。
ステップ1:市場調査とターゲット設定の方法
最初に取り組むべきは、「どの市場を狙うべきか」「どのような顧客に価値を届けるか」を見極めるための市場調査とターゲット設定です。
■ 市場調査とは何か?
市場調査(マーケットリサーチ)とは、対象とする業界や消費者のニーズ、競合の動向などを把握する活動です。以下のような情報を集めることで、進出すべき市場の妥当性を判断できます。
-
市場規模と成長性
-
顧客の購買行動や属性(年齢・性別・地域など)
-
競合企業の数とシェア、強み・弱み
-
法規制や外部環境(PEST分析など)
これらの情報は、政府統計データ、業界団体のレポート、Googleトレンドなどの無料ツールでも一定の調査が可能です。
■ ターゲット設定の重要性
市場を選定したら、次に「誰に売るか」を明確にします。これがターゲティング(ターゲット設定)です。
ターゲットが曖昧だと、商品設計・広告・営業手法すべてがブレてしまいます。BtoBの場合は業種・規模・担当者属性、BtoCの場合は年齢・性別・生活習慣などをもとに具体的に絞り込みましょう。
ペルソナ設定も有効な手法です。ペルソナとは「架空の理想的な顧客像」を指し、その人物の価値観・悩み・行動を設定することで、戦略の軸が明確になります。
ステップ2:カスタマージャーニー設計とニーズ可視化
ターゲットが決まったら、次は「その顧客がどのようなプロセスで商品を知り、購入に至るのか」を設計する必要があります。これをカスタマージャーニー設計と呼びます。
■ カスタマージャーニーとは?
カスタマージャーニーとは、顧客が商品・サービスを知り、比較し、購入・利用に至るまでの一連の行動・心理プロセスを指します。
一般的には以下のような5段階で構成されます。
|
フェーズ |
内容 |
|---|---|
|
認知 |
商品やブランドの存在を知る |
|
興味 |
詳細情報を調べる、比較検討する |
|
欲求 |
自分に必要だと感じ始める |
|
行動 |
実際に問い合わせ・購入する |
|
継続 |
リピート・紹介する |
この流れに沿って、各フェーズでどんな情報が必要か/どのチャネルが有効か/何が障壁になるかを洗い出すことで、的確なマーケティング施策が打てるようになります。
ステップ3:GTM(Go-to-Market)戦略の構築
市場と顧客が見えてきたら、次はGTM(Go-to-Market)戦略を構築します。これは「どのようにしてその市場に自社商品・サービスを投入するか」を設計するフェーズです。
■ GTM戦略とは?
GTM戦略とは、製品やサービスを新しい市場に導入するための「マーケティング・営業・製品・オペレーション」を総合的に設計する戦略のことです。具体的には以下のような構成になります。
|
要素 |
内容例 |
|---|---|
|
ターゲット市場 |
どの市場・顧客層を狙うか |
|
提供価値 |
どんなニーズにどう応えるか(バリュープロポジション) |
|
販売チャネル |
オンライン/オフライン/代理店/直販など |
|
プロモーション |
広告、SNS、営業手法、展示会など |
|
KPI設計 |
目標達成に向けた具体的な数値指標 |
GTM戦略は、単なる「売り方」ではなく、事業全体の筋道を描くものです。特に新規市場への進出では、従来と異なるチャネルやパートナーが必要になる場合も多いため、柔軟かつ戦略的な設計が重要となります。
正しい順序と整理が、成果につながる市場開拓の第一歩
市場開拓においては、「やってみてから考える」のではなく、「考え抜いてから行動に移す」ことが成功の近道です。今回紹介した3つのステップ(市場調査・ターゲット設定、カスタマージャーニー設計、GTM戦略構築)を通じて、自社に最適な道筋を描くことができます。
これらのステップは、決して一度限りのものではありません。市場の反応や競合の動向に応じて柔軟に見直すことで、進化し続ける市場でも安定的な成果を出すことが可能になります。
新規市場開拓の具体的なアプローチ方法

新しい市場に参入するには、理論だけでなく実行力が求められます。「どのチャネルを活用するか」「どのアプローチ手法が効果的か」といった実践的な選択が、結果を大きく左右します。
このセクションでは、「新規市場開拓の方法」として効果的な具体策を紹介します。オンラインとオフラインのチャネル戦略、手法ごとの特徴と比較、スモールスタートによるリスク軽減、競合との差別化ポイントの発見といった、現場で活用できるアプローチを体系的に解説します。
オンラインとオフラインのチャネル戦略
まず、新規市場へどのようにアプローチするかを決める上で、重要な選択肢となるのが「チャネル設計」です。チャネルとは、商品やサービスの情報・価値を顧客に届けるための手段です。
オンラインチャネルの例
-
自社サイト(SEO、コンテンツマーケティング)
-
SNS(Instagram、X、Facebookなど)
-
Web広告(Google広告、Meta広告など)
-
メールマーケティング
-
ウェビナー・オンラインイベント
オフラインチャネルの例
-
訪問営業
-
展示会・見本市
-
チラシ・DM配布
-
店頭プロモーション
-
地域限定キャンペーン
自社の業種や商材、ターゲットによって最適なチャネルは異なります。複数を組み合わせるマルチチャネル戦略が効果的なケースも多く見られます。
手法別比較|メリット・デメリットを理解しよう
以下は代表的な新規市場開拓手法を、特徴・利点・注意点という観点で整理した比較表です。
|
手法 |
特徴 |
メリット |
デメリット |
|---|---|---|---|
|
テレアポ |
電話による直接営業 |
即時反応が得られる |
拒否される心理的負担が大きい |
|
メール営業 |
リストへの一斉配信 |
少ない工数で広範囲にアプローチ可能 |
開封率・返信率が低い傾向がある |
|
Web広告 |
SNSや検索を使った広告出稿 |
短期でアクセスや認知を拡大できる |
広告費がかさみやすく継続的運用が必要 |
|
展示会出展 |
リアルでの商談・接点獲得 |
業界関係者に広くアプローチできる |
出展コストや人員負荷が大きい |
|
コンテンツSEO |
検索エンジンからの集客導線 |
中長期的に安定したリード獲得が可能 |
成果が出るまでに時間がかかる |
このように、どの手法も万能ではありません。目的・対象・社内リソースに応じて適切に選択・組み合わせることが重要です。
スモールスタート戦略でリスクを最小化
新規市場にいきなり全力投球するのはリスクが高く、費用対効果が不透明です。そこで有効なのが「スモールスタート」という考え方です。
スモールスタートとは?
スモールスタートとは、最小限のコストとリソースで施策を試し、市場の反応を確認しながら改善する手法です。以下のような方法があります。
-
限られた地域・業界での限定展開
-
トライアル商品・モニターキャンペーンの実施
-
初期フェーズはオンラインのみで完結させる
-
アウトバウンド営業を数社限定で実施し反応を見る
スモールスタートの目的は「失敗を最小限にとどめる」ことだけではありません。実際の市場の声を早期に収集し、改善サイクルを早く回すことで、結果として成功確率を高める戦略なのです。
競合との差別化ポイントを明確にする方法
「良い商品を作れば売れる」という時代はすでに終わっています。市場には似たような商品・サービスがあふれており、競合との明確な違い、すなわち差別化が不可欠です。
差別化をつくるポイント
-
独自の技術・素材・デザインを持っている
-
顧客が気づいていない課題を先回りして解決できる
-
サポートやアフターサービスに圧倒的な強みがある
-
地域密着・スピード対応など、顧客との距離が近い
これらを洗い出すには、3C分析というフレームワークの活用がおすすめです。
|
要素 |
内容 |
|---|---|
|
Customer |
顧客が求めているもの、潜在ニーズ |
|
Competitor |
競合企業が提供している価値、ポジショニング |
|
Company |
自社が提供できる価値、リソース、ブランド力 |
自社の「強み」と「顧客の期待」が交わるポイントこそが、差別化の核となります。この強みを訴求軸として展開することで、新規市場での印象付けと選ばれる理由が明確になります。
「やり方を選ぶ力」こそが成果を左右する武器になる
新規市場開拓では、「何をやるか」よりも「なぜそれを選ぶのか」「どう実行するか」が重要です。手法の特徴を理解し、段階的に取り組むことで、無理なく市場開拓を進めることができます。
今回紹介した内容は、いずれも中小企業やスタートアップでも実践可能な現実的手段です。自社の強みとリソースを踏まえ、最適なアプローチを組み立てていくことで、成果へとつながる確率は大きく高まります。
実践的なKPI設計と評価方法

「新規市場開拓の方法」を実行する際、多くの企業が見落としがちなのが“評価指標”の設計です。明確なKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定せずに施策を展開しても、成果が出ているのか否かが判断できず、改善の方向性も見いだせません。
このセクションでは、新規市場開拓におけるKPIの考え方、適切な指標の選定方法、そして継続的に成果を出すためのPDCAサイクルについて、初心者にもわかりやすく解説します。
KPI(重要業績評価指標)の設定ポイント
新規市場においては、売上などの最終成果だけを追っても意味がありません。顧客認知の獲得から商談化・受注まで、段階ごとに適切なKPIを設定することが重要です。
以下に、新規市場開拓における代表的なKPIを段階別にまとめました。
|
フェーズ |
KPIの例 |
目的 |
|---|---|---|
|
認知獲得 |
PV数、広告インプレッション数、SNSフォロワー数 |
顧客に気づいてもらう |
|
興味・検討段階 |
LPクリック率、資料請求数、セミナー参加数 |
見込み客との接点づくり |
|
商談・提案段階 |
問い合わせ件数、商談数、メール返信率 |
営業活動の活性化 |
|
成約・コンバージョン |
受注数、成約率、平均契約単価 |
実際の売上につながる成果 |
|
継続・紹介段階 |
リピート率、紹介件数、LTV(顧客生涯価値) |
長期的な関係性と事業安定化の測定 |
このように、フェーズに応じて「今どこを改善すべきか」が可視化され、施策の無駄打ちを減らすことができます。
KPIは“可視化できる行動目標”である
KPIは単なる目標数値ではなく、「チーム全員が共通認識として持てる行動の目印」です。設定する際は以下の条件を満たすようにしましょう。
-
具体的(Specific):曖昧な言葉ではなく明確な数値で
-
測定可能(Measurable):データで管理できる項目を
-
現実的(Achievable):自社のリソースで到達可能かどうか
-
期限付き(Time-bound):期限を定めて進捗管理する
この考え方は「SMARTの法則」とも呼ばれ、ビジネス目標の設計で広く使われています。
モニタリングと改善のためのPDCAサイクル
KPIを設定したら、それを一度きりで終わらせず、継続的にモニタリングし、改善する仕組みが必要です。ここで活用すべきなのが、PDCAサイクルです。
PDCAとは?
PDCAは次の4つのステップから構成されます。
|
項目 |
内容 |
|---|---|
|
P(Plan) |
計画を立てる(ターゲット・戦略・KPIの設定) |
|
D(Do) |
実行する(アプローチ・営業活動など) |
|
C(Check) |
評価する(KPIの進捗確認・成果分析) |
|
A(Act) |
改善する(成功要因の強化、失敗要因の修正) |
新規市場では、仮説が的外れなことも少なくありません。そのため、「まずやってみて、すぐに振り返り、修正する」ことが極めて重要です。
モニタリングをチームで共有する仕組みも必要
KPIやPDCAを個人の中だけで回していては、組織全体のスピードが落ちてしまいます。以下のような共有の工夫が効果的です。
-
KPIダッシュボードの作成(スプレッドシート/BIツール)
-
週次・月次の定例レビュー会議の実施
-
KPI進捗グラフを可視化して社内に掲示
これらを通じて、チーム内で「今どの地点にいて、何が足りないのか」を共通認識として持つことができます。
成果は「数値で管理」しなければ、改善できない
どれだけ優れた戦略やアプローチを持っていても、それを測定・分析・改善する仕組みがなければ成長は持続しません。新規市場開拓の成否を左右するのは、KPIの設計と、その後のモニタリング体制にかかっているといっても過言ではありません。
成果が出ない原因を“感覚”で判断するのではなく、数値という客観的なデータに基づいて次の一手を導くこと。これができる企業こそが、変化の激しい市場においても安定した成果を上げることができるのです。
新規市場開拓を支援する合同会社えいおうの戦略的アプローチ

新規市場開拓は、決して一朝一夕で成果が出る取り組みではありません。市場調査や戦略設計、実行と改善のサイクルを一貫して回していくためには、体系的な知識と現場感のある経験が必要です。特に中小企業においては、リソースやノウハウが限られているため、「誰と取り組むか」が成功の大きな鍵を握ります。
このセクションでは、「新規市場開拓の方法」における合同会社えいおうの支援内容と、なぜ同社が中小企業やスタートアップから高く評価されているのかを詳しく解説します。
合同会社えいおうとは|中小企業に特化した事業戦略コンサルティング
合同会社えいおうは、「中小企業が持続的に成長できるビジネスモデルを構築する」ことをミッションに掲げ、伴走型の事業戦略コンサルティングを提供しています。
特徴1:現場目線での実行支援
えいおうの支援は、いわゆる机上のアドバイスにとどまりません。クライアントの業界特性や課題を深く理解したうえで、以下のような実行支援までを一貫してサポートします。
-
市場調査・競合分析・ターゲット選定の支援
-
営業・マーケティング戦略の設計と実施
-
KPI設計とモニタリングの体制構築
-
社内体制(人材・業務プロセス)の整備
単なる戦略立案ではなく、成果が出るまで伴走する姿勢が、他社との最大の違いです。
特徴2:中小企業の課題に特化したノウハウ
えいおうは、スタートアップから年商10億円規模の企業まで、数多くの中小企業の支援実績があります。そのなかで蓄積されたノウハウは、「限られた人材・予算・時間」の中でも結果を出すために最適化されています。
|
支援領域 |
対応内容例 |
|---|---|
|
戦略立案 |
商品戦略、市場選定、販路構築計画の設計 |
|
集客・販促 |
Web広告運用、SEO支援、SNS戦略設計 |
|
顧客化・営業支援 |
リード育成、営業フロー構築、ツール整備 |
|
組織設計支援 |
社内の目標設計・役割明確化・会議体構築 |
支援可能な領域と実績例
合同会社えいおうの「新規市場開拓の方法」支援は、多岐にわたる分野・業種で導入され、具体的な成果に結びついている点が特徴です。以下に代表的な支援領域と実績例を紹介します。
■ 新規事業開発支援
-
ニッチ市場向けのオリジナル製品開発(例:レジン家具ブランド「樹映」)
-
顧客インサイト調査からの用途提案・ブランド設計
■ 販路拡大・越境EC支援
-
地方の食品ブランドにおける、SNSとオンライン広告を活用した新販路獲得
-
アジア向け越境EC立ち上げ支援(翻訳・決済・物流設計)
■ リユース事業構築・拡大支援
-
アウトドア用品専門の中古買取・再販ECの立ち上げ(SUNDAY MOUNTAIN REUSE)
-
中古市場分析とユーザー導線設計
■ 店舗ビジネスのDX支援
-
地方小売店における来店データの分析と販促施策の可視化
-
デジタル会員証・ポイントシステムの設計
このように、「新規市場の選定」から「商品開発」「集客」「営業」「改善」までを一気通貫でサポートできる体制が整っており、クライアントごとにカスタマイズされた支援内容が高く評価されています。
結果を出すためには、「頼れる戦略パートナー」と進めるべき理由
新規市場開拓は、成功すれば大きな飛躍につながる一方で、誤った戦略や実行の失敗によってコストと時間だけが失われる危険もあります。とりわけ中小企業にとっては、その一度の挑戦が経営全体に与えるインパクトが大きいのが現実です。
だからこそ、外部の支援を受けるなら、単なるアドバイスにとどまらず、「ともに考え、ともに動き、成果に責任を持つ」パートナーを選ぶべきです。
合同会社えいおうは、クライアントの“戦略参謀”としてだけでなく、“実行部隊”としても寄り添い続ける存在。単発の成果ではなく、中長期的な事業成長を見据えた支援体制で、新規市場開拓の成功を強力に後押しします。
成功事例から学ぶ新規市場開拓のリアル
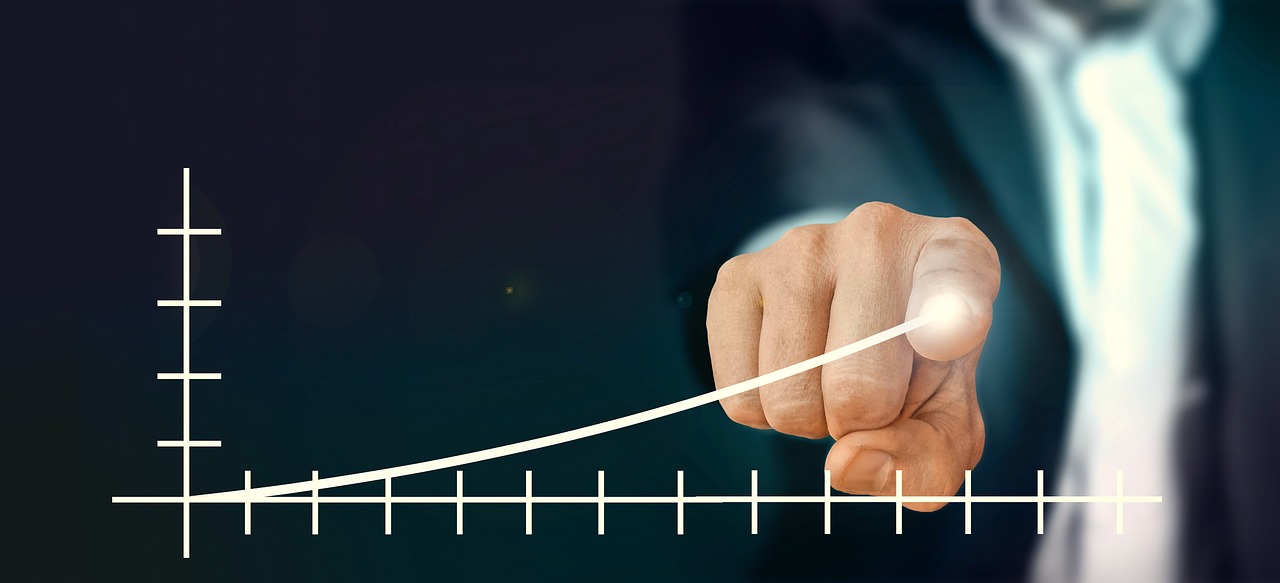
新規市場開拓は、理論や戦略だけでは語りきれない、現場での実行力と柔軟な対応力が試される領域です。「新規市場開拓の方法」は知っていても、実際に行動に移し、成果を上げられる企業はごく一部に限られます。
このセクションでは、実際に新規市場への進出を成功させた企業の事例を紹介しながら、どのようなアプローチで成果を上げたのかを分析します。中小企業・スタートアップが限られたリソースの中で結果を出すためのヒントが詰まっています。
国内成功事例の紹介(製造業/飲食業/SaaSなど)
事例①:地域の木工メーカーが全国へ展開「家具×EC」の成功
福井県の木工メーカーは、地域内の受注依存から脱却すべく、オーダーメイド家具のEC販売に挑戦。従来は展示会での営業が主流だったが、SEO対策とSNS活用によってニッチな顧客層を獲得。
|
ポイント |
内容 |
|---|---|
|
新規市場 |
全国の個人住宅ユーザー(BtoC) |
|
施策 |
インスタグラム活用/受注生産ECサイト構築/家具のカスタム提案 |
|
成果 |
月間平均受注20件以上、商談単価30万円超の高単価商品販売に成功 |
差別化の鍵は「暮らしに寄り添う提案型商品」であったこと。単に商品を売るのではなく、「選べる楽しさ」や「生活空間のストーリー性」を打ち出すことで、市場開拓に成功しました。
事例②:和菓子メーカーの若年層向けブランド立ち上げ
伝統的な和菓子を扱っていた企業が、20代~30代の若年層向けに「カラフル・ギフト向け」ブランドを新たに展開。商品は同じでも、ターゲットと訴求内容を大きく変えることで新規市場を獲得しました。
|
ポイント |
内容 |
|---|---|
|
新規市場 |
SNS感度の高いギフト需要層(主に女性) |
|
施策 |
パッケージリニューアル/インフルエンサー起用/ギフト特化EC展開 |
|
成果 |
バレンタイン・母の日などのギフト需要で売上前年比180%増加 |
既存顧客とまったく異なる層を狙うことで、新たな柱となる収益源を築きました。
事例③:SaaS企業がニッチ業種に特化して拡大
中小企業向けSaaSを提供する企業が、特定の業種(例:ビルメンテナンス業界)に特化して機能を絞り込んだことで、市場の信頼を獲得。「あえて狭く深く攻める戦略」で成功しました。
|
ポイント |
内容 |
|---|---|
|
新規市場 |
特定業界に特化した業務管理ニーズ |
|
施策 |
ヒアリングを重ねて業務にフィットする機能設計/業界特化セミナー開催 |
|
成果 |
顧客継続率95%以上、1社あたりLTVが2倍以上に向上 |
業界内での口コミや展示会出展によって、信頼のドミノが起きた点が成功要因となりました。
海外市場開拓事例(越境EC/現地パートナー)
事例④:地方食品メーカーが越境ECでアジア進出
日本酒や海産物などの地域資源を扱う企業が、アジア圏(台湾・シンガポール)への越境ECを開始。言語・決済・物流といった壁はあるものの、現地の輸入業者や翻訳パートナーとの連携でスムーズな展開を実現。
|
ポイント |
内容 |
|---|---|
|
新規市場 |
日本食人気の高い中華圏 |
|
施策 |
多言語EC構築/輸入業者との提携/SNS広告運用 |
|
成果 |
月間注文数200件以上、現地小売店との取引開始にも成功 |
キーワードは「現地ニーズを深く理解する」こと。日本人向けのままではなく、現地向けに最適化したパッケージや説明文が成約率アップにつながりました。
事例⑤:アパレルブランドがインスタ経由で欧州進出
小規模なアパレルブランドが、Instagramでのコーディネート投稿をきっかけにヨーロッパで話題に。海外向け発送体制を整え、D2C(Direct to Consumer)モデルで展開。
|
ポイント |
内容 |
|---|---|
|
新規市場 |
欧州のミニマルファッション市場 |
|
施策 |
Instagramマーケティング/多言語対応LP/越境発送体制構築 |
|
成果 |
欧州からの月間注文が売上の40%以上を占めるまでに成長 |
国内市場が頭打ちになるなか、海外のファン層を獲得できたことが事業継続のカギとなりました。
成功の背後には「戦略×現場力」がある
紹介した事例からわかるように、新規市場開拓は「奇抜なアイデア」ではなく、市場理解・顧客分析・価値提供の明確化といった、戦略と実行の積み重ねによって成果が生まれています。
特に中小企業の場合、派手な予算がなくても成功できる方法は存在します。
-
既存商品でもターゲットを変えるだけで新市場になる
-
SNSやWebを使ってニッチ層とつながることができる
-
少人数でも、現場の声を大切にすれば改良と改善が進む
「やってみたら意外と反応が良かった」という事例は多く、それを再現可能なモデルに昇華できるかが勝負です。次章では、新規市場開拓を進める際に陥りやすい失敗パターンと、その回避法について解説していきます。
新規市場開拓の注意点とよくある失敗パターン
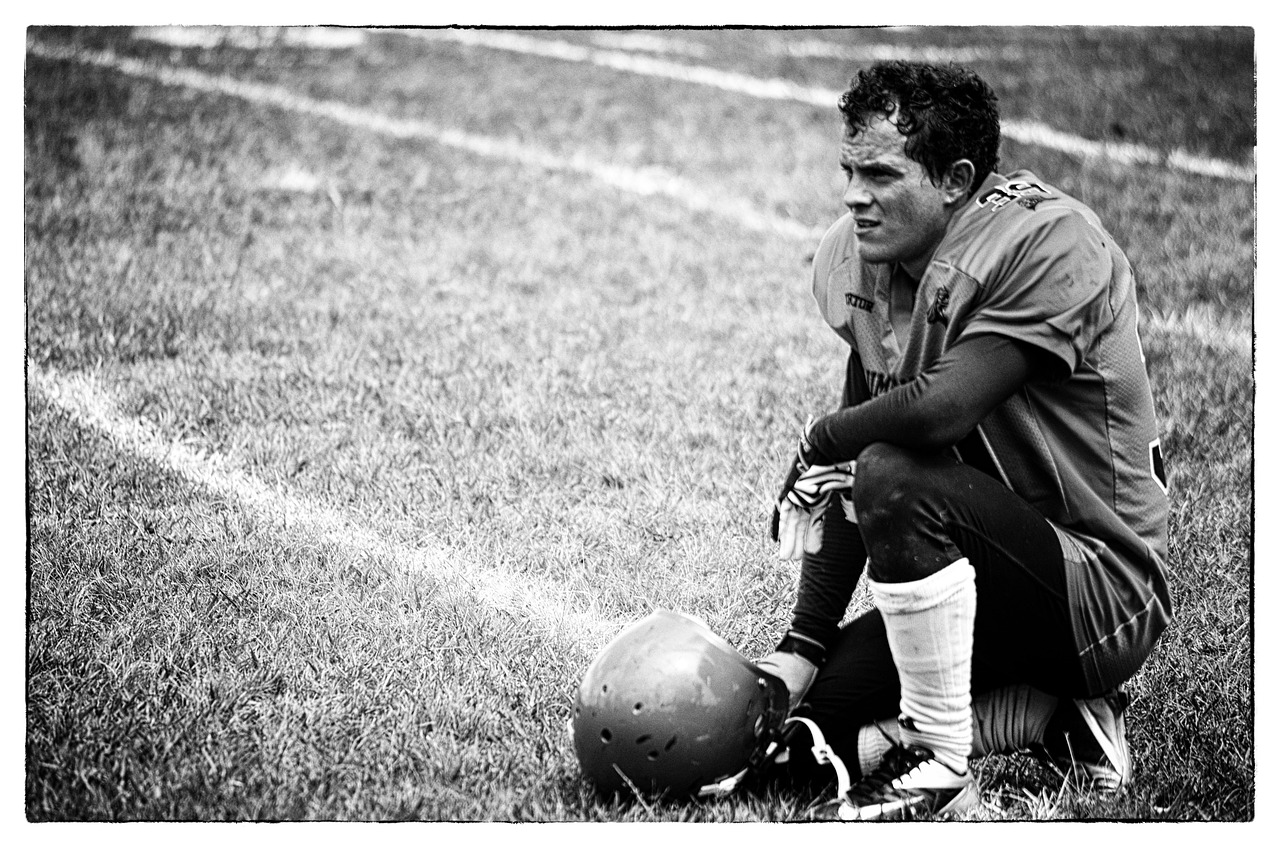
「新規市場開拓の方法」を実行に移す際、どんなに入念に準備をしていても、想定外の壁に直面することは珍しくありません。むしろ、新しいことに取り組むからこそ、失敗はつきものといえます。
しかし、よくある失敗パターンやリスク要因を事前に理解し、対策を講じることで、ダメージを最小限に抑えることは可能です。
このセクションでは、新規市場開拓における代表的な失敗事例と注意点、そして、撤退判断やリスク管理のポイントについて、具体的に解説します。
ありがちな失敗事例とその原因分析
新規市場開拓の失敗には、いくつかの共通パターンがあります。以下に代表的なものを整理しました。
|
失敗パターン |
主な原因 |
|---|---|
|
市場ニーズとの不一致 |
顧客ニーズや市場動向を十分に調査せず、製品やサービスが求められていなかった |
|
競合との差別化が不明確 |
他社と似たような商品・価格設定で、選ばれる理由がなかった |
|
社内体制が整っていなかった |
開拓に必要な人材や予算が確保できず、継続的なアプローチができなかった |
|
仮説検証をせずにいきなり全力投球した |
小さく試すことなく一気に資金投入し、結果的に大きな損失を出した |
|
成果指標(KPI)が設定されていなかった |
目標や評価基準が曖昧で、改善すべき点が分からなかった |
これらの失敗は、決して特殊なケースではなく、多くの企業が陥りがちなものばかりです。逆に言えば、このような落とし穴を事前に把握しておくことが、市場開拓の成功率を高める第一歩となります。
リスクマネジメントと撤退判断の視点
新しい市場に挑戦する以上、リスクは避けられません。しかし、それを“制御できるリスク”に変えることは可能です。特に重要なのは、撤退判断を含めた戦略的なリスクマネジメントです。
■ リスクマネジメントの具体策
-
スモールスタートで検証する
→ 小規模テストによって仮説の正確性を確かめる
-
複数のシナリオを立てる
→ 楽観・中立・悲観など、複数の結果を想定して計画を立てる
-
KPIによる進捗管理を徹底する
→ データに基づいて判断すれば感情に左右されない
-
撤退基準をあらかじめ設定する
→ 「この条件を満たさなければ撤退」と明文化することで迷いをなくす
■ 撤退は“失敗”ではなく“経営判断”
多くの企業が撤退を“敗北”と捉えがちですが、実際には「撤退=リソース再配分」という戦略的判断です。事前に撤退条件を決めておけば、感情的な判断に流されず、健全な事業判断が可能になります。
以下に撤退判断の基準例を挙げます。
|
項目 |
判断基準例 |
|---|---|
|
費用対効果 |
投資額に対して一定期間内に回収できる見込みがない |
|
顧客獲得コスト(CPA) |
想定以上に高く、継続的なマーケティングが困難 |
|
営業効率 |
商談化率が低く、営業活動の工数対効果が悪い |
|
組織的負担 |
他部門に負荷がかかり、既存事業に悪影響が出ている |
内部体制とコミュニケーション不足も失敗要因に
新市場開拓では「外」に目を向けがちですが、「社内の体制や連携不足」によって失敗するケースも少なくありません。
-
戦略の意図が現場に伝わっていない
-
営業とマーケティングが連携していない
-
リソース配分が曖昧で優先順位がブレている
このような状態では、せっかく立てた計画も、現場でうまく実行されません。全社的な共通認識と役割分担、そして継続的なフィードバック体制が成功の鍵となります。
「成功するための撤退戦略」を持つ企業が勝つ
新規市場開拓においては、「どんなときに進み、どんなときに引くか」を決めておくことが、企業を守る最大のリスクマネジメントになります。実は、“撤退できる力”こそが、挑戦する企業の強さの証明とも言えるのです。
綿密な戦略設計やアプローチ手法の選定と同じくらい、「やらない判断」「見直す判断」も重要です。これらを冷静に行える企業だけが、真に持続可能な市場開拓を実現できます。
実行に移すためのチェックリストとアクションプラン

「新規市場開拓の方法」について、戦略立案から実行、検証までの流れを学んでも、実際に行動に移せなければ成果にはつながりません。重要なのは、これまでの整理をもとに、自社に合ったプランを明確にし、一つひとつ着実に進めていくことです。
このセクションでは、すぐに活用できる事前準備チェックリストと、具体的なアクションプラン例、そして現場で使えるテンプレートツールを紹介します。社内の計画立案やチーム共有にもそのまま活用できます。
新規市場開拓の事前準備チェックリスト
まずは「準備が整っているかどうか」を可視化するためのチェックリストを使って、現状を確認しましょう。
|
項目 |
チェック内容 |
チェック済み |
|---|---|---|
|
市場調査 |
市場規模、成長性、競合状況を調査済み |
□ |
|
ターゲット設定 |
ペルソナや購買行動の仮説を具体化している |
□ |
|
バリュープロポジションの明確化 |
競合と差別化できる独自の提供価値が言語化できている |
□ |
|
販売チャネルの選定 |
自社に適したチャネルを整理し、優先順位を決めている |
□ |
|
KPIの設計 |
成果を定量的に測る指標(例:商談数、受注率)を設定している |
□ |
|
社内体制と予算の確認 |
開拓に必要な人材と予算の見通しが立っている |
□ |
|
リスクと撤退基準の定義 |
判断基準を明確にし、継続/撤退の基準が決まっている |
□ |
チェックが複数空白の場合、まだ準備段階にある可能性が高いため、慎重にステップを進めましょう。
すぐに活用できるアクションプラン例
新規市場開拓に必要な施策を、1〜3ヶ月・3〜6ヶ月・6ヶ月以降と段階ごとに整理すると、無理のない進行が可能です。
|
期間 |
主なアクション内容 |
|---|---|
|
1〜3ヶ月 |
市場調査、ターゲット設定、GTM戦略設計、プロトタイプ作成、小規模施策のテスト |
|
3〜6ヶ月 |
テスト結果の分析、改善策の実施、営業活動の強化、広告・コンテンツ運用の本格始動 |
|
6ヶ月以降 |
成果KPIの継続的な追跡、リピート・紹介の仕組み化、新たな市場への横展開の検討 |
特に初期3ヶ月は、仮説検証と改善のサイクルを早く回すことが成功へのカギとなります。
実行を支援するテンプレートツール一覧
実務に役立つ「新規市場開拓の方法」関連テンプレートを以下にまとめました。社内の企画書や会議資料、日々の実行管理などに活用できます。
|
テンプレート名 |
活用内容 |
|---|---|
|
ペルソナ設定シート |
ターゲット顧客の行動・価値観を明確化 |
|
カスタマージャーニーマップ |
顧客接点ごとの情報提供・施策を整理 |
|
GTM戦略フレーム(9マスシート) |
商品・チャネル・販促の整合性を視覚化 |
|
KPI設計ワークシート |
指標の設定・管理と改善の見える化 |
|
施策進捗ガントチャート |
各施策の進行状況と担当者の可視化 |
|
PDCAレポートテンプレート |
施策ごとの評価と改善策を記録・共有 |
これらのツールを活用すれば、社内のコミュニケーションコストを減らしながら、確実にプロジェクトを前進させることができます。
「やってみる前に整えておく」ことが成功を左右する
新規市場開拓の失敗は、多くの場合、「戦略そのもの」よりも「準備不足」によって起こります。つまり、やるべきことが明確になっておらず、チームで共有できていない状態が最大のリスクなのです。
チェックリストやテンプレートを活用することで、自社の現状を見える化し、足りない部分を把握しながら施策を組み立てることができます。行動する前に、まず整える。これこそが、無駄なコストや手戻りを減らし、成功に近づく最も確実な方法です。
よくある質問(FAQ)
新規市場開拓を検討・実行する中で、誰もが一度はぶつかる疑問や不安があります。このセクションでは、「新規市場開拓の方法」に関するよくある質問とその回答をまとめました。
中小企業の経営者、マーケティング担当者、新規事業部門の方など、さまざまな立場で市場開拓に取り組もうとしている方に向けた実践的な内容です。
Q. 小規模企業でも新規市場開拓は可能ですか?
A. はい、むしろ小規模企業こそ柔軟に動ける強みがあります。
大企業のような潤沢な予算や人員がなくても、スモールスタート戦略やニッチ市場への集中、オンラインチャネルの活用などによって、小規模でも着実な成果を上げることは可能です。むしろ、小回りの効く体制を武器に、変化に対応しやすいのが中小企業の強みです。
Q. 新規市場開拓と販路拡大の違いは何ですか?
A. 「販路拡大」は既存市場の中で販売チャネルを増やすこと、「新規市場開拓」は新しい顧客層や市場を開拓することです。
たとえば、「今まで東京でしか販売していなかった商品を大阪でも売り始める」のは販路拡大。一方、「これまで企業向けにしか販売していなかった製品を一般消費者にも提供する」のは新規市場開拓です。
戦略・リスク・リターンの規模感が異なるため、目的に応じた使い分けが必要です。
Q. オンラインだけで市場開拓を進めることはできますか?
A. はい、特に初期段階ではオンライン中心の施策で十分に成果を出せます。
Web広告、SNS、オウンドメディア、SEO、メールマーケティング、ウェビナーなどを駆使することで、認知獲得から商談獲得までを非対面で完結させることが可能です。特にBtoBでもBtoCでも、オンラインファーストの顧客行動が主流になっている今、デジタルチャネルを起点に市場開拓を行う企業が増えています。
Q. 初めて市場開拓に挑戦します。何から始めればいいですか?
A. まずは市場調査とターゲット設定から始めましょう。
「誰に売るのか」が定まらないまま施策に取りかかっても、失敗のリスクが高くなります。まずは次の2点を整理してください。
-
どの市場・業界・地域にニーズがありそうか(市場調査)
-
どんな人(企業)に、どんな価値を届けたいか(ターゲティング)
そのうえで、小規模な施策(SNS広告、モニター配布、メール営業など)を通じて仮説検証を進めるのがおすすめです。
Q. 市場開拓支援のコンサルティングに依頼するメリットは?
A. 成功までの「最短ルート」が見つかりやすくなります。
社内にノウハウがない場合、自社だけでの取り組みは時間もコストも多くかかる可能性があります。一方で、外部の専門家と一緒に取り組むことで、戦略設計・実行・改善のサイクルを効率よく回せるというメリットがあります。
特に合同会社えいおうのように「実行支援」まで行うパートナーであれば、現場レベルでの実装や調整にも対応してくれるため、成果につながりやすくなります。
Q. 新規市場開拓にはどれくらいの期間がかかりますか?
A. 最初の成果が見えるまでに、通常3〜6ヶ月程度が目安です。
ただしこれは業種・商品・市場規模などによって異なります。特にBtoBでは、顧客との信頼構築や検討期間が長くなるため、中長期の視点が必要です。
一方で、スモールスタートやテストマーケティングによって初期の反応を早期に把握できれば、本格展開までの時間を大幅に短縮することも可能です。
疑問を「行動のきっかけ」に変えることが成功への第一歩
新規市場開拓は不確実性が高い取り組みですが、だからこそ小さな疑問や不安をそのままにせず、一つひとつクリアにして前に進むことが大切です。
今回のFAQで紹介した内容は、実際に現場でよく聞かれる質問ばかりです。疑問は「止まる理由」ではなく、「次の行動を明確にするためのヒント」と捉え、前向きに活用してください。
未知の市場を「成果の市場」へ変える実践戦略

新規市場開拓は、単なる「新しい場所で売る」という作業ではありません。それは、これまで出会えなかった顧客に出会い、新しい価値を届け、自社の可能性を広げる“事業の進化”です。
特に中小企業にとって、「今ある商品・サービスの価値を、違うターゲットにどう伝えるか」は、経営の持続性を左右するほどの重要テーマです。そして、その挑戦は決して大企業だけのものではありません。
ここまでの内容で、「新規市場開拓の方法」に必要な要素と手順をひと通り整理してきました。最後に、その本質と、成果につなげるための実践的な視点を改めて共有します。
成果が出る企業に共通する3つの視点
1. 顧客視点に立ち続ける姿勢
自社が売りたいものではなく、「顧客が欲しがっている価値とは何か?」を起点に考え抜く姿勢が最も重要です。ターゲットを明確にし、行動や感情に寄り添うカスタマージャーニーを描けた企業ほど、提供価値の伝え方も自然と洗練されていきます。
2. 小さく試し、素早く改善する柔軟さ
完璧な戦略や施策はありません。だからこそ、スモールスタートで仮説検証を重ね、KPIを元に冷静に見直す姿勢が必要です。スピーディにPDCAを回しながら軌道修正できる企業は、最短ルートで成果に近づいていきます。
3. 社内を巻き込む共創のチーム設計
新市場開拓はマーケティング部門だけの仕事ではありません。営業、商品企画、経営層が一体となって動くことで、「売れる」仕組みが初めて生まれます。社内で同じビジョンを共有し、進捗を見える化する工夫が結果に直結します。
実行力を引き出すフレームと伴走支援を活用しよう
本記事では、市場調査・ターゲット設定・GTM戦略・チャネル設計・差別化・KPI・PDCA・撤退判断など、体系的なアプローチ方法を紹介しました。これらはすべて、「未知の市場」を「成果の市場」に変えるための“戦略と行動の道しるべ”です。
もし、自社だけで進めることに不安を感じているなら、伴走型で支援する専門家との連携も一つの選択肢です。たとえば、合同会社えいおうのように、「計画→実行→改善」を実務レベルで支えるパートナーがいれば、スピードも成果も大きく変わります。
今こそ、新しい市場へ一歩を踏み出す時
変化の激しい時代だからこそ、現状維持が最も危険な選択になります。
「失敗したらどうしよう」ではなく、「挑戦しなければ何も始まらない」という思考が、これからの時代に必要とされる企業像です。
市場は待ってくれません。動いた者だけが、新しい可能性に出会うことができます。
今、自社の強みを見つめ直し、顧客と市場を深く理解し、一歩を踏み出す時です。
“新規市場開拓”という挑戦が、やがて“持続可能な成果”へとつながる未来を、あなたの手でつくっていきましょう。














