経営を続けていると、売上の伸び悩みや人材不足、資金繰り、新規事業の停滞、さらにはDXの遅れなど、さまざまな経営課題に直面するものです。こうした課題を前にして、次のような悩みを抱えている経営者や担当者は少なくありません。
-
売上や利益率を改善したいが、どこから手を付けるべきか分からない
-
採用や人材育成に苦労しており、組織の成長が止まっている
-
新規事業やマーケティングを強化したいが、自社にノウハウがない
-
DXやIT活用の必要性を感じつつも、具体的な導入方法が見えない
-
補助金や助成金を利用したいが、手続きが複雑で申請に踏み切れない
本記事では、こうした経営課題を効果的に解決するための「コンサルティング活用」について詳しく解説します。経営課題の定義や解決の基本ステップ、コンサルティング導入のメリットと注意点、具体的な進め方、補助金・助成金の活用法、さらに合同会社えいおうが提供する事業戦略コンサルティング・マーケティングコンサルティングの特徴まで幅広く紹介します。
読み終えるころには、自社の経営課題を整理し、原因を分析し、解決に向けた行動計画を描けるようになるはずです。また、外部の専門家を活用するかどうかの判断材料を得ることができ、具体的に「次に何をすべきか」を明確にできるでしょう。経営課題を先送りせず、持続的な成長に向けて一歩を踏み出すための指針としてご活用ください。
弊社は事業戦略のコンサルティングサービスを展開しております。
- 事業を拡大したいが、どうすれば良いか分からない。
- 広告費が利益を圧迫している。
- 競合にシェアを奪われて売り上げが伸び悩んでいる。
- 新しく事業を始めるが、将来性が見えない。
等のお悩みをお持ちの企業様にご利用いただいているコンサルティングサービスです。
事業戦略に関するコンサルティングサービスではありますが、ITの導入、DX化、およびそれに伴う補助金申請のサポート等をトータルで行なっております。
目次
- 1 経営課題を解決へ導くコンサルティングの意義
- 2 経営課題とは何か?定義とよくある課題
- 3 経営課題解決のための基本ステップ
- 4 経営課題解決コンサルティングのメリットと注意点
- 5 経営課題を解決するコンサルティングの種類
- 6 経営課題解決コンサルティングの進め方と導入プロセス
- 7 補助金・助成金を活用した経営課題解決コンサルティング
- 8 合同会社えいおうの事業戦略コンサルティング
- 9 合同会社えいおうのマーケティングコンサルティング
- 10 経営課題解決を支えるコンサルティング手法とスキル
- 11 成果物とKPIで見る経営課題解決コンサルティングの効果
- 12 経営課題解決コンサルティングの導入事例
- 13 今すぐ実践できる経営課題解決の3ステップ
- 14 未来を描き、経営課題を共に解決するパートナーとして
- 15 合同会社えいおうの事業戦略コンサルティング
経営課題を解決へ導くコンサルティングの意義

売上の伸び悩み、人材不足、資金繰り、DXの遅れ――中小企業の現場では、複数の経営課題が同時多発的に起こることが珍しくありません。課題とは「あるべき姿」と現状のギャップを埋めるために設定されるテーマのことです。まずは課題を定義し、原因を特定し、打ち手を設計して実行・検証する一連のプロセスが欠かせません。
本記事は「経営課題 解決 コンサルティング」を検討している方に向け、基礎から実務までを体系化。外部の専門家を活用する意義や、伴走型の実行支援まで視野に入れたアプローチを、初心者にもわかりやすい言葉で解説していきます。定義やステップは一般的なフレームに依拠しつつ(課題定義→原因分析→施策立案→KPI設定→実行・評価)、幅広い論点を網羅し、実用的に役立つ構成としました。
この記事の目的と想定読者
本記事の目的は、経営課題の“見える化”から、優先順位づけ、解決策の設計、実行・定着までの道筋を提示することです。想定読者は以下の通りです。
-
事業の停滞要因をつかみきれず、どこから手を付けるべきか迷っている経営者・経営幹部
-
マーケティングや人事、IT・DXなど分野横断の課題を、外部の視点で整理したい管理職
-
助言型だけでなく、伴走型コンサルティングによる実行支援を検討している担当者
用語が出てきた際には、その都度わかりやすい補足を付け、初学者でも迷わないよう配慮しています。
用語の整理:経営課題・問題・コンサルティングの違い
経営課題とは、ミッション・ビジョンや業績目標と現状の差を埋めるために設定するテーマを指します。例えば「利益率の改善」「人材定着」「新規事業の立ち上げ」などです。
問題とは、日々の業務で顕在化する不具合や阻害要因であり、課題よりも具体的で短期的な性質を持ちます。
コンサルティングとは、第三者の専門家が課題の特定から打ち手の設計、実行支援までを行うサービスの総称です。フレームワーク(SWOT、3C、4P、PESTなど)を使って構造化し、KPI(重要業績評価指標)で効果を測定するのが基本です。
経営課題と「問題」の違い
-
経営課題=戦略目標とのギャップを埋めるテーマ(中長期の視点)
-
問題=日常業務の阻害要因(短期の視点)
両者を混同すると、場当たり的な対応に終始してしまい、根本的な改革につながりません。まず“あるべき姿”を定義し、逆算して課題を設定することが重要です。
経営課題の可視化とギャップ思考
“現状”と“あるべき姿”の差を測るには、財務・顧客・内部プロセス・学習成長など多面的な指標が有効です。客観的なデータを集め、仮説を立て、検証する循環を回すことで、組織全体で共通認識を持つことができます。
検索ユーザーの主な悩みと背景
検索上位で頻出する関連テーマには、売上低迷、人材不足、資金繰り、コスト削減、後継者不足、デジタル化の遅れといった課題が多く挙げられています。IT活用や評価制度の見直しなど具体的な処方が示されることもありますが、まずは経営計画やフレームワークでの整理、そして外部専門家への相談が推奨される傾向があります。
背景としては、属人的な営業やマーケティング、ノウハウの社内蓄積不足、市場変化への対応遅れといった構造的な要因が存在します。そのため、原因分析から解決策の比較、KPI設計、実行・検証までを一連の流れで取り組むことが欠かせません。
この記事の活用方法
本記事は以下の流れで構成されています。
-
経営課題の定義と基本ステップ
-
コンサルティングを活用するメリットと注意点
-
事業戦略コンサルティングとマーケティングコンサルティングの紹介
-
導入プロセスや補助金・助成金の活用方法
-
成果物とKPIで効果を見える化する方法
読み終えることで、自社の経営課題を整理し、原因と解決策を説明できるようになり、KPI設計や実行計画を作成できるようになることを目指します。
関連キーワードの整理
頻出する関連語を領域別にまとめると、次のようになります。
|
領域 |
関連キーワード(例) |
補足 |
|---|---|---|
|
戦略・事業 |
事業戦略、新規事業、競争優位、事業承継、M&A |
ビジョンと収益モデルの整合性、選択と集中 |
|
マーケティング |
集客、顧客獲得、LTV、CVR、ブランディング、SEO |
データドリブンの施策設計、コンテンツと広告の最適化 |
|
人・組織 |
人材不足、採用、育成、評価制度、定着率 |
評価と育成の仕組み化、属人化の解消 |
|
財務・資金 |
資金繰り、収益性、コスト削減、補助金、助成金 |
投資回収の見通し、制度活用の可否 |
|
IT・DX |
業務可視化、生産性、クラウド、AI、情報共有 |
システムの全体設計と段階導入 |
合同会社えいおうの提供価値
助言型コンサルティングは、診断や提案に重きを置き、社内実行の力が比較的高い企業に適しています。一方で伴走型コンサルティングは、ロードマップ作成からKPI運用、会議設計、施策実装までを支援するスタイルであり、中小企業にとって有効です。
外部コンサルティングを活用するメリットとしては「第三者視点」「知見の移植」「実行スピードの加速」が挙げられます。ただし、費用や社内の理解不足、依存リスクといった注意点も存在するため、導入前に慎重に検討する必要があります。
申し込み前に確認したいポイント
-
目的の明確化:到達したいゴールと指標を言語化できているか
-
役割分担:社内と外部支援の境界を明確にできているか
-
実行体制:データ提供や意思決定スピード、担当者配置が可能か
-
制度活用:補助金・助成金の活用が必要か、その適否を判断できているか
経営課題とは何か?定義とよくある課題

経営課題とは、企業が中長期的に成長し続けるために解決すべきテーマを指します。単なる日常業務上の問題とは異なり、企業の「あるべき姿」と現状の間に存在するギャップを埋めるために設定されます。例えば「売上を拡大して利益率を改善する」「優秀な人材を採用し定着させる」「新しい市場に参入する」などが経営課題にあたります。これらは経営戦略や組織運営全体に関わるため、解決には包括的なアプローチが必要です。
経営課題を理解することは、戦略の方向性を明確にし、資源を効果的に配分するための出発点となります。ここでは、初心者の方にもわかりやすく、代表的な経営課題の種類と背景について解説します。
経営課題の基本的な定義
経営課題は「将来の目標達成に必要だが、現時点では解決されていない状態」を意味します。経営理念や事業計画に基づいて設定されることが多く、企業規模や業種によって内容は異なります。例えば、大企業であればグローバル展開やM&A、新規事業創出などが課題になる一方、中小企業では資金繰りや人材確保などが大きなテーマになりがちです。
このとき重要なのは、課題を「漠然とした不安」ではなく、具体的に言語化することです。曖昧なまま放置すると、施策が場当たり的になり、効果的な改善につながりません。
中小企業が直面しやすい主要な課題
売上・利益の低迷
市場環境の変化や競合の激化により、売上や利益率が下がるケースは多く見られます。販売チャネルの多様化に対応できていなかったり、既存顧客への依存度が高すぎたりすることが原因となります。
人材不足・採用課題
少子高齢化の影響や働き方の多様化により、人材不足は中小企業にとって深刻な経営課題です。特に採用がうまくいかず、必要なスキルを持つ人材を確保できない場合、業務の効率化や事業拡大に大きな影響を与えます。
資金繰り・投資資金の確保
売上は伸びていても、運転資金や投資資金の確保に苦労する企業は少なくありません。金融機関からの借入条件、キャッシュフローの改善、補助金・助成金の活用などが課題解決の鍵になります。
新規事業開発や事業承継
既存事業の成長が鈍化するなかで、新規事業の立ち上げや事業承継は重要なテーマです。しかし新規事業にはリスクが伴い、また後継者不足は事業の存続自体を揺るがす深刻な問題につながります。
DX推進・IT活用
デジタル技術の活用は経営効率を高め、競争力を維持するために不可欠です。にもかかわらず、社内に専門知識が不足しているため導入が遅れ、結果として業務の非効率が放置されるケースが見られます。
経営課題解決のための基本ステップ

経営課題はただ認識するだけでは意味がなく、解決に向けて段階的に取り組むことが大切です。課題は複雑に絡み合うことが多く、明確なプロセスに沿って整理しなければ「問題への対処」で終わり、本質的な解決には至りません。ここでは、初心者にも理解しやすい形で、経営課題を解決するための基本ステップを解説します。
ステップ1:経営課題の特定と可視化
最初のステップは、経営課題を明確に洗い出すことです。売上の減少や離職率の上昇といった現象は「結果」に過ぎません。その背後にある「原因」を探るには、財務データ、顧客満足度調査、従業員アンケートなど、複数のデータを収集し、現状を客観的に可視化する必要があります。
ここで役立つのがフレームワークです。例えば、**SWOT分析(強み・弱み・機会・脅威)**を用いると、自社の強みや弱みを整理し、外部環境の変化を踏まえて課題を明確にできます。
ステップ2:原因分析と仮説立案
課題が特定できたら、次にその原因を深掘りします。売上が低迷している場合でも、原因は「商品力不足」「営業体制の弱さ」「マーケティング施策の不十分さ」など複数考えられます。
このとき有効なのがロジックツリーです。原因を「なぜ?」と掘り下げて分解し、仮説を立てることで、根本的な要因を特定しやすくなります。仮説を立てる際にはデータと現場の声の両方を組み合わせることが重要です。
ステップ3:解決策の立案と選択肢比較
原因が特定できれば、複数の解決策を検討します。例えば「人材不足」であれば、採用活動の強化、教育研修の充実、外部人材の活用などが候補に挙がります。
ここで大切なのは、選択肢を複数出したうえで、実現可能性と効果の大きさを軸に比較することです。すぐに実行できる「短期施策」と、中長期的に効果をもたらす「戦略的施策」をバランスよく組み合わせると、安定した成果につながります。
ステップ4:実行計画の策定とKPI設計
解決策が決まったら、実行計画を具体的に設計します。ここでは「誰が」「いつまでに」「何をするのか」を明確にし、社内で共有することが不可欠です。
同時に、成果を測るための**KPI(重要業績評価指標)**を設定します。売上高や利益率といった最終的な数値だけでなく、「問い合わせ件数」「商談化率」「従業員定着率」など、プロセスを測定できる指標を選ぶことで、改善の進捗を細かく把握できます。
ステップ5:実行支援と効果検証
最後のステップは実行と検証です。計画は立てただけでは意味がありません。現場で実行し、その効果を定期的に検証しながら、必要に応じて改善していきます。
ここで重要なのが**PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)**です。計画(Plan)を実行(Do)し、成果を検証(Check)、改善策を行動に移す(Act)。このサイクルを継続的に回すことで、組織は確実に改善と成長を積み重ねることができます。
POINT
経営課題は一度の取り組みで完全に解決できるものではなく、常に変化する市場環境や組織の状況に応じて見直す必要があります。明確なステップに従って取り組むことで、行き当たりばったりの対処ではなく、持続的な成長につながる「課題解決の仕組み」を企業内に根付かせることができます。
経営課題解決コンサルティングのメリットと注意点

経営課題の解決に向けてコンサルティングを導入することは、多くの企業にとって有効な手段です。しかし「コンサルを入れればすべて解決する」と考えるのは危険です。メリットとデメリットを理解し、導入前に注意点を押さえておくことで、投資対効果を高めることができます。ここでは、初心者にもわかりやすく、導入時に知っておくべきポイントを整理します。
経営コンサルティングを導入するメリット
外部の客観的な視点を得られる
経営者や社内のメンバーは、日常業務に追われているうちに「当たり前の前提」に縛られてしまうことがあります。コンサルタントは第三者として客観的に現状を分析し、これまで見落としていた課題や改善点を明らかにします。
専門的な知識とフレームワークを活用できる
コンサルタントは戦略立案やマーケティング、人材マネジメント、DX推進など、特定分野における知識やノウハウを持っています。例えばSWOT分析や3C分析といったフレームワークを用いることで、複雑な課題を体系的に整理できます。社内に蓄積が少ない分野でも、専門知識を短期間で取り入れることが可能になります。
実行支援によるスピード感のある改善
助言にとどまらず、実際に施策の実行を伴走して支援する「伴走型コンサルティング」であれば、施策を机上で終わらせず実行段階まで落とし込めます。これにより、課題解決のスピードが早まり、成果を得やすくなります。
リスクの可視化と対応策の提示
経営判断には必ずリスクが伴います。新規事業の立ち上げ、M&A、マーケティング投資など、大きな意思決定を行う際に、外部の専門家がリスクの可能性を示し、代替案や緩和策を提案してくれるのは大きな価値です。
経営コンサルティング導入時の注意点・デメリット
費用が発生する
コンサルティングには当然ながら費用がかかります。特に中小企業の場合、コスト負担は無視できない要素です。費用に見合う成果を得るためには、目的や期待するアウトプットを事前に明確にしておく必要があります。
社内の理解と協力が不可欠
外部コンサルタントがどれだけ有益な提案をしても、実行主体は社内の人材です。現場が「外部から押し付けられた施策」と感じてしまえば、定着せずに形骸化してしまうリスクがあります。導入時には経営層だけでなく現場も巻き込み、共通認識を持つことが不可欠です。
短期的成果ばかりを追うリスク
「すぐに売上を上げたい」という短期的な要望に偏ると、中長期的な体質改善や持続的成長が犠牲になることがあります。コンサルタントに依存しすぎず、自社での内製化や仕組みづくりを並行して進めることが重要です。
経営課題を解決するコンサルティングの種類

経営課題を解決するコンサルティングと一口にいっても、そのスタイルや専門分野は多岐にわたります。どのタイプを選ぶかによって、得られる支援内容や成果の出方が大きく異なるため、自社の状況に合ったコンサルティングを見極めることが重要です。ここでは、代表的な種類を整理し、それぞれの特徴を初心者にもわかりやすく解説します。
助言型コンサルティング
助言型は、経営診断や分析を行い、課題の特定と解決策の提案を中心に行うスタイルです。戦略的な方向性や意思決定のための材料を提供するのが主な役割であり、実行自体は社内に委ねられます。
-
メリット:専門家の知見を低コストで得られる、短期間で現状把握できる
-
デメリット:実行フェーズは自社任せとなるため、実行力やリソースが不足している企業には向かない
自社にある程度の人材や体制が整っている場合に有効です。
伴走型コンサルティング
伴走型は、課題の特定や提案にとどまらず、実行段階までコンサルタントが一緒に取り組むスタイルです。計画の立案から施策実行、効果検証までを一貫して支援するため、現場にノウハウが蓄積されやすく、定着度も高まります。
-
メリット:成果が実行段階までつながりやすい、社内メンバーの成長につながる
-
デメリット:期間が長期化しやすく、費用が比較的高額になる
人材不足やノウハウ不足に悩む中小企業にとっては特に効果的です。
分野別のコンサルティング種類
戦略コンサルティング
中長期的な事業戦略や競争優位の構築を支援します。市場環境や競合分析をもとに、新規事業の立案やM&A戦略などを検討するのが特徴です。
マーケティングコンサルティング
集客や顧客獲得、ブランディング、デジタルマーケティングなどに強みを持ちます。LTV(顧客生涯価値)やCVR(コンバージョン率)といった指標を改善するための施策を立案し、実行を支援します。
IT・DXコンサルティング
業務の効率化や生産性向上のために、システム導入やデータ活用を提案します。AIやクラウドの活用など、最新のテクノロジーを取り入れる支援が中心です。
人事・組織コンサルティング
採用戦略、教育・研修制度、評価制度の設計など、人材に関する課題に対応します。離職率の改善や組織文化の変革にも有効です。
財務・資金調達コンサルティング
資金繰りやコスト削減、補助金・助成金の活用、資金調達戦略などをサポートします。財務基盤を強化し、成長投資を可能にすることが狙いです。
経営課題解決コンサルティングの進め方と導入プロセス

コンサルティングを導入する際、多くの企業が不安に感じるのは「具体的にどのような流れで進むのか」という点です。契約から実行までの道筋を把握していないと、期待値とのズレが生じたり、社内の準備不足で成果が出にくくなったりします。ここでは、経営課題解決コンサルティングの導入プロセスを段階ごとに整理し、初心者にもわかりやすく解説します。
契約からスタートまでの流れ
コンサルティングは、いきなり施策の実行に移るのではなく、まずは「現状把握」から始まります。
-
初回ヒアリング
経営者や経営幹部に対して、企業の現状や課題感をヒアリングします。売上や利益といった定量データだけでなく、組織の雰囲気や意思決定の流れといった定性的な情報も重要です。
-
経営診断と現状分析
ヒアリング内容や財務データをもとに、課題を可視化します。ここで使われる代表的な手法が、財務諸表分析やSWOT分析、3C分析などです。
-
課題抽出と優先度付け
複数の課題が洗い出されるため、それぞれの重要度や緊急度を整理し、優先順位をつけます。ここでの選択が、後の解決プロセスの方向性を大きく左右します。
実行支援のプロセス
課題と解決策が明確になったら、実行フェーズに移ります。
-
解決策の導入
マーケティング戦略の見直し、人事制度の改善、ITシステムの導入など、決定した施策を実際に動かします。
-
定期的なレビュー
月次や四半期ごとに成果を検証し、必要に応じて軌道修正を行います。これを「スプリント」「レビュー」と呼び、短いサイクルで検証を繰り返すことで、失敗を最小化できます。
-
社内への定着支援
施策を一度導入しただけでは成果は長続きしません。マニュアル作成や研修を通じて、社内メンバーが自走できるようにすることがポイントです。
自走化までの支援
最終的なゴールは、外部コンサルタントがいなくても自社で課題解決の仕組みを回せる状態になることです。
-
ノウハウの共有
コンサルタントが持つ知識やフレームワークを、社内に落とし込みます。具体的には、チェックリストや分析手順、意思決定プロセスをドキュメント化することが多いです。
-
内製化サポート
社内担当者を育成し、改善プロジェクトを自力で推進できるよう支援します。これにより、コンサルティング契約終了後も継続的に課題解決が可能となります。
補助金・助成金を活用した経営課題解決コンサルティング

中小企業が経営課題の解決に取り組む際、最大の壁となりやすいのが「資金面の制約」です。施策を実行するには投資が必要ですが、資金繰りに余裕がない企業では実行に踏み切れないケースも多く見られます。そこで有効に活用できるのが、国や自治体が提供する補助金・助成金制度です。これらを戦略的に取り入れることで、資金的な負担を軽減しながら課題解決を進めることが可能になります。
補助金・助成金を活用するメリット
補助金・助成金を活用することには、次のような利点があります。
-
投資リスクを抑えられる
新規事業やシステム導入、マーケティング強化などの施策は初期費用が大きくなりがちです。補助金があることで、資金リスクを軽減しながら挑戦できます。
-
取り組みの幅が広がる
資金的な制約で先送りしていた施策にも取り組めるようになります。特にデジタル化や生産性向上に関する制度は充実しているため、DX推進や業務効率化に役立ちます。
-
信用力の向上
補助金の採択には審査があります。その審査を通過することで、事業計画の妥当性が外部から認められるため、金融機関からの評価向上や追加融資の後押しにもつながります。
採択されやすい分野と対象例
補助金・助成金は幅広い分野で提供されていますが、特に採択されやすい傾向があるのは次の領域です。
-
DX・デジタル化:ITツール導入、クラウド活用、AIやデータ分析の導入など
-
新規事業・イノベーション:新製品開発、サービス展開、販路拡大
-
海外展開:輸出促進、海外展示会出展、現地法人設立支援
-
人材確保・育成:人材採用の支援、教育研修費用の助成
このように、国の経済政策や社会課題に合致するテーマは採択率が高まる傾向にあります。
コンサルティングによる補助金・助成金活用支援
補助金制度は有効ですが、申請には専門的な知識や手続きが必要であり、慣れていない企業にとっては大きな負担になります。そこで、経営課題解決コンサルティングの一環として補助金・助成金活用をサポートすることに大きな価値があります。
-
制度の選定
数多くの補助金・助成金の中から、自社の課題解決に直結するものを選定します。
-
申請書作成支援
採択されるためには、事業計画を論理的かつ具体的に示す必要があります。コンサルタントは、審査で評価されやすい計画書作成をサポートします。
-
採択後の実行・報告支援
補助金は採択されて終わりではなく、実際に事業を遂行し、報告義務を果たす必要があります。コンサルタントが伴走することで、実行段階での不安や手間を軽減できます。
合同会社えいおうの事業戦略コンサルティング

経営課題を解決するうえで最も重要なのは、短期的な問題対応に終始するのではなく、企業の未来を見据えた「事業戦略」を描くことです。合同会社えいおうの事業戦略コンサルティングは、経営ビジョンと市場環境を結びつけ、中長期的な成長を実現するための支援を提供しています。単なるアドバイスではなく、経営層と共に未来の方向性を設計し、実行まで伴走する点が特徴です。
提供する主な支援領域
中長期ビジョンの策定
経営理念や企業の存在意義を再確認しながら、5年後・10年後を見据えた中長期ビジョンを策定します。ここでは、市場規模や競合動向を踏まえつつ「どの分野で勝ち残るか」を明確化し、経営の羅針盤をつくります。
市場分析・競合分析
3C分析(自社・顧客・競合)やPEST分析(政治・経済・社会・技術の外部要因)などのフレームワークを駆使して、市場構造を客観的に把握します。特に中小企業では、自社の強みを活かせるニッチ領域を見つけることが成功の鍵となります。
新規事業開発支援
既存事業だけに依存すると、市場の変化に対応できなくなるリスクがあります。合同会社えいおうは、新規事業のアイデア発掘からビジネスモデル設計、試験導入までをサポートし、成長の新たな柱を構築するお手伝いをします。
M&A戦略・事業承継の支援
後継者不足や市場縮小への対応策として、M&Aや事業承継は重要な選択肢です。買収や統合に伴うシナジー効果の検討、スムーズな承継に向けた計画立案を行い、企業の継続性を高めます。
他社にはない強み
合同会社えいおうの事業戦略コンサルティングは、大手コンサルティング会社とは異なり、中小企業の実情に寄り添った柔軟な支援が特徴です。
-
実行力重視:提案だけでなく、実際の施策の推進や現場の課題解決にまで踏み込みます。
-
中小企業特化のノウハウ:経営資源が限られる企業向けに、効率的かつ現実的な戦略設計を行います。
-
伴走型支援:社内メンバーと二人三脚で取り組み、ノウハウを共有しながら内製化を促します。
合同会社えいおうのマーケティングコンサルティング

経営課題の多くは「顧客の獲得」や「売上拡大」と密接に関わっています。いくら優れた商品やサービスを持っていても、ターゲットに届かなければ成果は得られません。合同会社えいおうのマーケティングコンサルティングは、経営戦略と連動したマーケティング施策を設計し、実行から効果検証まで一貫して支援することで、企業の持続的な成長を後押しします。
提供する主な支援領域
顧客ターゲティング・市場ポジショニング
自社の商品やサービスが「誰のためのものか」を明確化し、競合との差別化を図ります。ペルソナ(理想的な顧客像)の設定や市場調査を行い、訴求ポイントを可視化することで、無駄のない集客を実現します。
デジタルマーケティング戦略
現代の集客はデジタル抜きでは語れません。SEO対策、リスティング広告、SNS運用などを組み合わせ、オンライン上での認知拡大と見込み顧客獲得を支援します。特にSEOでは、検索ボリュームや関連キーワードを分析し、コンテンツマーケティングを通じて自然検索流入を増やすことに力を入れています。
コンテンツマーケティング・ブランド戦略
企業が発信する情報そのものがブランドの価値を形成します。記事やホワイトペーパー、動画など多様なコンテンツを活用し、顧客に「選ばれる理由」を提供します。これにより短期的な成果だけでなく、中長期的なブランド力向上につながります。
効果検証と改善
施策は打ちっぱなしにせず、必ず成果を数値で検証します。CVR(コンバージョン率)、LTV(顧客生涯価値)、CPA(顧客獲得単価)などの指標をもとに、改善サイクルを回すことでマーケティングの精度を高めていきます。
合同会社えいおうの強み
大手コンサルティング会社では「戦略立案」に偏りがちですが、合同会社えいおうは中小企業の実情に合わせ、実行と検証までを一貫して伴走する点が特徴です。
-
現場感覚を重視:机上の理論にとどまらず、具体的な施策を現場で試行・改善します。
-
費用対効果を最大化:限られた予算の中で最も効果を発揮する手法を選定し、無駄な投資を防ぎます。
-
成果の可視化:KPIを明確にし、数値で成果を測る仕組みを導入することで、納得感のある改善を実現します。
経営課題解決を支えるコンサルティング手法とスキル
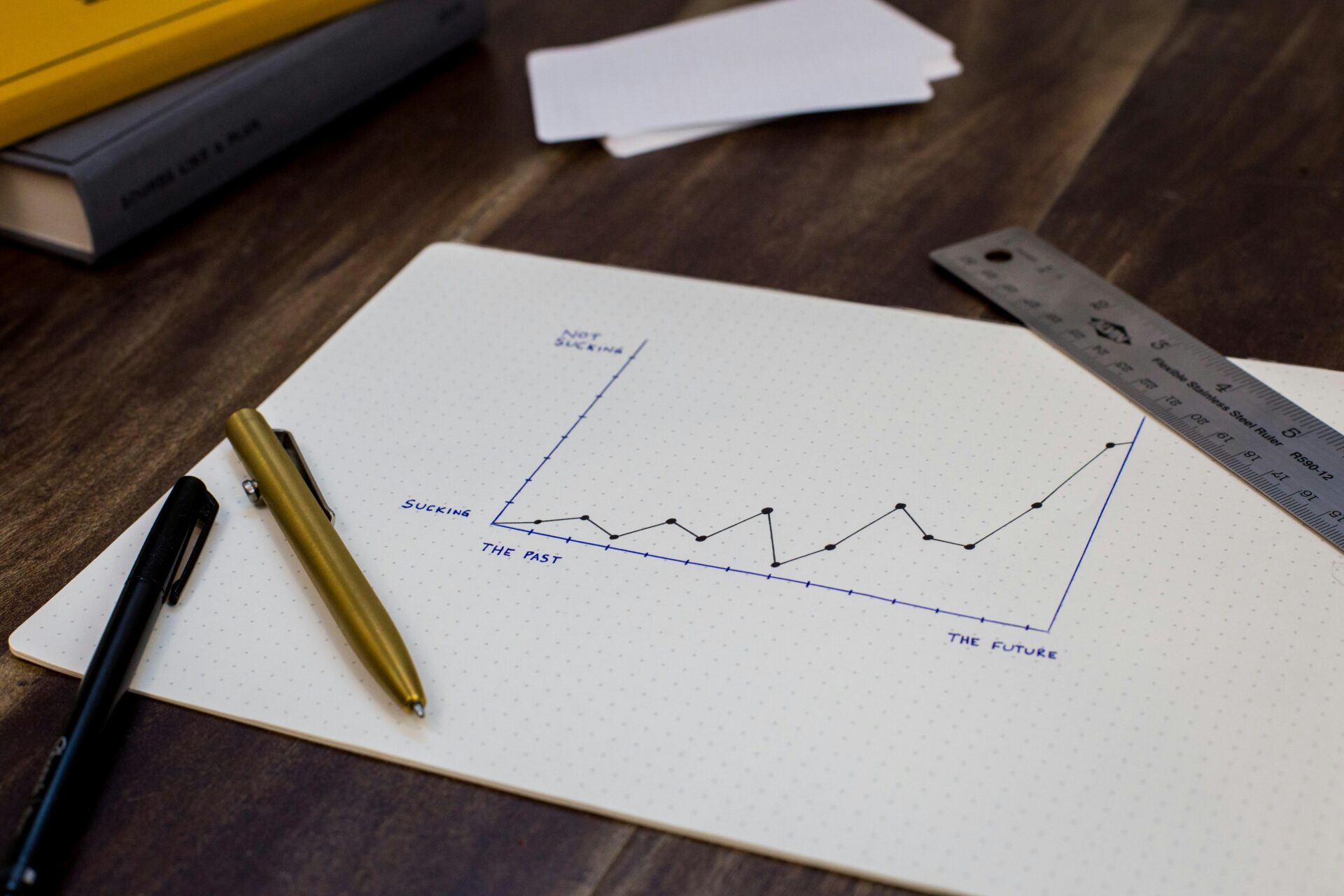
経営課題を効果的に解決するには、感覚や経験だけに頼るのではなく、体系的な手法と分析スキルを活用することが欠かせません。コンサルティングの現場では、経営の複雑な状況を整理し、原因を明確にし、具体的な解決策を導き出すために、さまざまなフレームワークやスキルが用いられています。ここでは、代表的な手法と必要なスキルを初心者にもわかりやすく解説します。
代表的な分析フレームワーク
SWOT分析
企業の「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」を整理する手法です。内部環境と外部環境を組み合わせて考えることで、自社がどの分野で競争優位を築けるかを明確化できます。
3C分析
3Cは「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の頭文字です。この3つの視点から市場環境を整理し、自社の立ち位置を把握するために使われます。顧客ニーズを見極め、競合との差別化を考える際に効果的です。
PEST分析
「政治(Politics)」「経済(Economy)」「社会(Society)」「技術(Technology)」の4つの外部環境要因を分析する手法です。法律改正や景気動向、社会トレンドやテクノロジーの進化といった外部要因を把握し、中長期の経営戦略に活かします。
4P分析
マーケティング分野でよく使われる手法で、「Product(製品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(販促)」の4つの視点から戦略を検討します。新規事業や商品開発の方向性を考えるときに有効です。
実務で活用するスキル
ロジックツリーによる課題分解
複雑な課題を「なぜ?」と掘り下げて分解し、階層的に整理する手法です。売上低迷の原因を「顧客数」「単価」「リピート率」などに分けて考えることで、根本原因を見つけやすくなります。
仮説検証とデータ分析
コンサルティングでは、まず仮説を立て、それをデータで検証するプロセスが重視されます。データに基づいた意思決定は、属人的な判断に比べて再現性が高く、納得感を得やすいのが特徴です。
KPI設計とPDCA運用
成果を数値で測定するためにはKPI(重要業績評価指標)の設定が不可欠です。例えば「新規顧客獲得数」「リピート購入率」「従業員定着率」などを設定し、PDCAサイクルを回すことで継続的な改善が可能になります。
成果物とKPIで見る経営課題解決コンサルティングの効果

経営課題解決コンサルティングの成果は、単なる提案資料や会議でのアドバイスだけではありません。具体的な「成果物」と「KPI(重要業績評価指標)」を通じて可視化されることで、社内メンバーが納得感を持ち、改善を継続しやすくなります。成果物は「形として残るアウトプット」、KPIは「進捗と成果を測る指標」として、それぞれ経営改善を支える重要な役割を果たします。
成果物の例
戦略レポート
現状分析と将来の方向性を示した戦略レポートは、経営層や従業員が同じ方向を向くための指針になります。これにより、組織全体で共通認識を持ち、意思決定のブレを防げます。
実行ロードマップ
「誰が・いつまでに・何をするのか」を具体的に示した行動計画です。短期・中期・長期に分けたステップを可視化することで、取り組みの優先順位やリソース配分を整理できます。
マニュアルや業務フロー設計
人材が入れ替わっても安定的に業務を回せるように、手順やルールを明文化します。属人化の解消や生産性向上につながる成果物です。
マーケティング施策(LPや広告設計など)
集客強化のために、実際に使えるマーケティングツールや広告プランを成果物として提供するケースもあります。形に残るアウトプットがあることで、施策を即座に実行可能です。
成果を可視化するKPI例
売上高・利益率
最も分かりやすい経営成果の指標であり、課題解決の最終的なゴールを測る物差しです。
顧客獲得数・リード数
マーケティング施策の効果を測定するうえで欠かせない指標です。広告やSEO、展示会など集客施策ごとにKPIを設定することで改善ポイントを特定できます。
コンバージョン率(CVR)
見込み顧客が実際の購入や契約に至った割合を示す指標です。マーケティング施策の質や販売プロセスの効率を測る目安になります。
従業員定着率
人材の定着は、組織課題の解決度合いを測る重要なKPIです。採用だけでなく育成・評価制度の改善が成果につながっているかを確認できます。
成果物とKPIを連動させる意義
成果物とKPIは、単独では十分な効果を発揮しません。例えば「ロードマップ」という成果物があっても、KPIで進捗を測らなければ、計画倒れになる恐れがあります。逆に、KPIだけを追いかけても、具体的な施策がなければ改善の手段が見えません。
そのため、コンサルティングでは成果物とKPIを連動させることが重視されます。施策を進めるための具体的なツールを成果物として提供し、それを定期的にKPIで評価・修正することで、経営課題解決の実効性が高まります。
経営課題解決コンサルティングの導入事例

経営課題解決コンサルティングの価値を理解するには、実際の導入事例を知ることが効果的です。ここでは中小企業が直面しやすい典型的な課題を取り上げ、どのようなプロセスで解決につながったのかを紹介します。実例をイメージすることで、自社に導入した場合の効果をより具体的に想像できるでしょう。
売上低迷からのV字回復事例
ある製造業の中小企業では、長年の取引先依存により新規顧客が増えず、売上が低迷していました。コンサルティング導入後は以下の流れで改善を進めました。
-
市場分析を通じて、未開拓だった新規顧客層を特定
-
マーケティング施策(WebサイトのSEO改善・展示会出展・営業資料刷新)を導入
-
KPIとして「新規問い合わせ件数」「商談化率」を設定し、月次で検証
結果として、新規顧客の獲得が加速し、売上が1年で前年比120%まで回復しました。依存リスクを下げつつ、新しい市場基盤を築くことができた事例です。
人材不足を解消し組織改革に成功した事例
地方のサービス業では、人材不足と高い離職率が深刻な経営課題でした。コンサルタントの伴走支援により、次の施策が行われました。
-
採用プロセスを見直し、ターゲット人材に合わせた採用チャネルを開拓
-
社内の評価制度と研修プログラムを整備し、定着率を改善
-
KPIとして「離職率」「従業員満足度調査スコア」を設定し、定点観測
結果として、離職率が1年で30%から15%に半減し、従業員が安心して働ける組織文化が形成されました。人材確保に苦しむ中小企業にとって参考になる事例といえます。
マーケティング戦略の見直しで顧客獲得が加速した事例
BtoBサービスを提供する企業では、既存顧客は安定していたものの、新規顧客獲得が停滞していました。コンサルティング支援を通じて、次の取り組みが行われました。
-
ペルソナを再設定し、ターゲット企業の明確化
-
コンテンツマーケティング(専門記事・ホワイトペーパー)の強化
-
デジタル広告とSEOを組み合わせ、見込み顧客へのリーチを拡大
-
KPIとして「リード獲得数」「WebサイトCVR」を設計
この結果、半年でリード獲得数が2倍に増加し、新規契約数も大幅に改善しました。戦略的なマーケティングが売上に直結した事例です。
今すぐ実践できる経営課題解決の3ステップ

コンサルティングを導入する前段階として、自社で簡単に取り組めることがあります。大規模な分析や高額な投資をしなくても、正しい手順で考えるだけで経営課題の整理が進み、方向性が見えやすくなります。ここでは、中小企業の経営者や担当者がすぐに実践できる3つのステップを紹介します。
ステップ1:自社の経営課題を洗い出し、3つ以内に絞り込む
まずは「現状における経営課題」を思いつく限り書き出します。売上、人材、資金、顧客満足度、IT活用などテーマは多岐にわたるでしょう。しかし列挙するだけでは優先順位がつかず、混乱を招きます。そこで重要なのが「3つ以内に絞る」ことです。
人は課題を同時に多数解決するのが難しいため、重点領域を明確にすることで限られた経営資源を集中投下できます。
ステップ2:課題に優先順位を付け、原因の仮説を立てる
絞り込んだ課題に対して「なぜこの状況が起きているのか」を考え、原因の仮説を立てます。例えば「売上低迷」が課題なら、原因は「新規顧客獲得不足」「既存顧客の離脱」「客単価の低下」などに分けられます。
このプロセスはロジックツリー(課題を枝分かれの図で分解する手法)を使うと整理しやすくなります。仮説を立てることで、解決の方向性を見極めやすくなり、無駄な対策を避けられます。
ステップ3:第三者の視点を取り入れ、初回相談で“見える化”する
最後に、自社内だけで完結させず、外部の視点を取り入れることが重要です。経営者自身や社内メンバーは、慣れや固定観念により課題を客観的に捉えにくくなります。そこで、経営コンサルタントの初回相談や無料診断サービスを利用し、現状を第三者の目で“見える化”することが効果的です。
外部からの意見を取り入れるだけで、課題の本質が明確になり、改善の優先度を誤るリスクが減ります。
未来を描き、経営課題を共に解決するパートナーとして

経営課題は、単に数値を改善するためのものではなく、企業の未来を形づくる大きなテーマです。売上の回復や人材定着、マーケティングの強化といった課題の背後には、「どんな企業でありたいか」「社会にどのような価値を提供するのか」といったビジョンが必ず存在します。課題解決はそのビジョンを実現するための手段であり、経営者や従業員が未来を描くためのプロセスでもあります。
合同会社えいおうは、単なるアドバイザーではなく、企業と共に歩む伴走型のパートナーであることを重視しています。外部から課題を指摘するだけではなく、現場に入り込み、実際に改善の一手を共に実行することで、成果を「机上の提案」に終わらせないのが強みです。
また、中小企業の経営資源は限られています。その限られた人材や資金をどのように活かすか、どの施策に集中すべきかを明確にすることこそがコンサルティングの価値です。経営者が抱える漠然とした不安や悩みを整理し、実行可能な戦略へと変換していく過程を、えいおうは全力で支援します。
企業が未来を描くためには、短期的な成果だけでなく、長期的に持続可能な経営基盤を築くことが欠かせません。そのために必要なのは「第三者の視点」「専門的な知見」「現場での実行力」を兼ね備えたパートナーです。
経営課題の解決はゴールではなく、新しい未来を切り拓くためのスタート地点です。合同会社えいおうは、経営者と同じ視点で未来を見据え、共に挑戦し続ける伴走者として、次の成長ステージへの道を切り開いていきます。
合同会社えいおうの事業戦略コンサルティング
合同会社えいおうでは、中小企業様向けに事業戦略設計のコンサルティングサービスを展開しております。
事業戦略コンサルティングでは、事業に関する経営戦略を支援するだけではなく、この記事でご紹介したようなIT導入、IT導入に関わる補助金の取得申請もサポートしております。
- 売上が停滞しており、次の成長戦略が見えない
- 市場環境の変化に適応できていない。
- ビジネスモデルの拡張、投資家対応、資金調達などに課題を感じている。
- 売上はあるが利益が少ない、キャッシュフローが回らない。
- どの市場に進出すべきか、どのようなビジネスモデルが適しているかがわからない。
- DXの必要性は感じているが、どのツールを導入すべきか判断できない。
- 海外展開の進め方、現地パートナーの探し方がわからない。
このようなお悩みを抱えている企業様に向け、事業戦略の設計により事業体質の改善を支援します。IT、およびITを活用するための補助金を利用して、費用対効果の高い事業成長を目指しましょう。
机上の空論ではなく、商品企画、集客施策、営業体制を含めた各分野に対してマーケティングの知識を持った実務レベルのサポートを致します。














