事業戦略コンサルティングに興味を持ったものの、いざ検索しても「何をしてくれるのか」「自社に必要なのか」が分からず戸惑っていませんか。多くの経営者や担当者が次のような悩みを抱えています。
-
売上が伸び悩んでいるが、原因が分からない
-
競合との差別化ができず、価格競争に巻き込まれている
-
社内にマーケティングやITの知識がなく、改善の方向性を見いだせない
-
外部の支援を受けたいが、具体的にどんな効果があるのか想像できない
こうした課題に対して、事業戦略コンサルティングは経営の方向性を整理し、利益を伸ばすための実践的な方法を提案してくれます。本記事では「事業戦略コンサルティングで企業はどう変わるのか」というテーマのもと、具体的な成功事例や実践プロセスを詳しく解説します。
内容は、事業戦略コンサルティングの基本的な役割から、マーケティングやIT導入の効果、組織のモチベーション向上、そして実際に成果を上げた企業の事例まで幅広くカバーしています。また、専門用語が出る場合は丁寧に解説しているので、初めての方でも安心して読み進められます。
弊社は事業戦略のコンサルティングサービスを展開しております。
- 事業を拡大したいが、どうすれば良いか分からない。
- 広告費が利益を圧迫している。
- 競合にシェアを奪われて売り上げが伸び悩んでいる。
- 新しく事業を始めるが、将来性が見えない。
等のお悩みをお持ちの企業様にご利用いただいているコンサルティングサービスです。
事業戦略に関するコンサルティングサービスではありますが、ITの導入、DX化、およびそれに伴う補助金申請のサポート等をトータルで行なっております。
目次
- 1 新規事業に挑戦する企業が直面する課題と背景
- 2 新規事業コンサルティングとは?基本を理解する
- 3 なぜ新規事業にはコンサルティングが必要なのか
- 4 新規事業を成功させるための分析フレームワーク
- 4.1 分析フレームワークの全体像(探索→設計→検証→拡張)
- 4.2 3C分析で市場・顧客・競合を立体的に把握する
- 4.3 SWOT/TOWSで強みと機会を結合し戦略へ落とし込む
- 4.4 PEST分析でマクロ環境の変化を先読みする
- 4.5 STPで狙う顧客を定義し、ポジショニングマップで勝ち筋を描く
- 4.6 4P/4Cでマーケティングミックスを設計する
- 4.7 JTBD(ジョブ理論)と顧客インサイトで「買う理由」を掘り起こす
- 4.8 価値提案キャンバスでバリュープロポジションを言語化する
- 4.9 ビジネスモデルキャンバスとユニットエコノミクスで収益性を設計する
- 4.10 MVP/PoCとPMF指標の設計で検証を高速化する
- 4.11 ノーススターKPIと実験設計で意思決定を明瞭化する
- 4.12 フレームワークの使い分けと落とし穴
- 4.13 合同会社えいおうの適用方針
- 5 新規事業コンサルティングの進行ステップ
- 6 新規事業コンサルティングの費用相場と契約形態
- 7 新規事業コンサルティング会社の選び方と注意点
- 8 合同会社えいおうの事業戦略コンサルティングの特徴
- 9 未来を共創するパートナーとしての第一歩
- 10 合同会社えいおうの事業戦略コンサルティング
新規事業に挑戦する企業が直面する課題と背景

新規事業コンサルティングを検討する企業の多くは、「なぜ進まないのか」「どこでつまずくのか」という課題に直面しています。実際、日本国内の調査では新規事業の成功率は2〜3割程度、累損解消まで至る企業はさらに少数とされており、その難易度は極めて高いことが分かります。背景には顧客ニーズの把握不足や社内リソースの限界、人材・ノウハウ不足など、複数の要因が重なっているのが現実です。ここでは、企業が抱える典型的な課題とその背景を整理し、事業戦略コンサルティングの視点で理解を深めていきます。
新規事業の失敗率の現実を直視する
新規事業の多くは、アイデア段階から事業化に至るまでに淘汰されます。特に累損を解消して黒字化できるのは全体の1割前後と言われており、思いついた企画の大多数が途中で停滞・撤退を余儀なくされているのが実情です。この背景には、十分な市場調査が行われていないまま開発を進めてしまうことや、顧客にとって本当に必要な価値を見極めきれていないことが挙げられます。
用語解説
-
MVP(Minimum Viable Product):最小限の機能を備え、短期間・低コストで市場の反応を確かめるプロトタイプ。
-
PoC(Proof of Concept):コンセプトが技術的・事業的に実現可能かどうかを検証する実証実験。
-
PMF(Product-Market Fit):製品やサービスが市場に適合し、顧客が継続的に利用する状態。
これらの概念を理解し、段階ごとに検証を行うことが成功率を高める第一歩となります。
よくある課題:ノウハウ不足・人材不足・アイデア停滞
新規事業を進めるうえで多くの企業が抱えるのは、ノウハウや人材の不足です。市場リサーチや顧客インサイトの抽出、競合分析、事業計画の立案などは専門的な知識を必要としますが、既存事業の延長で取り組む場合、経験値が足りず正しい手法を選べないことが多いのです。
さらに、社内でアイデアは出ても具体的に形にできず停滞するケースも少なくありません。ニーズがあると思っていた領域に実際の需要がなく、PoCの段階で失敗することもよくあります。また、推進リーダーや検証設計を担える人材がいないために、スピード感を持った実行ができず、競合に先を越されてしまうリスクもあります。
組織やガバナンスの壁も課題になる
特に大企業や歴史のある企業では、稟議や承認フローが複雑で、意思決定に時間がかかるという課題があります。新規事業はスピードと柔軟性が求められる領域であるにもかかわらず、既存の仕組みに縛られると検証サイクルを回せず、結果的に機会損失につながります。
また、社内合意形成が不十分なまま進めると、途中で反対意見が出て頓挫することもあります。これらは「制度設計の不足」「リスクに対する説明不足」「経営層との認識のずれ」といった要因に起因するものであり、組織文化やガバナンスを新規事業に適応させる工夫が求められます。
課題の整理と初期対応策の早見表
以下に、新規事業でよく見られる課題とその背景、初期対応の方向性をまとめます。
|
症状(よくある悩み) |
背景要因 |
初期対応策 |
関連キーワード |
|---|---|---|---|
|
顧客が振り向かない |
顧客課題の把握不足、仮説検証不足 |
リサーチ強化、MVPでの実ユーザー検証 |
顧客インサイト、仮説検証、競合分析 |
|
プロジェクトが遅い |
多層の承認、硬直的な稟議 |
検証範囲の最小化、パイロット実施 |
稟議、ガバナンス、ステージゲート |
|
検証設計ができない |
PoC/MVPの知識不足、人材の経験不足 |
テンプレート導入、KPIと終了条件の事前設定 |
MVP、PoC、KPI |
|
差別化できない |
競合分析不足、価値提案が曖昧 |
ポジショニング再設計、独自価値の明確化 |
価値提案、ポジショニング |
|
社内の合意形成が進まない |
データ不足、リスク説明の不十分さ |
定量データを用いた説得、ROIの提示 |
事業計画、ROI、エビデンス |
なぜ社内リソースだけでは限界があるのか
新規事業は不確実性が高く、既存事業の延長では通用しない領域です。社内だけで進めようとすると、以下のような限界に直面します。
-
既存事業の評価基準に引きずられ、リスクを取った挑戦ができない
-
検証設計の知識や経験が乏しく、学習コストが高くなる
-
デジタルマーケティングやSEO、広告運用、顧客開発など幅広い領域に一気通貫で対応できない
このような理由から、外部の新規事業コンサルティングを活用することで、MVP/PoCの設計や市場調査の知見を取り込み、検証スピードを高めることが可能になります。
合同会社えいおうが着目する「早期検証と合意形成」
合同会社えいおうでは、新規事業の立ち上げにおいて「早期の検証サイクル」と「経営層を含めた合意形成」を両立させることを重視しています。リサーチから仮説立案、MVP検証、データ分析、改善までを短期間で繰り返しながら、同時に社内での合意を得られるエビデンスを積み上げていきます。これにより、不確実性の高い新規事業においても、戦略と実行を両立させる体制を構築できるのです。
新規事業コンサルティングとは?基本を理解する

新規事業コンサルティングは、企業が未知の市場や新たなサービスに挑戦する際に必要となる「戦略立案から検証、実行まで」のプロセスを支援する専門的なサービスです。単なるアドバイスではなく、外部の視点と専門ノウハウを組み合わせて、不確実性を減らし、成功の確率を高めることを目的としています。ここでは、新規事業コンサルティングの定義や役割、具体的な支援内容、導入メリットについて整理していきます。
新規事業コンサルティングの定義と役割
新規事業コンサルティングとは、企業が新しいビジネスを立ち上げる際に直面する「市場選定」「事業計画」「仮説検証」「収益モデル設計」といった多くの課題に対し、外部の専門家が体系的にサポートを行うことを指します。
その役割は大きく分けて以下の通りです。
-
市場や顧客のリサーチを通じたニーズの把握
-
事業計画や戦略の立案による方向性の明確化
-
MVP(Minimum Viable Product)やPoC(Proof of Concept)を活用した仮説検証
-
Go-To-Market戦略(市場投入戦略)の設計と初期マーケティングの支援
-
KPI設計とROI評価による効果測定と改善提案
一般的な顧問契約や社内研修と異なり、新規事業コンサルティングは「実行まで伴走し、成果を出すための仕組みを構築する」点に特徴があります。
新規事業コンサルティングで提供される主な支援内容
新規事業コンサルティングの支援範囲は広く、調査から実行まで多岐にわたります。
市場調査と顧客インサイト分析
新規事業の第一歩は、市場規模や競合状況を正しく理解することです。顧客インタビューやアンケート調査、競合分析を行い、ターゲットセグメントとその課題を明確にします。
事業モデル設計と価値提案の策定
市場データをもとに、収益モデルや提供価値を設計します。バリュープロポジションを定義し、自社の強みを活かした差別化戦略を描くことが重要です。
MVP・PoCによる検証
仮説を机上で終わらせず、最小限の機能を持ったプロトタイプ(MVP)や実証実験(PoC)を通じて、市場からの反応を得るプロセスを設計・実行します。これにより、早い段階で方向性の修正が可能となります。
マーケティングとGo-To-Market戦略
テストマーケティングを通じて効果的なチャネルや訴求方法を見極めます。SEOや広告、オウンドメディアなどを活用し、顧客獲得とブランド構築を同時に進めます。
KPI設計とデータ分析
新規事業においては明確なKPI(重要業績評価指標)の設定が欠かせません。売上や顧客獲得単価だけでなく、LTV(顧客生涯価値)や継続率なども含めた指標を追跡し、改善に活かします。
新規事業コンサルティングを導入するメリット
新規事業コンサルティングを導入することで得られるメリットは多岐にわたります。
-
成功確率の向上:専門的なフレームワークや経験に基づいた検証が可能になる
-
スピードアップ:社内だけでは時間がかかる意思決定や検証を加速できる
-
外部知見の活用:他業界の成功事例や最新のノウハウを取り込める
-
リスク低減:失敗の兆候を早期に発見し、方向転換がしやすくなる
-
社内人材育成:伴走型支援を通じて、社内に新規事業開発の知見を蓄積できる
事業戦略コンサルティングとの関係性
新規事業コンサルティングは「事業戦略コンサルティング」の一部でもあります。特に合同会社えいおうが提供する事業戦略コンサルティングでは、単なる計画立案にとどまらず、SEOやデジタルマーケティングを組み合わせた「実行力ある戦略支援」を強みとしています。これは、戦略の策定と実行を切り離さず、成果に直結する形で支援するスタイルです。
なぜ新規事業にはコンサルティングが必要なのか

新規事業は、既存事業の延長では測れない“未知の変数”に満ちています。市場規模、顧客の受容性、収益モデルの成立条件、法規制やガバナンスなど、不確実性が高い要素が同時多発的に絡むため、偶然の成功に頼らない再現性ある進め方が不可欠です。新規事業コンサルティングは、仮説設計からMVP/PoCによる検証、Go-To-Market(GTM)とグロース、KPI設計、ROI評価までを一気通貫で設計し、意思決定の質と速度を底上げします。単なる助言ではなく“伴走型”で学習サイクルを高速化する点が、本質的な価値です。
新規事業の成功率を左右する要因
新規事業の成否は、
- 顧客インサイトの深さ
- 検証設計の巧拙
- 意思決定のスピード
- 組織の巻き込み力
に収れんします。社内に蓄積された成功パターンが通用しづらいのは、未知の顧客課題や競合構造に直面する“探索型の仕事”だからです。事業戦略コンサルティングは、探索(Discovery)と実行(Delivery)を切り分け、各フェーズの論点とKPIを明確化。ムダな投資を避けながら、最短距離でPMF(Product-Market Fit)を狙えるように導きます。
探索と実行を分けて考える(失敗コストの最小化)
-
探索では、顧客の課題仮説を立て、MVPやPoCで事実ベースの検証を積み重ねます。
-
実行では、仮説が妥当と判定された領域に絞ってGTMを設計し、チャネル別のCVRやLTV/CACをモニタリング。
この二段構えにより、開発先行で手戻りが増える“あるある”を抑止できます。
社外の専門知見を導入する重要性
新規事業コンサルティングが介在すると、以下の効果が同時に立ち上がります。
再現性の高い仮説検証プロセスを実装
リーンスタートアップ、デザイン思考、顧客開発の要素を組み合わせ、検証KPIと終了条件をあらかじめ合意。検証のやり直しを減らし、学習コストを抑えます。
競合・市場の地図を整備し、差別化を言語化
3C/PEST/4P・4C、ポジショニングマップ、ユニットエコノミクスで“勝てる条件”を明文化。価格・チャネル・メッセージの整合を取り、GTMの初速を高めます。
マーケとデータの一体設計
SEO・広告・コンテンツ運用と、イベント計測やコホート分析を同時に設計。ノーススターKPIと先行/遅行指標を揃え、投資判断(ROI)を透明化します。
客観的な第三者視点がもたらす効果
新規事業を鈍らせるのは、社内“常識”のバイアスと、稟議の多層構造です。第三者である新規事業コンサルティングは、意思決定の基準を定量化し、合意形成を短縮します。
的確な“やらない判断”ができる
KPIに基づく終了条件を先に決めておくことで、惰性の継続や過剰投資を回避。限られた予算と時間を勝ち筋に集中できます。
経営陣と現場の翻訳者として機能
経営が知りたい指標(ROI、回収期間、リスク)と、現場が追う指標(CVR、継続率、NPS)を一枚のダッシュボードに接続。議論が早まり、ピボットの判断も明瞭になります。
事業戦略コンサルティングと内製の違い
内製の強みはドメイン知と実装力。一方、新規事業では未知の検証ノウハウや横断的な成功知が鍵になります。事業戦略コンサルティングは、横ぐしで通せる設計図と評価軸を持ち込み、内製チームの手を止めずに学習速度を2倍化する設計を担います。
役割の切り分け例
-
内製:開発・CS・既存チャネル運用、ドメイン特有のナレッジ
-
コンサル:検証設計、フレームワーク選定、データ基盤、GTMテストの設計・評価
よくある反論とその解き方
「自社だけでできるのでは?」
内製のみだと、検証設計の“型”がないため学習コストが高止まりしがちです。伴走型で型を導入し、社内に移植することで、以後は自走可能になります。
「費用対効果が見えない」
投資判断はLTV/CAC、回収期間、到達率などで可視化します。小さく試し、伸びたところに張る“ステージゲート”で、費用対効果の不透明さを解消できます。
「現場が忙しくリソースがない」
プロトタイプやノーコードを用いたMVP運用、テスト設計のテンプレ化で、現場負担を抑えつつ学習サイクルを回せます。
新規事業コンサルティングが解決するギャップ
|
課題(ギャップ) |
期待効果 |
代表施策 |
|---|---|---|
|
顧客課題の解像度が低い |
価値仮説の明確化 |
定性/定量リサーチ、JTBD、ペルソナ、カスタマージャーニー |
|
検証方法が属人的 |
再現性の確立 |
検証KPI・終了条件、MVP/PoC設計、ABテスト |
|
差別化が弱い |
勝ち筋の特定 |
3C/PEST、ポジショニング、4P/4C、価格・チャネル戦略 |
|
意思決定が遅い |
稟議の短縮 |
ダッシュボード、ノーススターKPI、経営会議用の投資判定表 |
|
収益性が見えない |
投資判断の透明化 |
LTV/CAC、感度分析、ユニットエコノミクス、ROI管理 |
|
組織が動かない |
合意形成の促進 |
ステークホルダー別論点整理、リスク対策、ガバナンス整備 |
|
学習が蓄積しない |
ナレッジの資産化 |
検証ログ、プレイブック、継続的ディスカバリー体制 |
用語解説
-
MVP(Minimum Viable Product):価値仮説を検証するための最小機能プロダクト。短期間・低コストで学習するための手段。
-
PoC(Proof of Concept):技術・事業面での実現可能性を確かめる実証実験。大規模投資前の関門。
-
PMF(Product-Market Fit):製品が特定市場のニーズに適合した状態。継続率や紹介意向などで確認する。
-
GTM(Go-To-Market):市場投入の計画。ターゲット、メッセージ、チャネル、価格の整合を設計。
-
LTV/CAC:顧客生涯価値/獲得コスト。単月の獲得効率だけでなく、継続価値で投資判断するための指標。
-
ノーススターKPI:事業の長期成長を最もよく表す最重要指標。全体最適の基準点。
合同会社えいおうの視点
合同会社えいおうの事業戦略コンサルティングは、検証設計・GTM・計測基盤を同時に整える“伴走型”アプローチを重視します。社内に残るプレイブックとダッシュボードを納品価値と位置づけ、以後は自走できる体制づくりまでを支援対象とします。過度に開発へ踏み込みすぎず、しかし意思決定に必要な実データは確実に集める――そのバランスが、新規事業の成功確率を押し上げます。
新規事業を成功させるための分析フレームワーク

新規事業コンサルティングの核心は、「勘や経験」を再現性のあるプロセスに置き換えることにあります。市場調査から価値提案の言語化、MVP/PoCによる仮説検証、Go-To-Marketの運用設計まで、適切な分析フレームワークを段階的に適用することで、不確実性を段階的に削減。ここでは、新規事業を成功に導く代表的なフレームワーク群を、使う順番・出力物・判断基準とともに整理します。
分析フレームワークの全体像(探索→設計→検証→拡張)
新規事業は「探索(Discovery)→設計(Design)→検証(Validation)→拡張(Scale)」の4段階で考えると整流化できます。各段階で使う主要フレームワークと代表アウトプットを一覧化します。
|
段階 |
主な目的 |
主要フレームワーク |
代表アウトプット |
関連キーワード |
|---|---|---|---|---|
|
探索 |
顧客課題の把握と市場理解 |
3C、PEST、JTBD、ペルソナ |
市場地図、顧客インサイト、セグメント仮説 |
市場調査、競合分析、顧客インサイト |
|
設計 |
価値提案とモデル構築 |
SWOT/TOWS、価値提案キャンバス、STP、4P/4C、ポジショニングマップ |
バリュープロポジション、価格・チャネル戦略 |
事業戦略、差別化、マーケティング戦略 |
|
検証 |
仮説の実証と指標設計 |
MVP、PoC、A/Bテスト、実験計画、ノーススターKPI |
検証レポート、終了条件、PMF指標 |
仮説検証、CVR、KPI、PMF |
|
拡張 |
収益性と再現性の確立 |
ユニットエコノミクス、LTV/CAC、コホート分析 |
収益モデル、成長ドライバー、投資判断 |
ROI、回収期間、グロース設計 |
3C分析で市場・顧客・競合を立体的に把握する
3C(Customer/Competitor/Company)は、どの土俵で戦うかを定めるための基本枠組みです。
-
Customer(市場・顧客): 市場規模、成長率、購買要因、スイッチングコスト。ペルソナやカスタマージャーニーの素案づくりに直結。
-
Competitor(競合): 直接・間接競合の提供価値、価格帯、チャネル、強み/弱み。ベンチマークの選定に活用。
-
Company(自社): 強み・弱み、既存資産(チャネル、技術、ブランド)。活かせるアセットの見極め。
新規事業コンサルティングでは、3Cの出力を次のフレームワーク(STPやポジショニング)へ橋渡しします。
SWOT/TOWSで強みと機会を結合し戦略へ落とし込む
SWOTは内部(Strength/Weakness)と外部(Opportunity/Threat)を分けて棚卸しする枠組み。新規事業では、列挙して終わらせずTOWS(外部×内部の掛け合わせ)で具体的戦略に落とすのが要点です。
-
S×O: 強みを活かして機会を獲る攻勢策
-
W×O: 弱みを補強して機会を逃さない改善策
-
S×T: 強みで脅威を回避する防衛策
-
W×T: 撤退・縮小や提携でリスク最小化
この思考で、戦略仮説が行動仮説に変わります。
PEST分析でマクロ環境の変化を先読みする
PEST(Political/Economic/Social/Technological)は外部環境の変動要因を網羅する視点。規制や補助金、金利や為替、価値観の変化、生成AIやIoTなど技術トレンドが新規事業の“潮目”を決めます。短期の検証だけでなく、中期のシナリオ設計にも有効。
STPで狙う顧客を定義し、ポジショニングマップで勝ち筋を描く
-
Segmentation(細分化): ニーズや利用シーン、価格許容度、チャネル嗜好でセグメントを切る。
-
Targeting(狙い): 参入しやすく伸びしろの大きい層を選定。最初は狭く深く。
-
Positioning(位置づけ): 競合との相対比較で独自価値を明確化。
ポジショニングマップは、顧客が重要視する2軸(例:導入負担×効果、価格×品質)で自社と競合を可視化。訴求メッセージや価格戦略の根拠になります。
4P/4Cでマーケティングミックスを設計する
4P(Product/Price/Place/Promotion)は企業視点、4C(Customer Value/Cost/Convenience/Communication)は顧客視点。両者を対に設計するとブレが減ります。
-
Product×Customer Value: 機能ではなく解決価値を起点に要件を決める。
-
Price×Cost: 顧客の総保有コスト(導入・運用・乗り換え)まで視野に。
-
Place×Convenience: オン/オフの購買導線、サブスクやD2Cなどのチャネル設計。
-
Promotion×Communication: SEO、広告、PR、セールスの役割分担を明確化。
新規事業コンサルティングでは、このミックスをMVP検証に組み込み、CVRとCPAで効果を測定します。
JTBD(ジョブ理論)と顧客インサイトで「買う理由」を掘り起こす
JTBD(Jobs To Be Done)は「顧客が“片づけたい用事”の達成」を焦点に置く発想法。年齢や属性ではなく、進歩(Progress)に注目します。
-
ジョブ記述例: 「忙しい平日の夕方に、家族に栄養バランスの良い夕食を短時間で用意したい」
-
ペイン/ゲイン: 障害と得たい成果の明確化。
-
代替行動: 現在の代替(他製品・無消費)を把握してスイッチング戦略を設計。
この理解が、価値提案キャンバスやメッセージの核になります。
価値提案キャンバスでバリュープロポジションを言語化する
価値提案キャンバスは、顧客プロフィール(ジョブ・ペイン・ゲイン)と、自社の提供(製品・ペインリリーバー・ゲインクリエイター)のフィットを可視化。
-
良い価値提案の条件: 具体的、検証可能、代替より明確に優位、価格と整合。
-
アウトプット: 30秒で伝えられる“ベネフィット主語”のステートメント。
新規事業コンサルティングでは、この文面をそのままLPや営業資料の核に転用します。
ビジネスモデルキャンバスとユニットエコノミクスで収益性を設計する
ビジネスモデルキャンバスは9ブロック(顧客セグメント、提供価値、チャネル、関係性、収益の流れ、リソース、活動、パートナー、コスト構造)で全体設計を俯瞰。さらにユニットエコノミクスで単位経済性を検証します。
-
LTV/CAC: 顧客生涯価値(LTV)と獲得コスト(CAC)の比率。一般に>1が最低ライン、>3で健全といった目安が使われます。
-
回収期間: CACを平均粗利で回収するまでの期間。短いほど再投資が回りやすい。
-
感度分析: 価格・継続率・CPAがLTV/CACに与える影響を比較。
収益性の見通しが甘いとPMF到達後の拡張で詰まります。ここで詰め切る意義は大きい。
MVP/PoCとPMF指標の設計で検証を高速化する
MVP(最小実用製品)は最小の機能で市場の反応を測る試作品。PoC(概念実証)は技術・事業の実現可能性を見極める検証。
-
成功/終了条件: 事前にKPIしきい値を設定(例:CTR、CVR、継続率、紹介意向)。
-
学習ループ: 設計→測定→学習の短サイクル運用。
PMF(Product-Market Fit)に近づくほど、オーガニック継続やNPS、チャーン低下が観測されます。新規事業コンサルティングは、この指標設計と計測基盤の構築を同時に進めます。
ノーススターKPIと実験設計で意思決定を明瞭化する
組織が同じ方向を見るためにノーススターKPI(事業の本質的価値を最も端的に示す指標)を定義。加えて、先行指標(獲得、活性、継続のドライバー)と遅行指標(売上、LTV、利益)を連結します。A/Bテストや多変量テストは、仮説の良否を短期に判定する装置。投資判断のブレが減ります。
フレームワークの使い分けと落とし穴
-
列挙で止めない: SWOTや3Cは“ToDo化”して価値が出る。TOWSやSTPへ接続。
-
数値の粒度: 市場規模の桁が荒いと、価格戦略やLTV設計が不安定。一次情報を補う姿勢。
-
検証の先延ばし: 机上の設計に偏りやすい。MVP/PoCを早期に差し込む運用規律が重要。
-
指標の多すぎ問題: ノーススターKPIを中核に、先行/遅行の最小集合で運用。
合同会社えいおうの適用方針
合同会社えいおうの事業戦略コンサルティングでは、上記フレームワークを“つなげて使う”ことを重視します。3C→STP→価値提案→4P/4C→MVP→ユニットエコノミクスという直列運用に、JTBDとPESTを横串で差し込み、さらにノーススターKPIと計測基盤で意思決定を自動化。設計と検証が乖離しない“伴走型”の実務運用で、PMF到達までの学習速度を引き上げます。
新規事業コンサルティングの進行ステップ
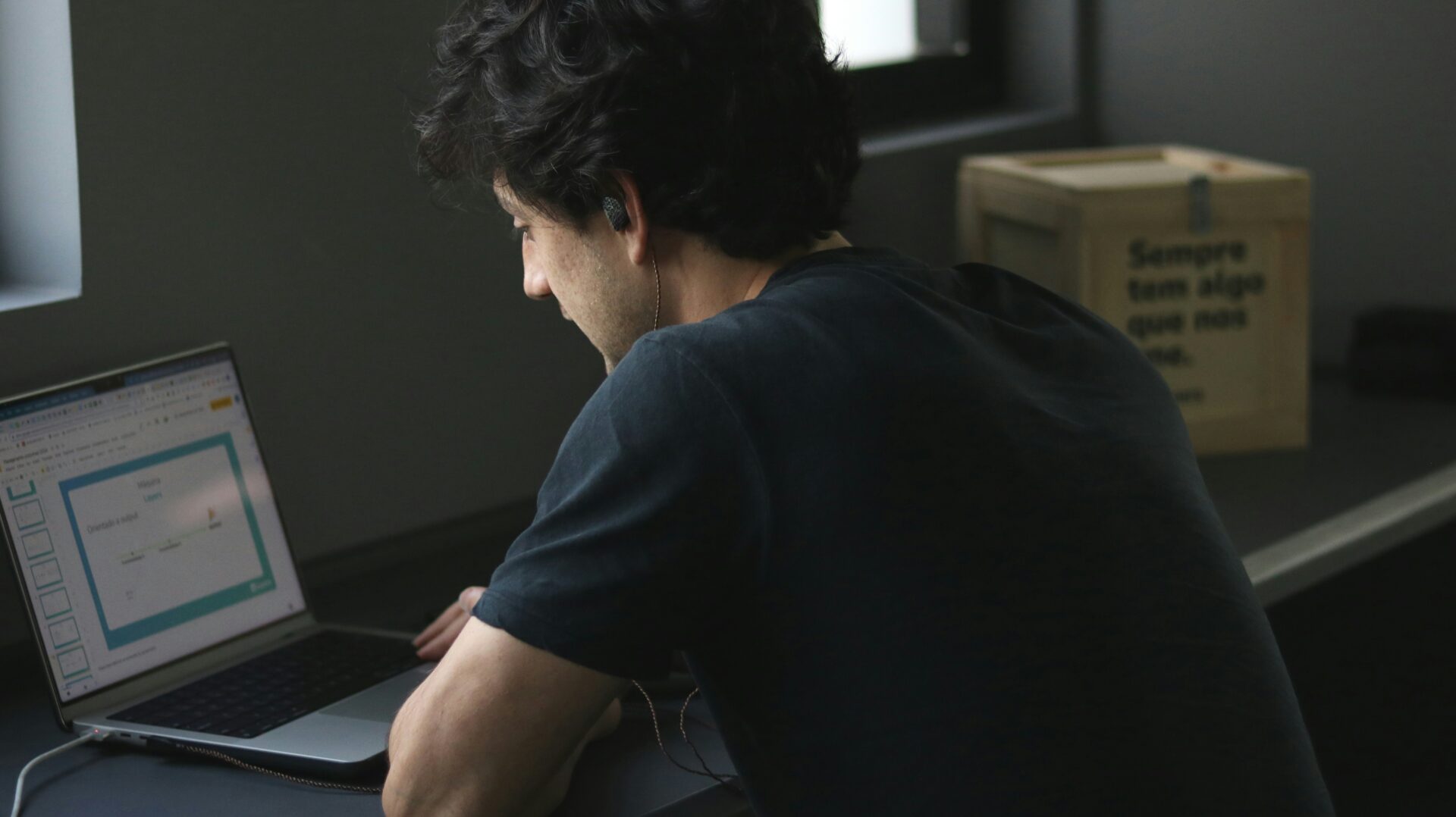
新しい事業を立ち上げるときは、思いついたアイデアをそのまま実行するのではなく、順序立てて進めることが大切です。新規事業コンサルティングでは、事業の方向性を整理するところから始まり、検証や改善を繰り返しながら、最終的に収益につながる仕組みを作っていきます。ここでは、初心者の方でも理解できるように、新規事業コンサルティングの進行ステップをわかりやすく解説します。
初期フェーズ:課題整理とヒアリング
最初の段階では、事業を進める目的や課題を整理します。ここで大切なのは「ゴールを明確にすること」と「社内外の関係者で目線を揃えること」です。
-
ゴール設定
どれくらいの売上を目指すのか、どのくらいの期間で成果を出したいのかを確認します。目標があいまいだと後で判断に迷いが出てしまうため、最初に基準を決めておくことが重要です。 -
ヒアリング
経営者や現場の担当者から意見を集め、新しい事業に期待することや不安に感じていることを整理します。 -
リサーチ計画
市場の大きさ、競合している会社、自社の強みや弱みを調べる方法を決めます。-
市場調査: お客様がどんな商品やサービスを求めているかを調べること。
-
競合分析: すでに同じようなことをしている会社がどんな特徴を持っているかを調べること。
-
戦略フェーズ:事業コンセプト設計と仮説づくり
次の段階では「どんな価値をお客様に提供するのか」を形にしていきます。
-
事業コンセプトの設計
誰に向けて、どんな悩みを解決する商品やサービスを提供するのかを具体的にします。 -
仮説づくり
「このサービスは若い世代に受け入れられるはず」「この価格なら買ってもらえるはず」といった予想を立てます。仮説を立てることで、その後に検証すべきポイントがはっきりします。
検証フェーズ:試作品やテストで反応を確かめる
いきなり大きな投資をするのではなく、小さなテストを行いながら本当に需要があるかを確かめます。
-
試作品(MVP)の活用
最小限の機能だけを備えた商品やサービスを作り、お客様の反応を見ます。
※MVP(Minimum Viable Product)=最低限の機能でつくった試作品。大きなリスクを避けながら市場の反応を確かめる方法です。 -
テストマーケティング
少人数のお客様に試してもらい、感想や改善点を集めます。この段階での学びが、将来の失敗を防ぎます。
実行フェーズ:本格的に事業を立ち上げる
検証で手ごたえを確認できたら、本格的に事業を立ち上げます。
-
販売やサービス提供の開始
実際に市場に出して販売を始めます。 -
集客や宣伝
ホームページ、SNS、広告などを使い、お客様に知ってもらう活動を行います。
フォローアップフェーズ:改善と拡大
事業を始めた後も、改善を続けることが欠かせません。
-
効果測定
売上、顧客数、リピート率などを確認し、思い通りに進んでいるかをチェックします。 -
改善活動
うまくいっていない部分を見直し、商品やサービスを改良します。 -
拡大戦略
成功が見えてきたら、対象となるお客様を増やしたり、新しい販売方法を取り入れたりして規模を大きくします。
進行ステップまとめ
|
フェーズ |
主な内容 |
目的 |
|---|---|---|
|
初期 |
課題整理・ヒアリング・リサーチ |
ゴールを明確にし、方向性を揃える |
|
戦略 |
事業コンセプト設計・仮説づくり |
提供する価値を具体化する |
|
検証 |
試作品(MVP)やテスト |
実際に需要があるかを確認する |
|
実行 |
市場投入・宣伝 |
本格的に事業を立ち上げる |
|
フォローアップ |
効果測定・改善・拡大 |
成功を安定させ、事業を成長させる |
新規事業コンサルティングの費用相場と契約形態

新規事業コンサルティングの料金は、やることの範囲(スコープ)と関与の深さ、期間で大きく変わります。一般的には、
- 単発の診断やレビューなどのスポット型
- 毎月ともに動く月額の伴走型
- 試作品づくりや実証実験まで含むプロジェクト型
- 成果に応じて支払う成果報酬型(レベニューシェア含む)
が中心です。本セクションでは、目安となる費用相場と契約の選び方・注意点を、初心者にもわかりやすく整理します。
用語補足
- MVP=最小限の機能で作る試作品。
- PoC=アイデアが実現可能か確かめる小さな実験。
- KPI=成果を測る指標。
- ROI=投資対効果。
- RFP=依頼内容をまとめた提案依頼書。
新規事業コンサルティングの費用相場の考え方
費用は「人件費×関与時間+必要経費」で組み立てられます。上流の調査・戦略設計だけなのか、下流の検証や集客実行まで入るのかで、金額は大きく上下します。以下は一般的な目安です(業界・会社規模・内容で変動します)。
目安早見表
|
契約タイプ |
想定スコープ |
期間の目安 |
費用の目安(税別) |
向いているケース |
|---|---|---|---|---|
|
スポット型(診断/レビュー) |
現状診断、戦略レビュー、壁打ち |
1回〜1ヶ月 |
30〜120万円/回 |
方向性確認、セカンドオピニオン |
|
月額の伴走型 |
調査〜仮説設計〜検証運用の並走 |
3〜12ヶ月 |
50〜200万円/月(中小)/ 200万円〜/月(大企業) |
継続的に学習と改善を回したい |
|
プロジェクト型(MVP/PoC含む) |
試作品、実証実験、GTM初期設計 |
2〜6ヶ月 |
150〜800万円/案件(内容で増減) |
実物で市場の反応を確かめたい |
|
成果報酬型/レベニューシェア |
売上・利益・CV数などに連動 |
3〜12ヶ月 |
固定小+成果5〜20%など |
初期費用を抑え、成果で支払いたい |
※GTM=市場投入の計画。広告費や制作費などの実費は別途になることが多い点に注意。
スポット型(診断・戦略レビュー)の費用相場と使いどころ
短期間で方向性を確認したいときに有効です。既存の企画書や事業計画のレビュー、課題の棚卸し、優先順位の整理などを実施。
-
費用目安:30〜120万円/回
-
メリット:短時間で論点が明確になる。稟議(社内承認)もしやすい。
-
注意点:実行までの伴走は含まれないことが多い。実装に進むなら次の契約が必要。
月額の伴走型(継続支援)の費用相場と進め方
調査、仮説づくり、テスト、見直しを毎月回す契約です。会議体の設計、KPIダッシュボード整備、実験計画、検証のレポート化まで一連で支援します。
-
費用目安
-
中小企業:50〜200万円/月
-
大企業や大規模領域:200万円〜/月
-
-
メリット:知見が社内に残る。学習スピードが上がる。
-
注意点:成果物と役割分担を明確に。追加依頼(広告運用、制作、採用支援など)は別費用になりやすい。
プロジェクト型(MVP/PoC)の費用相場と内訳
「仮説を形にして試す」ためのまとまった契約です。LP(ランディングページ)や試作品、ユーザーインタビュー、テスト広告などを組み合わせ、やる/やめる/方向転換の判断材料をつくります。
-
費用目安:150〜800万円/案件
-
内訳の例
-
調査・設計(3〜6週):リサーチ、顧客像、価値提案の言語化
-
制作・準備(2〜4週):LP/試作品、計測設定
-
検証(2〜8週):テスト配信、ユーザーテスト、改善
-
-
注意点:広告費・制作実費は別枠にするのが一般的。ここを混ぜると効果測定がぼやけます。
成果報酬型・レベニューシェアの特徴と注意点
成果に連動して支払う方式。成果の定義と測り方を先に決めるのが成功のコツです。
-
支払い方法の例:固定費少額+成果の5〜20%、または純増利益の一定割合など
-
メリット:初期費用を抑えられる。目線合わせがしやすい。
-
注意点:どの売上を対象にするか、外部要因(季節要因など)の扱い、解約条項を明記。監査可能なデータ連携もセットで合意。
工数とスコープで費用はこう変わる
費用の差は、関与時間(工数)とやる範囲(スコープ)でほぼ決まります。見積もりでは以下をチェックしましょう。
-
成果物:何が手元に残るか(調査レポート、検証計画、ダッシュボード、プレイブックなど)
-
体制:担当の人数と役割(戦略、データ、制作、広告運用)
-
頻度:定例会の回数、チャット対応の範囲、緊急対応の有無
-
変更管理:要件変更の扱い、追加費用の発生条件
-
権利関係:成果物の利用範囲、データの所有権
契約期間の目安とステージゲート
-
おすすめ構成
-
1〜2ヶ月目=調査と設計(方向性の仮決め)
-
3〜4ヶ月目=小さな検証(MVP/PoC)
-
5ヶ月目以降=拡張(うまくいった施策へ集中)
-
-
ステージゲート:区切りごとに「続ける/やめる/方向転換」をデータで判断するやり方。無駄な投資を避けるのに有効。
稟議を通すためのポイント
-
数字で語る:ROI、回収期間、KPIの基準値を先に示す。
-
リスクと対策:やめる基準、想定外が起きた時の手当て。
-
中間成果物:いつ、何が手元に残るのかを明確に。
-
スモールスタート:最初は小さく試す計画のほうが合意が取りやすい。
よくある失敗と回避策
-
安さだけで選ぶ:工数不足で検証が浅くなる。→成果物と進め方で比較する。
-
成果の定義が曖昧:成果報酬が揉める。→対象指標と測り方を契約書に明記。
-
追加費用の抜け:広告費や制作実費が想定外に。→“実費別”の範囲を事前に線引き。
-
データが見えない:効果が判断できない。→計測設定とダッシュボードを初回納品に入れる。
合同会社えいおうの料金イメージ
-
スポット診断:50万円前後/回(現状診断、優先課題の特定、アクション10項目の提示)
-
月額の伴走型:30〜150万円/月(調査→検証→見直しの月次運用、週次定例、ダッシュボード付)
-
MVP/PoCプロジェクト:100〜500万円/案件(LP/試作品、テスト広告、ユーザーヒアリング、検証レポート)
-
成果報酬オプション:固定小+成果連動(売上やCV数などに応じた割合)
※個別の目的・期間・体制に応じて調整します。広告費・制作実費は別途。
用語のかんたん解説
-
KPI:取り組みの進み具合を測る指標。例:問い合わせ数、成約率、継続率。
-
ROI:投資に対して得られた効果。かけた費用に見合う成果かを判断するもの。
-
RFP:依頼内容や要件をまとめた文書。複数社に同条件で見積もりを出してもらうために使う。
-
MVP/PoC:小さく作って早く確かめるための手法。失敗しても傷が浅いのが利点。
新規事業コンサルティングの費用は「何を、どこまで、どのくらいの期間でやるか」で決まります。金額だけでなく、成果物・体制・判断基準が明確かを基準に比較すると、失敗の確率を下げられます。合同会社えいおうでは、スモールスタートからの段階的な拡張を前提に、見える化された進め方をご提案します。
新規事業コンサルティング会社の選び方と注意点

新規事業コンサルティングは「誰に頼むか」で成果が大きく変わります。料金の安さや知名度だけで選ぶと、検証が浅くなり時間と費用のロスが発生しがち。ここでは、初心者でも迷わない判断基準と、契約前に必ず確認すべき注意点をわかりやすく整理します。
新規事業コンサルティング選定の基本方針(目的と成果を先に決める)
まず「依頼の目的」と「求める成果物」を先に言語化します。たとえば「市場調査と仮説づくりまで」なのか、「MVP(最低限の試作品)で需要検証まで」なのかで、必要なスキルや費用が変わります。
専門用語の解説
-
-
MVP:最小限の機能で作る試作品。小さく早く反応を確かめるための手法。
-
KPI:取り組みの進み具合を測る指標。例:問い合わせ数、成約率、継続率。
-
ROI:投資対効果。かけた費用に対してどれだけ効果が出たかを示す。
-
実績と再現性を見極める(事例は「結果」と「やり方」で評価)
単に成功事例の数を聞くだけでは不十分。どんな指標がどの期間でどれだけ改善したか、同じ手法を他案件でも再現できたかを確認します。
-
事例の確認ポイント
-
Before/Afterの数字(CVR、問合せ件数、回収期間など)が出ているか
-
期間と前提条件が明示されているか
-
失敗からの学びや、やらない判断をした例があるか(判断基準の透明性)
-
プロセスの型があるか
提案内容に調査→仮説→試作→検証→見直しの流れが明確かを確認。都度思いつきで動くのではなく、検証の設計書や終了条件が用意されている会社は信頼度が高いです。
体制とスキルの見極め方(伴走型か助言型かを選ぶ)
新規事業支援には、大きく伴走型(実行まで並走)と助言型(アドバイス中心)があります。自社のリソースに合わせて選びます。
-
伴走型が向くケース:社内に人はいるが、新規事業の進め方がわからない/検証設計と実装を手早く回したい
-
助言型が向くケース:実行体制はあるので、外部の視点で意思決定を磨きたい
データとマーケの一体設計ができるか
計測設定(アナリティクス)と集客施策(SEO、広告、コンテンツ)を一体で設計できるかが要。数字で議論できる体制だと稟議も通りやすくなります。
費用対効果の比較軸(安い高いではなく、成果物とKPIで見る)
見積もりは金額だけで比べないこと。何が手元に残るか(成果物)とどのKPIをどれだけ動かす計画かで比較します。
|
比較軸 |
質問例 |
見るべきポイント |
|---|---|---|
|
成果物 |
何が、いつ、どの形式で納品されるか |
調査レポート、検証計画、ダッシュボード、プレイブックの有無 |
|
範囲 |
どこまでが費用に含まれるか |
追加費用が発生する条件の明確化 |
|
体制 |
誰がどの役割を担うか |
戦略、調査、制作、広告、データの担当配置 |
|
期間 |
区切りごとの判定基準は何か |
続ける/やめるの終了条件が事前に合意されているか |
|
計測 |
KPIは何を採用するか |
定義が具体的、測定方法が現実的か |
|
ROI |
回収の考え方は? |
回収期間の目安と前提条件が説明されているか |
面談で確認したい質問
RFP(提案依頼書)を簡単でいいので作り、同条件で比較できるようにします。
-
RFP(提案依頼書)に入れる項目
目的、現状、求める成果物、期間、予算感、守秘条件、評価基準(KPI) -
面談での質問例
-
類似案件の成功・失敗の両方を教えてください(数字と期間つきで)
-
小さく試してダメだったとき、どの基準でやめる判断をしますか
-
広告費や制作費などの実費は見積もりに含みますか、別ですか
-
ダッシュボードやレポートは自社でも運用できますか(引き継ぎ前提か)
-
RFP=依頼内容をまとめた文書。同じ土俵で各社提案を比べるための基本資料。
契約形態ごとの注意点(スポット、月額、プロジェクト、成果報酬)
-
スポット(診断・壁打ち)
方向性の確認に有効。実行は含まれないことが多いので、次の契約に進む前提かを確認。 -
月額の伴走型
学習を回すのに向く。定例の頻度、対応時間、成果物を明文化。 -
プロジェクト型(MVP/検証ふくむ)
試作品とテストをまとめて実施。広告費や制作費は実費別にして効果測定を明瞭に。 -
成果報酬(レベニューシェア)
成果の定義と測り方を契約書に。外部要因(季節要因など)の扱い、解約時の精算方法も先に決める。
データ・計測・守秘(NDA)とコンプライアンスの確認
-
計測基盤:どの数値を、どのツールで測るか。アカウント権限は自社が保持するのが安心。
-
NDA(守秘義務契約):事前に締結し、競合企業への再利用を制限。個人情報や顧客データの扱いも明記。
-
データの所有権:調査データや広告アカウント、クリエイティブの権利を自社に帰属させるかを確認。
NDA=社外に情報が漏れないようにする契約。秘密情報の範囲と期間を明確にする。
稟議を通す資料の作り方
一枚サマリーに目的、KPI、期間、費用、ROIの見立て、終了条件、成果物を整理。数字で語れる提案は稟議が通りやすくなります。議論を短くするため、「やらない場合の機会損失」も併記すると効果的。
よくある失敗と回避策(トラブルを未然に防ぐ)
-
安さだけで選ぶ → 検証が薄くなり、判断材料が不足。成果物とKPIで比較する。
-
成果の定義が曖昧 → 成果報酬が揉める。対象指標・期間・測定方法を契約書に。
-
追加費用の想定漏れ → 広告費や制作実費は実費別で線引き。
-
データが見えない → 効果が判断できない。ダッシュボードを初回納品に含める。
-
属人化 → 担当者が替わると止まる。プレイブック(手順書)や引き継ぎ条件を明記。
新規事業コンサルティング会社を選ぶチェックリスト
|
項目 |
確認内容 |
OK基準 |
|---|---|---|
|
目的と成果物 |
何を、いつまでに、どの形で得たいか |
文書で合意 |
|
事例と再現性 |
数字・期間・前提条件が出ているか |
成果と失敗の両方を提示 |
|
進め方の型 |
調査→仮説→試作→検証→見直しが明確か |
終了条件がある |
|
計測と可視化 |
KPI、計測方法、ダッシュボードの有無 |
自社で継続運用できる |
|
契約条件 |
範囲、追加費用、権利関係、解約条項 |
全項目を契約書に明記 |
|
守秘とデータ |
NDA、データ所有権、アクセス権 |
自社帰属と権限保持 |
|
相性 |
担当者の説明がわかりやすいか |
納得できるコミュニケーション |
以上を押さえれば、「新規事業 コンサルティング」を安心して依頼できる土台が整います。合同会社えいおうでは、伴走型で小さく早く試し、数字に基づく合意形成を重視。費用対効果が見える進め方で、実行まで支援します。
合同会社えいおうの事業戦略コンサルティングの特徴

新規事業は、考えるだけでは前に進みません。合意を取り、試し、数字で確かめ、また直す。この当たり前を短いサイクルで回すために、合同会社えいおうは「伴走型×可視化×内製化」を柱にした事業戦略コンサルティングを提供します。戦略づくりと実行支援を切り離さず、現場で使える手順と指標を残すことにこだわります。
合同会社えいおうが提供する独自の支援スタイル
えいおうの新規事業コンサルティングは、次の3点を核に設計しています。単発の助言で終わらせず、成果が出るまで並走するスタイルです。
伴走型:机上ではなく現場で動かす
週次の打ち合わせと短い作業サイクル(スプリント)で、小さく試して早く学ぶ進め方を徹底。計画だけで終わらない体制づくりを支援します。
可視化:数字で判断する仕組みづくり
共通のダッシュボードを用意し、見るべき指標をそろえます。
-
ノーススターKPI:事業の方向を示す最重要指標。全員の物差しを合わせる指標。
-
先行指標と遅行指標:すぐ動く指標(例:問い合わせ数)と結果として動く指標(例:売上)をセットで管理。
専門用語はなるべくかみ砕き、誰が見ても同じ意味で理解できる表現に整えます。
内製化:知見を社内に残す
検証のやり方、集客の運用、レポートの作り方などを手順書(プレイブック)として残します。担当者が変わっても回る仕組みを意識。
強み1:データとSEOをつないだ事業戦略コンサルティング
戦略だけ、マーケだけでは成果が分断されます。えいおうは、調査→設計→検証→集客改善をひと続きで支援。検索経由の集客(SEO)と広告、コンテンツ運用を、計測の設計と同時に整えます。
用語解説
- SEO=検索エンジンで見つけてもらうための工夫。
- CVR=問い合わせや購入に至る割合。
初期診断からの流れ
-
現状の検索流入・広告・サイト導線を診断
-
計測設定を見直し(どの数字が、どこで取れるかを整理)
-
記事やLP(紹介ページ)の作り替え、広告テストを同時に実施
-
ダッシュボードで改善箇所を特定し、翌週の打ち手に反映
強み2:中小企業に合わせたスモールスタート設計
最初から大きな投資を求めません。まずは小さく始め、反応が確認できたら広げる進め方を基本にします。
-
ステージゲート:区切りごとに「続ける・やめる・方向転換」を数字で判断する仕組み。
-
稟議が通りやすい資料:目的、期間、費用、期待値、やめる基準を一枚に整理。
ROIの見立て:回収までの期間と前提条件を明記。
用語解説
-
稟議=社内の承認プロセス
-
ROI=かけた費用に対して得られた効果。
強み3:検証重視のMVP/PoC運用
考えた仮説は、試して初めて価値が分かります。えいおうは小さな試作品や限定テストで、実際の反応を確認していきます。
-
検証KPIと終了条件を事前に合意し、判断の迷いをなくす運用。
-
ユーザーインタビューやアンケートで「なぜ」の部分まで深掘り。
用語解説
- MVP=最小限の機能でつくる試作品。
- PoC=アイデアが実現可能かどうかを確かめる小さな実験。
強み4:経営と現場をつなぐコミュニケーション
経営は全体の方向と回収を知りたい。現場は具体的な次の一手を知りたい。えいおうは両者の視点を一枚でつなぎます。
-
経営会議用サマリー:目的、投資、成果、次の判断を簡潔に整理。
-
現場向けのタスク分解:今週やること、責任者、期日を明確化。
-
言葉の定義をそろえ、誤解による手戻りを防止。
提供メニューと成果物
実際にどんな支援と成果物が得られるのか、イメージしやすいように整理しました。内容は目的に合わせて調整します。
|
メニュー |
目的 |
主な内容 |
成果物の例 |
期間目安 |
|---|---|---|---|---|
|
スポット診断 |
現状の整理と優先順位づけ |
データ確認、課題抽出、打ち手提案 |
課題一覧・優先度表、アクション10項目 |
2〜4週間 |
|
伴走支援(月額) |
学習サイクルの定着 |
週次定例、改善施策の設計と実行、レポート |
週次レポート、ダッシュボード、プレイブック |
3〜12ヶ月 |
|
MVP/PoCプロジェクト |
仮説の検証 |
試作品/LP作成、テスト広告、ユーザー調査 |
検証計画、実験結果、次の判断資料 |
2〜3ヶ月 |
|
GTM初期設計 |
市場投入の型づくり |
ターゲット・メッセージ・チャネルの整理 |
セールス資料、サイト構成、運用計画 |
1〜2ヶ月 |
|
計測基盤構築 |
数字での合意形成 |
計測設定、KPI設計、可視化 |
ダッシュボード、指標定義集 |
3〜6週間 |
用語解説
- GTM=市場へ出すときの設計。誰に、何を、どうやって届けるかの計画。
進め方の標準プロセス(えいおう方式)
-
キックオフ:目的と成功の基準をそろえる
-
探索:市場・顧客の調査、競合の把握
-
設計:価値提案、価格やチャネルの整理
-
検証:小さく試し、結果を記録
-
拡張:手ごたえのある打ち手に集中
各段階の出口基準(合格ライン)を事前に決めておき、迷いのない判断を支援します。
よくあるご相談と、えいおうの解き方
-
「アイデアはあるが、どこから手をつけるべきか分からない」
→ 現状診断で優先順位を決め、2週間で初回の小さな検証まで進めます。 -
「社内の承認が進まず、動きが止まっている」
→ 稟議用の一枚サマリーと、やめる基準を先に定義。迷いを減らします。 -
「数字がバラバラで、効果が評価できない」
→ 計測設定を整理し、共通ダッシュボードを用意。用語の意味も統一します。
用語の簡単解説
-
ノーススターKPI:事業の本質的な価値を一番よく表す指標。全員が同じ方向を見るための“北極星”。
-
ユニットエコノミクス:1人の顧客あたりで収益がプラスかを見る考え方。LTV(顧客生涯価値)とCAC(獲得コスト)で判断。
-
プレイブック:やり方をまとめた手順書。担当が替わっても同じ品質で回せる土台。
えいおうの事業戦略コンサルティングは、「小さく早く試す」「数字で語る」「やり方を残す」の三拍子を重視します。新規事業コンサルティングに迷いがある場合もご安心ください。目的に合わせたスモールスタートから、堅実に成果へつなげます。
未来を共創するパートナーとしての第一歩

新規事業は、一人では抱え込みきれない不確実性との戦いです。合同会社えいおうは、机上の計画で終わらせず、現場で試し、数字で確かめ、素早く学び直すための仕組みづくりを一緒に行います。本セクションでは、新規事業コンサルティングを検討中の方が「今日から動ける」具体的な第一歩を整理しました。やることが見える、効果が測れる、社内合意が取りやすい——そんな進め方の全体像を提示します。
新規事業コンサルティングで到達したいゴールの再確認
新規事業支援の目的は、アイデアの数ではありません。再現性ある進め方を確立し、ムダを減らしながら結果に近づくこと。えいおうの事業戦略コンサルティングは、以下のゴールを狙います。
-
顧客の課題と解決価値を、言葉と数字で説明できる状態
-
小さな検証で「やる・やめる・方向転換」を判断できる状態
-
集客から改善までが一気通貫で回る運用体制
-
稟議が通る資料と、継続的に学べる指標設計
すべての施策は、このゴールに結びつくよう設計します。
はじめの7ステップ(最短2週間のスモールスタート)
最初から完璧を目指さず、小さく素早く回すのが要点。次の順番で進めると迷いが減ります。
-
目的の言語化
どの顧客に、どんな価値を届け、どの数字を動かしたいかを明確化。曖昧な目標は後の判断を濁します。 -
現状の整理
使える資産(顧客リスト、既存チャネル、強み)と制約(期間、予算、人員)を棚卸し。 -
仮説の作成
誰の、どの課題を、どの方法で解くのか。価格やチャネルの当たりも書き出す。 -
試作の準備(小さく)
紹介ページ(LP)や簡易プロトタイプを用意。いきなり大規模開発は避けます。 -
検証の実施
少額のテスト広告や小規模トライアルで反応を確認。結果を数字で記録。 -
判断と見直し
合格ラインに届いたかを確認。届かなければ原因を特定し、修正して再挑戦。 -
稟議用の1枚資料作成
目的、結果、次の打ち手、必要な費用を簡潔に。合意形成を早めます。
初回無料診断(例)で確認する3つのポイント
無料診断では、施策の数よりも「結果への道筋」を重視します。
-
誰に向けて、どの価値を、どのチャネルで届けるか
-
どの指標で成果を測り、どこまでいけば合格とするか
-
2週間で実施できる最小の検証案(必要な作業と役割)
この三点が明確だと、動き出しが一気に軽くなります。
準備しておくとスムーズなチェックリスト
以下を用意できると、打ち合わせが短く、検証が速くなります。
|
項目 |
中身 |
なぜ必要か |
|---|---|---|
|
顧客像のメモ |
想定する年齢・役割・困りごと |
仮説の的を絞れる |
|
既存の窓口 |
サイト、SNS、営業資料 |
使える資産の把握 |
|
競合の候補 |
3〜5社、強みと弱み |
差別化の方向を確認 |
|
数字の現状 |
相談件数、成約率など |
目標設定の土台 |
|
社内体制 |
決裁の流れ、関係者 |
稟議の詰まりを予防 |
作り込みは不要。事実メモで十分です。
成果が見える運用ルール(KPI/終了条件/稟議資料)
新規事業では、あらかじめ「線引き」を決めることが大切です。
-
KPI(重要指標):問い合わせ数、成約率、継続率など。用語の定義も合わせます。
-
終了条件:合格ラインに満たなければ、やめる・縮小する・方向転換する——この基準を先に決めておきます。
-
稟議資料:目的、期間、費用、結果、次の判断を1枚に。議論の回数を減らせる設計。
用語解説
- KPI:取り組みの進み具合を測る指標。
- 終了条件:続けるかやめるかの判断基準。
- 稟議:社内で承認を得る手続き。
よくある質問
Q. 予算が限られています。効果は出せますか?
小さく試す設計により、限られた予算でも学びを最大化。成果が見えた打ち手に集中的に投資します。
Q. どのくらいの期間で結果が分かりますか?
仮説検証なら2〜4週間で傾向が判定可能。本格展開は結果を見て段階的に。
Q. 社内にノウハウを残したいのですが?
手順書(プレイブック)とダッシュボードを整備。担当交代があっても運用が続く設計にします。
合同会社えいおうの事業戦略コンサルティング
合同会社えいおうでは、中小企業様向けに事業戦略設計のコンサルティングサービスを展開しております。
事業戦略コンサルティングでは、事業に関する経営戦略を支援するだけではなく、この記事でご紹介したようなIT導入、IT導入に関わる補助金の取得申請もサポートしております。
- 売上が停滞しており、次の成長戦略が見えない
- 市場環境の変化に適応できていない。
- ビジネスモデルの拡張、投資家対応、資金調達などに課題を感じている。
- 売上はあるが利益が少ない、キャッシュフローが回らない。
- どの市場に進出すべきか、どのようなビジネスモデルが適しているかがわからない。
- DXの必要性は感じているが、どのツールを導入すべきか判断できない。
- 海外展開の進め方、現地パートナーの探し方がわからない。
このようなお悩みを抱えている企業様に向け、事業戦略の設計により事業体質の改善を支援します。IT、およびITを活用するための補助金を利用して、費用対効果の高い事業成長を目指しましょう。
机上の空論ではなく、商品企画、集客施策、営業体制を含めた各分野に対してマーケティングの知識を持った実務レベルのサポートを致します。














